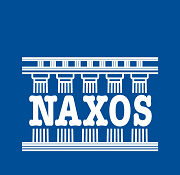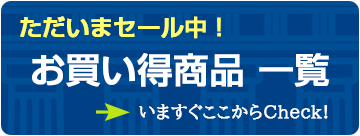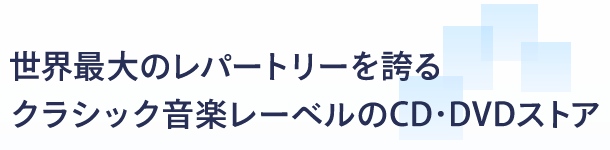交響曲 最新アルバム
43 件 / 43件中
-
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 第9番 ニ短調 WAB 109 (原典版) [パーヴォ・ヤルヴィ、チューリヒ・トーンハレ管弦楽団]発売日:2024年08月23日
CD国内仕様 日本語解説付き価格:3,300円(税込、送料無料)
パーヴォ・ヤルヴィ、ブルックナー第九を15年ぶりに再録音パーヴォ・ヤルヴィとトーンハレ管によるブルックナー後期三大交響曲のラストを飾るのは、フランクフルト放送響との録音から15年ぶりとなる第9番。版は今回「原典版」としか表記されていませんが、旧録音で使用したコールス版ではなくノーヴァク版を基調としている模様です。旧録音と比較するとスケルツォを除いて両端楽章は大幅に速くなっており、第1楽章で約1分40秒、第3楽章に至っては約3分も演奏時間が短くなっています。 旧録でゆったりめであった第1楽章は今回全体が引き締められた印象ですが、緩急を大きめに取って各主題の特性を生かしており、コーダでは思い切ったためも聴かせています。第2楽章では詳細なスコアリーディングに基づくコントロールで各パートが埋もれることなく明快に鳴り、オーケストレーションの面白さを鮮明に打ち出してブルックナーの意図した響きを強調。加えてタイトなアクセントで躍動感のある音楽を生み出しています。音楽的な流れを強く意識した第3楽章はたっぷりとした表情で速いという印象はほとんど無く、コラールが際立った極めて美しい演奏に仕上がりました。 オーケストラは前作第8番同様ヴァイオリンを両翼に配置し、チェロの後ろとなる左奥にコントラバス、その右隣りにホルン・セクションが並び、その後列ワーグナー・チューバ持ち替えの隣、全体の中央奥にバス・チューバ、その右にトロンボーン、一番右にトランペットというもの。低音金管楽器とティンパニが中央に配され、独特の安定感が得られています。 国内仕様盤には舩木篤也氏による日本語解説が付属します。
収録作曲家:
-
ハイドン(1732-1809):
〈後期交響曲集 第3集〉
交響曲 第99番-第101番 [アダム・フィッシャー(指揮)、デンマーク室内管弦楽団]発売日:2024年08月09日
CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
アダム・フィッシャー、ハイドンへ還る。
後期交響曲の再録音第3集!ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、マーラーの全交響曲を録音した唯一の指揮者アダム・フィッシャーが、デンマーク室内管弦楽団の 首席指揮者就任25年を記念してスタートさせたハイドンの後期交響曲の再録音、第3集です。演奏は彼自身の旧全集に比べると更にシェイプアップ、テンポアップされており、ダイナミックスの切り替えやアクセントも鮮烈。随所に即興的な装飾を加えるなど、ディテールにも凝っています。 近年の歴史的アプローチから得た経験や情報を参考にしつつも、フィッシャーがオペラやオーケストラの演奏で積み重ねてきた様々な表現の手法を駆使して迫力と遊び心を存分に備えた個性的な演奏は、ハイドンの作品が演奏者に許容する懐の深さも感じさせるものとなっています。 この第3集には表題付きの2曲を含む第99番から第101番の3曲を収録。第99番は1793年、ロンドン再訪の出発直前にウィーンもしくはアイゼンシュタットで作曲され、翌年の2月10日にロンドンで初演されました。クラリネットが編成に入る初の交響曲です。第100番は、当時流行していた「トルコ風」の楽器、シンバルとトライアングルの両方が用いられており、また第2楽章に使われたトランペットが軍隊ラッパを模していることから「軍隊」と呼ばれる作品。もともとこの第2楽章は『2つのリラ・オルガニザータのための協奏曲第3番 ト長調』からの転用ですが、最後にティンパニとトランペットが加えられて盛大に盛り上がります。第101番は、第2楽章の弦楽器とファゴットの刻むリズムから、長い間「時計」というあだ名が付けられてきました。 ※国内仕様盤には音楽評論家、八木宏之氏の解説が付属します。収録作曲家:
-
ベートーヴェン(1770-1827):
交響曲 第3・5・7・9番他
(マーラー版によるベートーヴェン作品のすべて) [マイケル・フランシス(指揮)/ラインラント=プファルツ州立フィルハーモニー管弦楽団 他]BEETHOVEN, L. van: Mahler Re-Orchestrations - Symphonies Nos. 3, 5, 7, 9 / String Quartet No. 11 (Rheinland-Pfalz State Philharmonic, M. Francis)
発売日:2024年07月26日
 NMLアルバム番号:C5484
NMLアルバム番号:C5484CD 3枚組国内仕様 日本語解説・歌詞対訳付き価格:4,950円(税込、送料無料)
マーラー版のベートーヴェンを網羅した画期的アルバムが登場!
引き締まった演奏にも注目ウィーン・フィルの指揮者などを歴任したマーラーが、先輩作曲家たちの作品の演奏にあたりオーケストレーションに手を入れていたことは広く知られており、それぞれに録音も出ていますが、そのうちベートーヴェン作品をすべて演奏・収録したアルバムはありそうで無かった企画の一つ。すぐれた作曲家の眼を持つ練達の指揮者マーラーの思考を系統的に追うのに好適なセットです。 マーラー自身の交響曲は曲も編成も大規模なものですが、彼が過去の作品に行った変更は少し方向が違います。場所により弦楽器に管楽器を重ねる、弦の細かなフレーズを強調するために管のパートを省く、管の動きにオクターヴを付与する、といった楽器間のバランスを整えて効果的に響かせるためのものが多く、また細かな演奏指示も書き込まれており、指揮者マーラーがどのパートを重視したか分かるのが興味深いところです。また金管楽器の改良や用法の変遷に伴って、かつては音が出なかった旋律が足されたり、高すぎる音を下げるといった処理も行われています。 しかしながら、ホルンは基本的に倍管となっており、「第九」はティンパニ2人を擁するマーラーらしい巨大編成へと変貌していることも事実。「英雄」葬送行進曲フーガのクライマックスや第4楽章コーダ前にティンパニが加筆されていたり、「第九」第1楽章で低弦にトロンボーンを重ねたり第4楽章でコントラファゴットのサポートにチューバが動員されたりといったところは、なかなか衝撃的でもあります。 英国出身の指揮者マイケル・フランシスが2019年から首席指揮者を務める手兵オケを指揮してこれらを次々と浮き彫りにしてゆきます。 (曲目・内容欄に続く)収録作曲家:
-
〈#bruckner2024〉
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 第9番 ニ短調
交響曲 ヘ短調 [マルクス・ポシュナー(指揮)/リンツ・ブルックナー管弦楽団]BRUCKNER, A.: Symphony No. 9 (1894 version, ed. L. Nowak) (Complete Symphony Versions Edition, Vol. 17) (Linz Bruckner Orchestra, M. Poschner)
発売日:2024年07月05日
 NMLアルバム番号:C8096
NMLアルバム番号:C8096CD 2枚組国内仕様 日本語解説付き価格:2,970円(税込)
#bruckner2024、遂に完結。
最終巻はブルックナーの交響曲の最初と最後を一堂に収録CAPRICCIOレーベルと国際ブルックナー協会の主導でブルックナーの交響曲全11曲全18バージョン(稿)を録音するプロジェクト、#bruckner2024が遂に完結。同一指揮者による全稿録音は史上初の快挙ですが、最新の知見を援用した解釈と、ブルックナーの細かい指示を丹念に踏まえたポシュナーの指揮によって新たなブルックナー像を提示することに成功。「私たちが習慣にしてきた聴き方と伝統と見なしてきたものを問い直す企画」としてICMA(International Classical Music Award)2024の特別賞を受賞しました。 最終巻にはブルックナーの交響曲創造の出発点となった交響曲ヘ短調(別名「習作交響曲」、通称「第00番」とも)と未完の遺作となった第9番を収録。どちらも異稿は無く、使用楽譜はノーヴァク版ですが、このプロジェクトに一貫する「スコアの読み直し」によって新鮮なサウンドと解釈が聞かれます。 ヘ短調の交響曲はブルックナーが作曲の師キツラーに提出した最終課題の一つ。ブルックナー自身はこれを出版することを考えていた形跡があり、自信作であったことがうかがわれます。ポシュナーはリピートを省いているので全曲の演奏時間は34分弱。インバル盤(Teldec、現Warner)の46分余りに比べてだいぶ短くなっていますが、シューマンやメンデルスゾーンに連なるドイツ・ロマン派の風合いを感じさせる、颯爽としてチャーミングな作品として独自の魅力を提示しています。 (曲目・内容欄に続く)収録作曲家:
-
ロレンゾ・フェルナンデス(1897-1948):
組曲「田園風東方の三博士祭」
交響曲 第1番
交響曲 第2番「エメラルド・ハンター」 [ファビオ・メケッティ (指揮)/ミナスジェライス・フィルハーモニー管弦楽団]LORENZO FERNÁNDEZ, O.: Symphonies Nos. 1 and 2, "O Caçador de Esmeraldas" / Reisado do pastoreio (Minas Gerais Philharmonic, Mechetti)
発売日:2024年06月07日
 NMLアルバム番号:8.574412
NMLアルバム番号:8.574412CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
20世紀に活躍したブラジルの多くの作曲家と同様、フェルナンデスは民族主義的な作風から出発し、それらを国際的な技法や様式と統合することを試みました。 「田園風東方の三博士祭」組曲は初期の民族主義的な路線による代表作。クリスマスをモチーフにした親しみ易い音楽で、特に覚えやすくノリ易い第3曲「バトゥーキ」はブラジル管弦楽名曲集の定番の一つ。2022年に東京で行われたブラジル独立記念200周年コンサートでも演奏され喝采を博しました。 交響曲第1番はバルトークに影響されて書いた4楽章形式の力作。古典的な構成による純粋音楽を目指しつつもブラジルらしいリズムや旋律が随所に顔を出します。エメラルドを求めて密林に入り、先住民や大自然の脅威に直面した冒険家を描いた第2番は標題音楽の性格が強く、ドラマティックな作品。作曲者は初演を聴くことなく世を去りました。 ※国内仕様盤には木許裕介氏(指揮者/日本ヴィラ=ロボス協会会長)の日本語解説が付属します。
収録作曲家:
-
〈#bruckner2024〉
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 第3番 ニ短調(第2稿)
アダージョ(1876年) [マルクス・ポシュナー(指揮)/ウィーン放送交響楽団/リンツ・ブルックナー管弦楽団]BRUCKNER, A.: Symphony No. 3 (1877 version, ed. L. Nowak) (Complete Symphony Versions Edition, Vol. 16) (ORF Vienna Radio Symphony, M. Poschner)
発売日:2024年06月07日
 NMLアルバム番号:C8095
NMLアルバム番号:C8095CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,970円(税込)
CAPRICCIOレーベルと国際ブルックナー協会の主導で、ブルックナーの全交響曲のすべての稿を録音する企画 「#bruckner2024」の第16弾。 ブルックナーがワーグナーに献呈したことで「ワーグナー」のニックネームを持つ第3番には3つの稿があり、改訂の度に全体は短くなって、ワーグナー作品からの引用は削られてゆきます。第3稿の完成時にはブルックナーは第5番まで書き終えており、その経験が反映されていますが、この経過を「完成度を高めた」と取るか、「オリジナリティが減じた」と取るか、研究者でも評価が分かれます。CAPRICCIOの#bruckner2024では3つの稿すべてに加え、第1稿と第2稿の間に作曲された1876年のアダージョも収録(ノーヴァクが「アダージョ2」と命名したもの)。これで第3番創作と改訂の軌跡を同一指揮者の解釈でたどれることとなりました。 ポシュナーの解釈は重々しいサウンドやテンポから決別し、見通しよく、細部の指示をわかりやすく音にしてゆく姿勢で当初から一貫してきました。1876年のアダージョにはティントナーやヴァンスカの録音があり、いずれも演奏時間20分を越えますが、ポシュナーは約16分。瞑想性よりも清らかな抒情が感じられます。それでも第2稿(1877年)の第2楽章(アンダンテ…クワジ・アダージョ。演奏時間約14分)と比べると、この微妙なテンポ指定の違いをしっかりと認識して指揮していることがわかります。こうした態度は、異稿の録音が集積された今こそ意義や効用があらためて実感されることでしょう。 ブルックナー研究家のウィリアム・キャラガンはブルックナーの異稿について「自分の好み、理想の姿、究極の形を探すのはやめよう。すべてのスコアには価値がある。特に第3番は傑作だ。どのような姿であろうとも」と語っており、その言葉に感じるところのあるファンには是非聞いて頂きたい1枚です。 ※国内仕様盤には石原勇太郎氏(音楽学/国際ブルックナー協会会員)による日本語の解説が付属します。
収録作曲家:
-
リース(1784-1838):
交響曲 第1番&第2番 [ヤンネ・ニソネン(指揮)/タピオラ・シンフォニエッタ]発売日:2024年05月10日
 NMLアルバム番号:ODE1443-2
NMLアルバム番号:ODE1443-2CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,970円(税込)
にわかに脚光を浴びるリースの交響曲。北欧から全集録音がスタート!フェルディナント・リースは人気コンポーザー・ピアニストとして欧州各地を席巻し、ピアノ・ソナタやピアノ協奏曲をはじめ、交響曲、弦楽四重奏曲からオペラやオラトリオに至る幅広いジャンルに作品を書きました。しかし師が余りにも偉大であったためか、「ベートーヴェンの弟子」のイメージが強く、その交響曲もベートーヴェン作品を思わせるフレーズが出て来ることに関心が向けられがちで、なかなか独自の評価を得られずにいました。 状況が変わったのは2020年代になってから。日本でリースの評伝が出版され、2024年2月には飯森範親の指揮でパシフィック・フィルハーモニア東京が全曲演奏会を開始。更にリースが1813年に演奏会を行ったことのあるフィンランドのONDINEから交響曲全集の開始が発表されたのです。 リースの交響曲全集録音はハワード・グリフィス指揮、チューリヒ室内管(1997-2002、cpoレーベル)が今のところ唯一の存在。ここに登場したニソネン盤はオケのサイズは大差無いと思われますが、アプローチにはかなり違いがあります。基本テンポが快速であること、舞曲を思わせるフレーズでの軽やかに跳ねるような処理、アクセントの利いたティンパニやブラスなど、古楽演奏のスタイルに通じる点が多く、音色は多彩で楽想ごとの表情付けは細かく且つ濃密。ころころと表情を変えてゆくリースの音楽を、爽快な流れに乗って細大漏らさず伝え、その創意の豊かさで聴き手を驚かせます。 世界初の全集として高品位のスタンダードを目指したであろう端正なグリフィス盤に対して、ニソネン盤は作品の持つ感情表現のポテンシャルを引き出すことに挑戦し、見事な成果を挙げています。ベートーヴェンの名を借りなくても、聴く人を驚かせ感心させる作品であることを知らしめる快演と言えるでしょう。 (曲目・内容欄に続く)
収録作曲家:
-
〈HAYDN 2032 第15集〉
~王妃~
ハイドン(1732-1809):
交響曲 第50番・第62番・第85番 [ジョヴァンニ・アントニーニ、バーゼル室内管弦楽団]発売日:2024年05月03日
CD国内仕様 解説日本語訳付き価格:3,300円(税込、送料無料)
後期の傑作群への推移を示す充実作3作。
スリルと深みの交錯はアントニーニならでは!40年近くの歳月を通じて100曲以上の充実した交響曲を書き、門弟ベートーヴェンの同分野における新境地の開拓を導いた“交響曲の父”ハイドン。作曲家生誕300周年の2032年までに、時に関連作も交えつつ現存する彼の交響曲を全て録音する「HAYDN 2032」プロジェクトで指揮を務めるのは、古楽器演奏の分野で目覚ましい存在感を発揮し続けてきた異才ジョヴァンニ・アントニーニ。2014年の企画開始以来、指揮者と演奏者たちの才気と深い洞察が隅々まで行き届いた才気煥発な新解釈で注目を集めてきました。 入念かつ順調に中盤に差し掛かったプロジェクトの第15弾に選ばれたのは、ハイドンの作曲活動の拠点エステルハージ侯爵家での創造力の結実が遠隔地から注目を集めつつあった作曲家40~50代の充実作3曲。宮廷劇場を沸かせた舞台音楽に由来するドラマティックな書法を駆使、民俗調と知的洗練の間でスリリングなバランスを聴かせるハイドン随一の手腕の魅力に、アントニーニのタクトが余すところなく光を当ててゆきます。 ナチュラル金管やティンパニが華やかに活躍する第50番、全楽章が同一調による異色の第62番、そしてフランス王妃マリー=アントワネットが愛したという逸話で知られる「パリ交響曲」中の白眉・第85番…古楽器を使いこなすバーゼル室内管弦楽団の妙演もさることながら、最新研究を踏まえた背景解説(英仏独3言語、国内仕様盤では追補情報を含む日本語全訳付き )、テーマに沿った美麗写真を多数含むブックレットの充実もこのシリーズならでは。 作風の深まりに垣間見るハイドンの底知れぬ深さに気づかされる3曲、今回もじっくりお楽しみください。収録作曲家:
-
〈#bruckner2024〉
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 第1番 ハ短調(第2稿/ブロシェ版)
スケルツォ(1865年/グランジャン版) [マルクス・ポシュナー(指揮)/リンツ・ブルックナー管弦楽団]BRUCKNER, A.: Symphony No. 1 (1891 revision, ed. G. Brosche) (Complete Symphony Versions Edition, Vol. 15) (Linz Bruckner Orchestra, M. Poschner)
発売日:2024年05月03日
 NMLアルバム番号:C8094
NMLアルバム番号:C8094CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,970円(税込)
CAPRICCIOレーベルと国際ブルックナー協会の主導で、ブルックナーの生誕200年にあたる2024年中にブルックナーの全交響曲のすべての稿(バージョン)を録音する企画 「#bruckner2024」の第15弾。 交響曲作家ブルックナーのデビュー作「第1番」をめぐる興味深いアルバム。最後に収められた1865年作のスケルツォは第1番のスケルツォ楽章として作曲されたと見られますが、後に差し替えられたため、演奏・録音の機会に恵まれませんでした。主部は第1稿、第2稿のスケルツォとは別物ですが、トリオの素材は共通しており、ブルックナーの音楽的成長を知る上で興味深いものです。ここでは1995年に出版された楽譜を使用。もはやブルックナーのスペシャリストの感のある当コンビの録音は貴重な資料となります。 交響曲第1番は1865年に着手され、翌66年に完成(第1稿)、68年にリンツで初演された後、1877年以後数回の改訂を経て91年に改訂版(第2稿)が完成しました。2つの稿の間には基本的な素材や構造の面では大きな違いはありませんが、第8番までの経験をふまえて世に出された第2稿ではオーケストレーションがより熟達し、アーティキュレーションやフレーズは理解しやすいように整えられています。 この点をブルックナーのオリジナルの発想が薄められたと見るか、完成度が高められたと取るか、評価の分かれるところですが、作曲家が公認して出版した演奏会用バージョンとしての第2稿の地位が揺らぐことはなく、両者を比べて楽しみたいところです。 ※国内仕様盤には石原勇太郎氏(音楽学/国際ブルックナー協会会員)による日本語の解説が付属します。
収録作曲家:
-
リース(1784-1838):
交響曲全集[4枚組] [ハワード・グリフィス(指揮)/チューリヒ室内管弦楽団]発売日:2024年05月03日
CD 4枚組国内仕様 日本語解説付き価格:6,600円(税込、送料無料)
“ベートーヴェンの愛弟子”が、8作もの交響曲を世に送り出していた……日本国内のプロ/アマチュアオーケストラでも演奏機会が増えつつあるフェルディナント・リース(1784-1838)の交響曲、世界唯一の全集が国内仕様盤としてリリース。 1784年にボンで生まれたリースは1801年にウィーンに移り、ベートーヴェンに師事。後に人気コンポーザー・ピアニストとして欧州各地を席巻しました。ピアノ・ソナタやピアノ協奏曲を始め、交響曲、弦楽四重奏曲からオペラやオラトリオに至る幅広いジャンルに作品を書いたのは師ベートーヴェンに通じます。作風は盛期古典派様式から初期ロマン派のスタイル。8曲の交響曲はすべてオーソドックスな4楽章構成で、曲想も構成も親しみ易く、ベートーヴェン作品を思わせるモチーフが随所に登場します。 2024年2月にはパシフィックフィルハーモニア東京が飯森範親の指揮で交響曲第1番が日本初演されたのに続き、7月には同メンバーにて交響曲第2番の日本初演も予定されているなど、ますます古典派の作曲家としてのフェルディナント・リースへの注目が高まっています。 国内仕様盤には『ベートーヴェンの愛弟子~フェルディナント・リースの数奇なる運命』の著者、かげはら史帆氏による日本語解説が付属します。
収録作曲家:
-
マーラー(1860-1911):
交響曲 第4番 ト長調
(エルヴィン・シュタインによる室内アンサンブル版) [ララ・マレッリ、アンドレア・カッペレーリ (指揮)、アンサンブル・キャント・テル・イット]発売日:2024年08月16日
CD価格:2,175円(税込)
20世紀初頭のウィーンでシェーンベルクによって設立された「私的演奏協会」。ここではマーラーやブルックナー、ヨハン・シュトラウスらの作品を室内楽編成に編曲したものを愛好家たちが楽しんでいました。 エルヴィン・シュタインはシェーンベルクの弟子で、団体の設立にも尽力、さまざまな編曲版を提供した作曲家です。このマーラーの第4番は1921年の編曲で、編成は木管楽器、弦楽五重奏、打楽器、ハルモニウム、ピアノという小ぶりなもの。作品のテクスチャーが際立つ透明感溢れる音色に仕上がっています。 演奏する「アンサンブル・キャント・テル・イット」はイタリア、ノヴァーラの「グイード・カンテッリ」音楽院で結成され、アンサンブル名もCantelliへのオマージュを込めたものです。主として作曲コンクール「アルモニエ・デッラ・ナトゥーラ」の作品の初演や、ノヴァーラ音楽院の作曲科の学生たちたちの作品の演奏に携わっています。 アンドレア・カッペッレーリは、歌劇、古典派から現代音楽まで幅広いレパートリーを持つ指揮者。イタリアを中心に世界中で演奏活動を行い好評を博しています。
収録作曲家:
-
フランケッティ(1860-1942):
交響曲
交響的印象「黒き森にて」
ヴォルフ=フェラーリ(1876-1948):
室内交響曲 [ローマ交響楽団、フランチェスコ・ラ・ヴェッキア(指揮)、ミンアンサンブル-9]発売日:2024年08月09日
CD価格:1,900円(税込)
イタリアの後期ロマン派の作曲家、アルベルト・フランケッティとエルマンノ・ヴォルフ=フェラーリ。両者とも優れた歌劇を遺しましたが、生粋のイタリア人でなかったことも共通点として挙げられます。イタリア貴族の父とウィーン出身の母の下に生まれたフランケッティは何不自由ない少年時代を送り、ヴェネツィアとドイツで学びました。 このアルバムに収録された交響曲ホ短調は、ドレスデン音楽院の卒業試験の一環として書かれた曲。ドイツ伝統の形式に則った荘厳かつ色彩豊かなオーケストラの音色を駆使した作品です。 40歳の時の交響的印象「黒き森にて」はライン渓谷の森と自然の美しさからインスピレーションを得た描写的な曲。角笛の響きを思わせる冒頭に始まり、全編穏やかな曲調で書かれています。 ドイツ人の画家の父とイタリア人の母を持つヴォルフ=フェラーリは《マドンナの宝石》や《スザンナの秘密》などの歌劇が知られています。この室内交響曲は彼が長年過ごしたドイツで作曲されたもので、小ぶりな編成から生まれる透明感溢れる響きが魅力的。ピアノを交えた各々の奏者の技巧が際立つ美しい作品です。
収録作曲家:
-
アルベルガ(1949-):
〈管弦楽作品集〉
交響曲 第1番 「ストラータ」他 [トーマス・ケンプ(指揮)、BBC交響楽団、カスタリアン四重奏団]発売日:2024年08月09日
CD価格:2,325円(税込)
ジャマイカ出身、現在はイギリスを拠点とする作曲家エリナー・アルベルガの管弦楽作品集。彼女は5歳でピアニストになることを決意するとともにこの頃から作曲もはじめました。地元ジャマイカの音楽学校で基礎を学んだ後、ロンドンの王立音楽アカデミーに留学し研鑽を積み、卒業後はピアニストとして活動しましたが、2001年から作曲に専念し、数多くの作品を発表しています。2021年の誕生日には、英国音楽界への高い貢献が称えられ、大英帝国勲章(Order of the British Empire)が授与されるなどますます注目が高まっています。 彼女の作品は複雑なハーモニーとダイナミズム、繰り返されるリズム・パターンが特徴。近年は不協和音の使用も目立つなど作風の変遷も見られますが、とりわけジャマイカの民族音楽の要素やジャズが取り入れられたピアノ曲などは高く評価されています。 このアルバムには、アルベルガの親友でヴァイオリニスト、デイヴィッド・エンジェルの死を悼んで作曲した「タワー」、彼女初の交響曲で、地球の構造からインスピレーションを得たという「ストラータ」と、神話の登場人物たちを描いた「神話」の3作品を収録。 演奏は、トーマス・ケンプが指揮するBBC交響楽団。「タワー」ではカスタリアン弦楽四重奏団も参加し、力強く創造性溢れる作品を存分に聴かせます。
収録作曲家:
-
ジョルジュ・プレートル&
シュトゥットガルト放送交響楽団名演集
ベートーヴェン:英雄
ベルリオーズ:幻想交響曲
レスピーギ:ローマの松&噴水
ストラヴィンスキー:火の鳥他 [ジョルジュ・プレートル(指揮)、シュトゥットガルト放送交響楽団]発売日:2024年08月09日
CD 8枚組価格:6,075円(税込、送料無料)
ジョルジュ・プレートル生誕100年記念。
首席指揮者を務めたシュトゥットガルト放送響とのホットなライヴ音源集が登場。初出ありジョルジュ・プレートル(1924-2017)の生誕100年にあたる2024年8月14日を前に、SWR(南西ドイツ放送)のアーカイヴから貴重なライヴ録音集が登場。フランス生まれのプレートルはトランペットを学んだ後、デュリュフレに和声を、クリュイタンスらに指揮を学びました。歌劇場でのキャリアが豊かで、パリ・オペラ座、スカラ座、コヴェント・ガーデン、メト、ウィーン国立歌劇場などで活躍し、マリア・カラスがキャリアの後期において頼りにした指揮者の一人としても知られました。プーランクと親交があり、彼の作品の録音は高い評価を得ました。 日本でのプレートルの人気がブレイクしたのは2008年。元旦にウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートに初登場し、年末にはウィーン交響楽団とのマーラーの第5番が2008年度のレコード・アカデミー賞交響曲部門を受賞して、ドイツ・オーストリア音楽における巨匠として大きく注目されました。更に2010年にはニューイヤー・コンサートに再登場(最年長記録)、秋にはウィーン・フィルとの日本公演を指揮して非常に強い印象を残したのでした。 シュトゥットガルト放送交響楽団での任期は1996年から98年と長くはありませんが、その前後を含めて楽団創設50周年記念コンサートやツアーを指揮し、楽団員からも慕われて退任後は名誉指揮者の称号を贈られ、定期的に客演を続けました。オーケストラ曲の王道というべきレパートリーを揃えたこのセットは彼のファンにとって大きな宝物となることでしょう。ブックレットにはドイツ・レコード批評家賞の審査員を務めるクリストフ・ヴラーツ氏によるエピソードをまじえた解説が掲載されています(英語とドイツ語)。 レーベルからの情報によれば、CD1、CD4、CD7は初CD化とのこと。 -
〈ブルックナー・フロム・アーカイヴ第3巻〉
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 第3番 ニ短調
交響曲 第4番 変ホ長調「ロマンティック」 [ハンス・シュミット=イッセルシュテット、フォルクマール・アンドレーエ(指揮)]発売日:2024年08月02日
CD 2枚組価格:3,675円(税込、送料無料)
アメリカ・ブルックナー協会の事務局長で、放送業界でも活躍したジョン・F・バーキーの11,000本にも上るエアチェック・テープから、選りすぐりの音源で交響曲全集をCD化するブルックナー・フロム・アーカイヴ第3巻、いずれも初出音源です。このシリーズは同協会の総裁でブルックナー研究者のベンジャミン・コーストヴェットが監修と解説執筆を担当していることも注目です。 第3番はハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮の北ドイツ放送響。彼はブルックナーの正規録音がありませんが、1950年にフリッツ・エーザーが校訂した第3番第2稿の楽譜が出版された際にいち早くその初演を行っています。マタチッチやスイトナーなど第3番第2稿を好む指揮者が使っていたエーザー版ですが、1980年に第2稿のノーヴァク版が出版されると、主流の座を譲りました。しかし両版の大きな違いは第3楽章のコーダの有無(エーザー版には無い)だけということもあり、その後もバレンボイムやドホナーニが使っています。 当音源には、第3番の演奏史において重要な役割を果たしたエーザー版と、そのバイオニアとしてのシュミット=イッセルシュテットへのトリビュートが込められているのでしょう。TahraからCD化されたこのコンビの第4番(1966年)と第7番(1968年)に通じる、あわてず騒がず細部を緻密に積み重ねて行く音楽作りが聞かれます。 フォルクマール・アンドレーエは1953年にウィーン響を指揮して録音した史上初のブルックナー交響曲全集で知られていますが、1906年から1949年の長きにわたり首席指揮者を務めたチューリヒ・トーンハレ管とは第4番と第9番のスイス初演や交響曲全曲演奏会を行い、生涯でのブルックナー作品指揮回数は250回以上と伝えられています。ここではミュンヘン・フィルを指揮して楽想の変化に応じた細かなテンポとダイナミクスの操作によって作品の持つ威容と深い情感を過不足なく描き出しています。
収録作曲家:
-
ディートリッヒ (1829-1908):
交響曲 ニ短調
ヴァイオリン協奏曲
序曲 ハ長調 [クライディ・サハチ(ヴァイオリン)、クリストフ・ケーニヒ(指揮)、ソリスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルク]DIETRICH, A.: Symphony in D Minor / Violin Concerto / Overture in C Major (Sahatçi, Solistes Européens, Luxembourg, C. König)
発売日:2024年07月26日
 NMLアルバム番号:8.574507
NMLアルバム番号:8.574507CD価格:1,900円(税込)
「FAEソナタの、もう一人の作曲家」ディートリッヒの神髄を聴く!アルベルト・ディートリッヒ、ドイツのロマン派時代の作曲家で指揮者。ブラームスやシューマンのファンならば、FAEのソナタの共作者として見覚えのある名前でしょう。シューマンに作曲を師事していたディートリッヒは、そこでブラームスと出会って親交を結び、後に指揮者としてブラームス作品のよき理解者となりました。彼の回想録『ブラームスの思い出』は、その時代の息吹を生き生きと伝える第一級の資料とされています。 ここでは彼の大規模な管弦楽作品を収録。メンデルスゾーンのように屈託を感じさせない抒情的ロマン派といった趣の楽想に、シューマンやブラームスに通じる語法や響きをまとわせており、ドイツ・ロマン派好きの人ならばきっと楽しめる仕上がりです。欧州の腕利き演奏家を集めたソリスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルクが力強いサウンドを響かせています。 中でもヨアヒムを念頭において書かれたヴァイオリン協奏曲は高度な技巧の見せ場の多い華麗な作品で、クライディ・サハチが献身的な演奏を聴かせます。
収録作曲家:
-
ニールセン(1865-1931):
交響曲全集[4枚組 BOX]
デンマーク王立管弦楽団575周年記念 [デンマーク王立管弦楽団、指揮:サイモン・ラトル、レナード・バーンスタイン、パーヴォ・ベルグルンド 他]発売日:2024年07月26日
CD 4枚組価格:9,975円(税込、送料無料)
初出多数! 「ニールセンのオーケストラ」による交響曲全集2023年に創設575周年を迎えたデンマーク王立管弦楽団(RDO)ならではの記念企画、ニールセンの交響曲全集です。 RDOは1448年にデンマーク王クリスチャン1世が臨席する場面で演奏するためのトランペット・バンドとして発足しました。その後の拡充や改編を経て今日に至りますが、驚くことに初代メンバーから名簿が残っており、通し番号が振られていて、その中にはダウランド(140番)やシュッツ(259番)の名前も見られます。 デンマークを代表する作曲家ニールセンは1889年から1905年までヴァイオリン奏者(647番)として在籍し、その後も指揮者として度々登場。その主要作品の数々をここで初演したため、楽団には「ニールセンのオーケストラ」としての特別な自負が今もあると言います。 このボックスでは、バーンスタインの第3番はCBS(現ソニークラシカル)、ベルグルンドの第6番はRCA(同)、シェンヴァントの《仮面舞踏会》序曲はDACAPOからのライセンスですが、他はすべてアーカイヴから厳選した音源で、初CD化となります。 (曲目・内容欄に続く)
収録作曲家:
-
バワーズ(1989-):
若き日の自分へ
シェーンベルク(1874-1951):
室内交響曲 第1番 [チャールズ・ヤン(ヴァイオリン)、カルロス・イスカライ(指揮)、アメリカン・ユース・シンフォニー]発売日:2024年07月26日
CD価格:2,175円(税込)
2011年にセロニアス・モンク国際ジャズ・ピアノ賞を受賞し、アカデミー賞の短編ドキュメンタリー部門を受賞したピアニスト・作曲家クリス・バワーズの「For A Younger Self=若き日の自分へ」。コロナ禍のパンデミックの中で書き上げられたこの作品は、映画音楽作曲家として名を上げた彼の初の管弦楽作品であり、若者が自身の問題を克服し、成長していくという物語をヴァイオリン協奏曲の形式で描こうとしています。 ヴァイオリン独奏は、グラミー賞受賞バイオリニストのチャールズ・ヤンが担当。併録のシェーンベルクは編成を拡大した、いわゆる「フル・オーケストラ」版と呼ばれるもの。両曲ともカルロス・イスカライが指揮するアメリカン・ユース・シンフォニーが見事にバックを務めています。
収録作曲家:
-
ブルックナー(1824-1896):
オルガン編曲による交響曲全集 [ハンスイェルク・アルブレヒト(オルガン)]発売日:2024年07月19日
CD 13枚組価格:9,675円(税込、送料無料)
ブルックナー生誕200周年企画「オルガン編曲による交響曲全集」ついに完結!オルガニストでミュンヘン・バッハ管弦楽団の指揮者でもあるハンスイェルク・アルブレヒトの壮大なプロジェクトを集成。交響曲ヘ短調を含むCD13は当ボックスのみの収録となります。リンツのザンクト・フローリアン修道院の「ブルックナー・オルガン」をはじめ、チューリッヒ、ライプツィヒ、ウィーン、ロンドンなど作曲者所縁の地のオルガンを用いることで、各地のオルガンの音色の特徴を楽しめるだけではなく、ブルックナー作品のオルガン的な響きも存分に堪能できます。 番号順に並べられたアルバムには、交響曲の他、第二次世界大戦直後にブルックナーの弟子の遺品から発見された「交響的前奏曲」や「詩篇150篇」、3本のトロンボーンのための「エクアーレ」など興味深い作品のオルガン版も収録されています。 更に、現役作曲家がぞれぞれの交響曲から受けたインスピレーションをもとに作曲した各曲への「フェンスター(窓)」を収録(第5番へのフェンスターは配信のみ)。伝統を現代につなぐ企画となっています。
-
バツェヴィチウス(1905-1970):
〈管弦楽作品集 第2集〉
交響曲 第3番
ピアノ協奏曲 第1番&第2番 [ガブリエリウス・アレクナ(ピアノ)、クリストファー・リンドン=ジー(指揮)、リトアニア国立交響楽団]BACEVIČIUS, V.: Orchestral Works, Vol. 2 - Piano Concertos Nos. 1 and 2 / Symphony No. 3 (Alekna, Lithuanian National Symphony, Lyndon-Gee)
発売日:2024年07月12日
 NMLアルバム番号:8.574414
NMLアルバム番号:8.574414CD価格:1,900円(税込)
グラジナ・バツェヴィチの兄、ヴィータウタス・バツェヴィチウスの管弦楽曲集第2弾バチェヴィチウスは、もともとピアニストとして名声を博し、数多くの演奏会に出演していましたが、1939年に南アメリカで演奏旅行を行っている時に第二次世界大戦が勃発。その翌年、祖国リトアニアがソビエト連邦に併合されたため、アメリカ合衆国へ渡りそこに留まりました。 このアルバムに収録されている交響曲第3番は、アメリカに到着して間もなく作曲された作品。新天地に対する楽観的な希望が、牽引力ある力強い曲調で描かれており、曲の最後はアメリカ国歌「星条旗」で高らかに締めくくられます。 2つのピアノ協奏曲は大戦前のパリ留学時の作品。第1番ではリトアニアの民俗音楽の旋律が用いられており、彼の故郷への郷愁が窺えます。第2番の協奏曲にも民謡の要素が使われており、その曲の歌詞がバツェヴィチウスによって総譜内に書き込まれています。どちらの曲も装飾的なピアノ・パートを持ち、オーケストラの伴奏がこれを彩ります。 リトアニアのピアニスト、ガブリエリウス・アレクナはTOCCATAレーベルからバツェヴィチウスのピアノ曲をこれまでに3枚リリースした他、このシリース第1集の協奏曲でもピアノを担当しています。
収録作曲家:
-
パリの祭典
ミヨー(1892-1974):屋根の上の牛
ラヴェル(1875-1937):ツィガーヌ
ビゼー(1838-1875):交響曲
シャブリエ(1841-1894): 気まぐれなブーレ [アレクサンドラ・スム、バンジャマン・レヴィ、ペレアス室内管弦楽団]Orchestral Music (French) - BIZET, G. / CHABRIER, E. / MILHAUD, D. / RAVEL, M. (Paris est une fête) (Soumm, Orchestre de Chambre Pelleas, Lévy)
発売日:2024年07月05日
 NMLアルバム番号:FUG813
NMLアルバム番号:FUG813CD価格:2,775円(税込)
アレクサンドラ・スムとバンジャマン・レヴィがパリの賑わいを描く、
楽しくも美しいアルバム2024年パリの祝祭をテーマに、第二帝政から1920年代の狂騒の時代まで約70年間の作品を集めたアルバム。ブラジルの大衆音楽に大きな影響を受けたミヨーの「屋根の上の牛」で賑やかに始まり、最晩年のシャブリエが書き上げたピアノ曲の管弦楽版「気まぐれなブーレ」、新しいラヴェル・エディションでの初録音となる「ツィガーヌ」、ビゼーが唯一残した交響曲が収められています。 ミヨーとラヴェルではロシア出身で現在はパリを拠点に活躍するヴァイオリニスト、アレクサンドラ・スムがソリストを務め、高い技術と表現力で聴く者に強く訴えかける素晴らしい演奏を披露。バンジャマン・レヴィ率いるペレアス室内管弦団も世界観をストレートに歌い上げ、喧騒、郷愁、揺らぎに満ちた光の街の肖像画を描きます。 -
ペトリディス(1892-1977):
オラトリオ「聖パウロ」
交響曲 第1番他 [バイロン・フィデツィス(指揮)/ブルガリア国立放送合唱団/ブルガリア国立放送交響楽団 他]PETRIDIS, P.: Saint Paul [Oratorio] (D. Tiliakos, A. Simos, Stamboglis, Bulgarian National Radio Chorus and Symphony, Fidetzis)
発売日:2024年06月28日
 NMLアルバム番号:8.574356-57
NMLアルバム番号:8.574356-57CD 2枚組価格:2,900円(税込)
トルコのカッパドキア近郊出身の作曲家ペトロス・ペトリディス。イスタンブールの高校を卒業し、1911年からパリで法律を学ぶも、翌年からバルカン戦争に従軍。帰還後は音楽家を目指し、ほぼ独学で作曲技法を習得しました。1913年にはギリシャに帰化、その後はパリとアテネを行き来しながら音楽評論家としても活動。「皇帝コンスタンティノス・パレオロゴスのためのレクイエム」など、中世ビザンチン聖歌を用い、複雑なポリフォニーを駆使した作品が高く評価されています。 当盤に収録されたオラトリオ「聖パウロ」も同様で、聖書の使徒行伝中の聖パウロに関するエピソードが朗読、独唱、合唱が歌う14のコラールを交えドラマティックに綴られます。 アルバムには1933年にディミトリ・ミトロプーロスが初演を行った「交響曲第1番」と、ペトリティスにとって初の大規模なオーケストラ作品となった「クレフティコ舞曲集」も収録されています。
収録作曲家:
-
ディッタースドルフ(1739-1799):
オウィディウスの『変身物語』による交響曲集 [ケース・スカリョーネ(指揮)/ハイルブロン・ヴュルテンベルク室内管弦楽団]DITTERSDORF, C.D. von: Symphonies Nos. 1-6 (Symphonies after Ovid's Metamorphoses) (Württemberg Chamber Orchestra of Heilbronn, Scaglione)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:555429-2
NMLアルバム番号:555429-2CD 2枚組価格:4,800円(税込、送料無料)
LP時代から人気のあったディッタースドルフの「変身物語」に基づく交響曲集に新録音が登場。 1781年、ディッタースドルフは古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』に基づく交響曲シリーズの作曲を計画します。この物語は古代神話の登場人物たちが動物や植物、鉱物、果ては神にまで変身していくエピソードを集めた叙事詩で、後世数多くの演劇作品やオペラなどの題材になっています。 ディッタースドルフは15曲の交響曲を5曲ずつ3つのセットにし、そのセットのために造られた彫刻を合わせて出版することを計画。これは18世紀後半における「最も野心的なプロジェクト」の一つとして評判になりましたが途中で頓挫。完成したのはここに収められた6曲の交響曲だけでした。 ハイドンを思わせる端正な音楽に現れる「変身」の場面は今も魅力的に響きます。
収録作曲家:
-
バッハへの階段
60年代と70年代のシンフォニック・ロックと
バッハ作品をオルガンで [スヴェン=イングヴァル・ミッケルセン(オルガン)]STAIRWAY TO BACH - Rock Classics with a Hint of Bach Mikkelsen)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:8.226920
NMLアルバム番号:8.226920CD価格:2,400円(税込)
アルバムタイトルのStairway to Bachは言うまでもなくレッド・ツェッペリンの名曲「天国への階段 Stairway to Heaven」をもじったもの。ここにアルバムのコンセプトが凝縮されています。 60年代から70年代のロック・ミュージック・シーンではシンセサイザーやメロトロン、オルガンやオーケストラを導入して、分厚いシンフォニックなサウンドを構築したり、バロック風のフレーズを織り込んだりした曲が多数制作されました。バッハの音楽を自らのルーツの一つとして演奏・引用したELPのキース・エマーソンのような存在も影響を与えたと思われます。 このアルバムは世界的なヒットを記録したロックの名曲をアレンジしてオルガンで弾きまくり、バッハと組み合わせたもの。こうして聴くと、これら往年のロックの名作がクラシックの仲間入りをする日も遠くないと思われます。
-
マーラー(1860-1911):
交響曲 第9番 ニ長調 (ピリオド楽器による) [フィリップ・フォン・シュタイネッカー、マーラー・アカデミー管弦楽団]MAHLER, G.: Symphony No. 9 (Mahler Academy Orchestra, Steinaecker)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:ALPHA1057
NMLアルバム番号:ALPHA1057CD価格:2,775円(税込)
作品の印象を覆す澄んだ美しさ!
作曲当時の楽器と演奏習慣による、マーラー交響曲第9番第一次大戦終結までオーストリア領だったイタリアの南チロル州で、クラウディオ・アバドによって創設された「マーラー・アカデミー・ボルツァーノ=ボ―ゼン」の活動の一環として、世界各国から集まった若い音楽家たちとヨーロッパの有名オーケストラの団員が共に演奏する機会を作るマーラー・アカデミー管弦楽団。そのOriginalklang(ドイツ語で「本来の響き」)プロジェクトとして、マーラーの交響曲第9番が初演された1912年にウィーンで使われていた楽器を世界中から集め(後世の再現楽器含む)、その演奏習慣を研究・習得して行われた録音が登場します。 この作品が生まれた地であるトーブラッハで行われた今回の録音は、ピリオド楽器によるおそらく初めてのもの。管楽器はヴィブラートをほぼかけず、ガット弦を張った弦楽器のヴィブラートも控えめながらポルタメントを多くかけ、テンポは比較的速めという方向で作られる音楽は、この作品に付きまとう死や情念といったイメージからはほど遠い、清涼感に溢れたものとなっています。特に第4楽章の澄み渡るような美しさは特筆もの。マーラー録音史に残る一枚と言えそうです。 指揮者のフィリップ・フォン・シュタイネッカーは、マーラー室内管やオーケストラ・レヴォリューショネル・エ・ロマンティークの首席チェロ奏者を務めた後、モダン楽器とピリオド楽器のオーケストラ双方で活躍する指揮者。当CDの巻末には後援者として内田光子氏の名前もクレジットされています。収録作曲家:
-
ベートーヴェン(1770-1827):
交響曲 第3・5・7・9番 他(マーラーによるオーケストレーション版) [マイケル・フランシス(指揮)/ラインラント=プファルツ州立フィルハーモニー管弦楽団 他]BEETHOVEN, L. van: Mahler Re-Orchestrations - Symphonies Nos. 3, 5, 7, 9 / String Quartet No. 11 (Rheinland-Pfalz State Philharmonic, M. Francis)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:C5484
NMLアルバム番号:C5484CD 3枚組価格:3,525円(税込、送料無料)
マーラー版のベートーヴェンを網羅した画期的アルバムが登場!
引き締まった演奏にも注目ウィーン・フィルの指揮者などを歴任したマーラーが、先輩作曲家たちの作品の演奏にあたりオーケストレーションに手を入れていたことは広く知られており、それぞれに録音も出ていますが、そのうちベートーヴェン作品をすべて演奏・収録したアルバムはありそうで無かった企画の一つ。すぐれた作曲家の眼を持つ練達の指揮者マーラーの思考を系統的に追うのに好適なセットです。 マーラー自身の交響曲は曲も編成も大規模なものですが、彼が過去の作品に行った変更は少し方向が違います。場所により弦楽器に管楽器を重ねる、弦の細かなフレーズを強調するために管のパートを省く、管の動きにオクターヴを付与する、といった楽器間のバランスを整えて効果的に響かせるためのものが多く、また細かな演奏指示も書き込まれており、指揮者マーラーがどのパートを重視したか分かるのが興味深いところです。また金管楽器の改良や用法の変遷に伴って、かつては音が出なかった旋律が足されたり、高すぎる音を下げるといった処理も行われています。 しかしながら、ホルンは基本的に倍管となっており、「第九」はティンパニ2人を擁するマーラーらしい巨大編成へと変貌していることも事実。「英雄」葬送行進曲フーガのクライマックスや第4楽章コーダ前にティンパニが加筆されていたり、「第九」第1楽章で低弦にトロンボーンを重ねたり第4楽章でコントラファゴットのサポートにチューバが動員されたりといったところは、なかなか衝撃的でもあります。 英国出身の指揮者マイケル・フランシスが2019年から首席指揮者を務める手兵オケを指揮してこれらを次々と浮き彫りにしてゆきます。 (曲目・内容欄に続く)収録作曲家:
-
モーツァルト(1756-1791):
アダージョとフーガ ハ短調 K.546
協奏交響曲 K.364
交響曲 第27番 K.199 [マッシモ・ベッリ(指揮)/新フェルッチョ・ブゾーニ管弦楽団]MOZART, W.A.: Adagio and Fugue, K. 546 / Sinfonia concertante, K. 364 / Symphony No. 27 (Milani, Ranieri, Ferruccio Busoni Chamber Orchestra, Belli)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:CDS8012
NMLアルバム番号:CDS8012CD価格:2,175円(税込)
1965年にトリエステのヴェルディ歌劇場のメンバーによって創設された新フェルッチョ・ブゾーニ管弦楽団。楽団名はブゾーニの母親がトリエステ出身であることにちなんでいます。 このアルバムでは、バロック音楽を思わせる厳粛な雰囲気の「アダージョとフーガ」、RAI国立交響楽団の第1奏者二人を迎えたフランス風の協奏交響曲、急緩急の3楽章構成でフガートによるプレストの終楽章で締めくくられるユニークな交響曲第27番という、性格の異なるモーツァルトの3作品を演奏しています。
収録作曲家:
-
ピアノ・デュオによるベートーヴェン
〈交響曲全集 第5集〉
交響曲 第4番&第8番他 [テッサ・アイス(ピアノ)/ベン・スクーマン(ピアノ)]BEETHOVEN, L. van: Symphonies, Vol. 5 - Nos. 4 and 8 / MOZART, W.A.: The Magic Flute Overture (Uys, Schoeman)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:SOMMCD0687
NMLアルバム番号:SOMMCD0687CD価格:2,250円(税込)
フランツ・クサヴァー・シャルヴェンカの編曲によるベートーヴェンの交響曲全集第5集。当盤には画期的な大作第3番と意欲的な第5番の間に書かれ、均整のとれた構成を特徴とする第4番、小規模ながらも和声やリズムに独創性が認められる第8番を中心に収録。ベートーヴェン作品の中でも比較的軽やかかつ重要な2曲をテッサ・アイスとベン・スクーマンが息のあったデュオで聴かせます。 編曲をしたシャルヴェンカはポーランド系ドイツの作曲家。彼の兄ルートヴィヒ・フィリップ・シャルヴェンカも作曲家として知られています。兄弟はベルリンでツェルニーの弟子であったテオドール・クラクにピアノを師事しており、この編曲にもベートーヴェン直系の弟子(ツェルニーはベートーヴェンに直接師事していた)ならではの作品に対する敬愛が感じられる見事な仕上がりを見せています。 最後に置かれたのはブゾーニの編曲によるモーツァルトの《魔笛》序曲。シャルヴェンカよりも後に生まれたブゾーニですが、同じ年の1924年に亡くなったため2人とも2024年が没後100年にあたります。 演奏しているのは南アフリカのケープタウン出身のピアニスト、テッサ・アイスと、同じく南アフリカ出身のペン・スクーマンによるピアノ・デュオ。2010年からロンドンを中心に各地で活躍しています。2015年からシャルヴェンカ編曲による交響曲全9曲の演奏を始め、2020年にはベートーヴェン生誕250周年記念として全曲の録音を開始、残りは第九を残すのみとなりました。
-
インバル/シュトゥットガルト放送交響楽団
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 第7番&第8番 [エリアフ・インバル(指揮) シュトゥットガルト放送交響楽団]BRUCKNER, A.: Symphonies Nos. 7 and 8 (Stuttgart Radio Symphony, Inbal)
発売日:2024年06月21日
 NMLアルバム番号:SWR19152CD
NMLアルバム番号:SWR19152CDCD 2枚組価格:3,675円(税込、送料無料)
インバルとシュトゥットガルト放送響のブルックナー録音が登場。後期の名作2曲、2010年代のライヴです。 フランクフルト放送響との第3、4、8番の初稿の録音(Teldec/現Warner)により大きな議論を巻き起こし、これら初校への認識を広める上で決定的な役割を果たしたエリアフ・インバル。卓越した細部の読みと指揮能力も相まって、現代に至る精緻で理知的なブルックナー解釈をリードしてきました。彼が定期的に指揮していたシュトゥットガルト放送響とのアーカイヴから第7番と第8番が初めてリリースされます。 インバルには両曲ともフランクフルト放送響と都響を指揮した2種の録音がありますが、当盤はその中で最新の音源となります。解釈はTeldec盤の時点で練り上げられていたようで、第8番の演奏時間は3種とも75分台で楽章毎の差もごく少ないという完成度の高さに驚かされます。一方、第7番では2012年の都響盤(Exton)の58:34に対し1年半後の当盤では62:01となり、全楽章において少しずつ演奏時間が延びているのが興味深いところ。オケも透明度の高いサウンドで精緻な演奏を繰り広げており、シューリヒト、チェリビダッケ、ノリントンという個性的なブルックナー指揮者との録音を残してきたシュトゥットガルト放送響のディスコグラフィに貴重な追加となります。 楽譜はインバルらしくノーヴァク版を使用(第7番第2楽章はシンバルあり)、拍手はカットされています。
収録作曲家:
-
ブラウワー(1940-):
〈管弦楽作品集〉
交響曲 第1番「湖の声」
狂詩曲、管弦楽のための協奏曲
プルート他 [マリン・オルソップ(指揮)/ウィーン放送交響楽団]BROUWER, M.: Orchestral Music - Art of Sailing at Dawn (The) / Rhapsody / Symphony No. 1 / Pluto (Rhapsodies) (ORF Vienna Radio Symphony, Alsop)
発売日:2024年06月14日
 NMLアルバム番号:8.559933
NMLアルバム番号:8.559933CD価格:1,900円(税込)
ニューヨーク・タイムズ紙で「独特の魅惑的なハーモニーの世界に棲んでいる」と称賛されたアメリカの作曲家マーガレット・ブラウワー。1996年から2008年までクリーヴランド音楽院作曲科の主任教授を務め、数々の名誉ある賞を受賞、オーケストラや演奏家からも数多くの委嘱を受けています。 このアルバムには5つの作品を収録。交響曲第1番には、彼女が幼い頃に過ごしたオランダ系アメリカ人のコミュニティで耳にしていたオランダの賛美歌が繰り返し現れます。「狂詩曲、管弦楽のための協奏曲」では様々な楽器が色彩豊かに用いられており、まばゆいばかりの響きです。 1996年、ホルストの「惑星」の続編として作曲された「プルート=冥王星」は冥府を司る神をモティーフに破壊と再生が描かれた作品。「海王星」のラストを受けて初演版では女声合唱が入りますが、この作曲家自身による編曲では、声の代わりにフルートとオーボエが太陽の温かさを描き出します。 他には、早朝の静けさの中に咲く花々を描いた「Path at Sunrise, Masses of Flowers」、夜明けの航海の様子を描いた「The Art of Sailing at Dawn」を収録。マリン・オルソップがウィーン放送響とともに常に自然に寄り添うブラウワー作品の抒情的な魅力を丁寧な仕事で隅々まで伝えます。
収録作曲家:
-
〈ブルックナー・フロム・アーカイヴ 第2巻〉
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 ニ短調
交響曲 第2番 ニ短調
ミサ曲 第2番 ホ短調 [カール・フォルスター (指揮) /ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、聖ヘトヴィヒ大聖堂合唱団/エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指揮) 他]発売日:2024年06月14日
CD 2枚組価格:3,675円(税込、送料無料)
アメリカ・ブルックナー協会の事務局長で、放送業界でも活躍したジョン・F・バーキーの11,000本にも上るエアチェック・テープから、選りすぐりの音源で交響曲全集をCD化するブルックナー・フロム・アーカイヴ第2巻。このシリーズは同協会の総裁でブルックナー研究者のベンジャミン・コーストヴェットが監修と解説執筆を担当していることも注目で、当巻には1868年から73年の間に書かれた2曲の交響曲に加えてミサ曲第2番を収めています。 ニ短調交響曲の演奏はエドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮のコンセルトヘボウ管。このコンビが第7番(1953年)、第8番(55年)、第9番(56年)と集中してブルックナーに取り組んでいた時期の演奏だけに出来栄えに期待されます。楽譜は1927年にウニヴェルザール出版社から出たブルックナー交響曲全集所収のヨーゼフ・ヴェナンティウス・ヴェス(1863-1943)校訂版を使用。コーストヴェットによれば「ベイヌムらしい、キビキビとした演奏」とのこと。 第2番はオイゲン・ヨッフムの弟ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフムのケルン放送響。コーストヴェットはこの演奏について「とても優れた演奏。深い情感、輝かしい想像力、充実した響きを持つ作品として第2番を聞かせてくれる」と評しています。 冒頭に収められたミサ曲第2番の指揮者カール・フォルスターは哲学や神学を学んだ人で、1934年から63年までベルリンの聖ヘトヴィヒ大聖堂の楽長を務めました。戦時中は演奏を禁じられるなどの苦労をしましたが、戦後はいち早く合唱団を復活させ、1961年には招かれてローマ教皇のために演奏しました。CDにはソリストの名前がありませんが、初出LPによればアグネス・ギーベル、マルガ・ヘフゲン、ヨゼフ・トラクセル、ゴットロープ・フリックが歌っています。
収録作曲家:
-
エイドリアン・ボールト指揮
ベートーヴェン(1770-1827):
交響曲 第3番 「英雄」
シューベルト(1797-1828):
交響曲 第9番 「ザ・グレート」
ブラームス(1833-1897):
ハイドンの主題による変奏曲他 [エイドリアン・ボールト、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、BBC交響楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦管弦楽団 ほか]BEETHOVEN, L. van: Symphony No. 3 / SCHUBERT, F.: Symphony No. 9 / BRAHMS, J.: Variations on a Theme by Haydn (Boult)
発売日:2024年06月14日
 NMLアルバム番号:ICAC5179
NMLアルバム番号:ICAC5179CD 2枚組価格:3,525円(税込、送料無料)
ボールト、名演揃いの初出ライヴ音源集!BBCのアーカイヴから、エイドリアン・ボールトのライヴ音源が登場。いずれもこれまで商業発売の無いもので、Re:Soundのポール・ベイリーが丁寧なリマスターを行い、オリジナル・マスターテープから素晴らしい音を引き出しています。中でもメインと捉えられる3曲、ライヴ音源初登場の「英雄」、名演として知られる1972年のスタジオ録音を凌ぐライヴならではの「ザ・グレート」、そして「ハイドン変奏曲」は、演奏がたいへん立派なうえに音質も良く、これらだけでもお宝ものの発掘と言えそうです。 さらに「献堂式」はボールトにとって初登場レパートリー、「オイリアンテ」はステレオ録音初登場と小品も充実。ボールトといえばホルストやエルガー、ヴォーン・ウィリアムズなどの英国音楽の解釈で知られますが、1912-13年にはライプツィヒ音楽院でニキシュに指揮、レーガーに作曲の教えを受けており、ワインガルトナー、フルトヴェングラー、ワルターといったドイツ系の指揮者たちに心酔していたこともあって、ドイツ音楽にもまた多くの名演を残しています。 これはそんな巨匠の一面を新たな音源で再確認することの出来るという意味でも、たいへん貴重な2枚組です。
-
ショスタコーヴィチ(1906-1975):
交響曲 第15番(室内楽版)
エスケシュ(1965-):
Vitrail [トリオ・メシアン、トリオ・クセナキス]SHOSTAKOVICH, D.: Symphony No. 15 (arr. V. Derewianko) / ESCAICH, T.: Vitrail (Trio Messiaen, Trio Xenakis)
発売日:2024年06月14日
 NMLアルバム番号:LBM063
NMLアルバム番号:LBM063CD価格:2,775円(税込)
-
〈次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.9〉
モーツァルト(1756-1791):
協奏交響曲
ホルン協奏曲 第2番
ロンド K.382&386 [ユーハン・ダーレネ、アイヴィンド・リングスタッド、アレクサンドル・ザネッタ、アリエル・ラニ、ハワード・グリフィス、ザルツブルク・モーツァルテウム管]MOZART, W.A.: Sinfonia concertante, K. 364 / Rondos, K. 382 and 386 (Next Generation Mozart Soloists, Vol. 9) (Dalene, Ringstad, Zanetta, Griffiths)
発売日:2024年06月07日
 NMLアルバム番号:ALPHA1051
NMLアルバム番号:ALPHA1051CD価格:2,775円(税込)
若手ソリストによるモーツァルトのシリーズに、
俊英ユーハン・ダーレネ登場!2000年ノルウェー生まれのユーハン・ダーレネは、スウェーデンBISより2019年からこれまで4枚のアルバムをリリース、2度の来日公演を通じて日本の聴衆にも大きなインパクトを与えている俊英。2012年のユーロビジョン・ヤング・ミュージシャンズの覇者であるアイヴィンド・リングスタッドと共に、切れ味のよい演奏を聴かせています。 ホルンのアレクサンドル・ザネッタは1990年生まれのフランス出身、ベルリンでマリー=ルイーズ・ノイネッカーに師事するなど研鑽を積んだ後、バーゼル・スコラ・カントルムでナチュラル・ホルンを習得しました。ここでも細やかなトリルや装飾音など見事な技巧とセンスを聴かせ、作曲家が本来想定したホルンの音色で作品を楽しませてくれます。 1997年イスラエル生まれのアリエル・ラニは2023年、ルドルフ・ブッフビンダーが選出する若いアーティストのためのピアノ賞プリ・セルダンに選出された新鋭で、粒のそろった音色で安定した美しい演奏を聴かせます。収録作曲家:
-
ウォーカー(1922-2018):
弦楽のための抒情詩
ライラック/管弦楽のための民謡集
ドーソン(1899-1990):
ニグロ・フォーク・シンフォニー [ニコール・カベル(ソプラノ)/アッシャー・フィッシュ(指揮)/ロデリック・コックス(指揮)/シアトル交響楽団]WALKER, G.: Lyric for Strings / Folksongs for Orchestra / Lilacs / DAWSON, W.L.: Negro Folk Symphony (N. Cabell, Seattle Symphony, R. Cox, A. Fisch)
発売日:2024年06月07日
 NMLアルバム番号:SSM1027
NMLアルバム番号:SSM1027CD-R価格:2,175円(税込)
20世紀に活躍した2人のアフリカ系アメリカ人作曲家の作品集。 ジョージ・ウォーカーはカーティス音楽院で作曲とピアノを学び、1945年に同音楽院初の黒人卒業生となりました。このアルバムに収録された「ライラック」で1996年にピューリッツァー賞を受賞した他、ジャズや民謡、黒人霊歌のイディオムを用いた数多くの管弦楽曲や室内楽曲を書きました。初期の作品「弦楽のための抒情詩」と黒人霊歌を印象的に用いた「管弦楽のための民謡」も収録。 ウォーカーの一つ上の世代にあたるウィリアム・リーヴァイ・ドーソンの「ニグロ・フォーク・シンフォニー」も黒人霊歌の要素を用いた作品。レオポルド・ストコフスキーが指揮するフィラデルフィア管弦楽団によって初演され大好評を博しました。 オペラとコンサート両面で幅広く活躍するアッシャー・フィッシュがウォーカー作品を、2018年、サー・ゲオルグ・ショルティ指揮者賞を受賞した俊英指揮者ロデリック・コックスがドーソンの作品を指揮。どちらもオーケストラの機動性を生かした豊かな表現を披露しています。 ※ CD-Rメディアでの発売です。
-
テイラー(1964-):
〈管弦楽作品集 第2集〉
交響曲 第6番
オーボエ協奏曲
クラリネット協奏曲
ヴァイオリン小協奏曲 [ジェイムズ・ターンブル(オーボエ)/ポピー・ベドー(クラリネット)/ミラ・マルトン(ヴァイオリン)/マシュー・テイラー(指揮)/BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団]TAYLOR, M.: Orchestral Music, Vol. 2 (Beddoe, Turnbull, Marton, BBC National Orchestra of Wales, M. Taylor)
発売日:2024年06月07日
 NMLアルバム番号:TOCC0708
NMLアルバム番号:TOCC0708CD価格:2,175円(税込)
英国の作曲家マシュー・テイラー。彼の音楽は「現代に語りかける言葉と伝統的な形式を組み合わせた」もので、ベートーヴェンやハイドンから連なる古典派の伝統を踏まえ、そこにシベリウスやニールセンの影響を感じさせる現代的な装いの響きを描き出します。 このアルバムには2021年に生誕100年を迎えたマルコム・アーノルドの追悼として作曲された交響曲第6番の他、3つの協奏的作品を収録。オーボエ協奏曲は、2つのコールアングレと弦楽器が伴奏を務めるというユニークな編成で書かれ、クラリネット協奏曲の冒頭では、ブラームスの五重奏と似た旋律が聴こえてきます。 ジャズのリズムが用いられたヴァイオリン小協奏曲は、短いながらもまとまりのある曲。全ての作品はテイラー自身が指揮を行い、彼が信頼する奏者たちが独奏を務めています。
収録作曲家:
-
シマノフスキ(1882-1937):
交響曲 第3番「夜の歌」
おとぎ話の王女の歌他 [イヴォナ・ソボトカ(ソプラノ)/ジャンカルロ・ゲレーロ(指揮)/NFMヴロツワフ・フィルハーモニー管弦楽団]SZYMANOWSKI, K.: Concert Overture / Songs of a Fairy Princess / Symphony No. 3 (Sobotka, NFM Wrocław Philharmonic, Guerrero)
発売日:2024年05月31日
 NMLアルバム番号:CDAccordACD315
NMLアルバム番号:CDAccordACD315CD価格:3,675円(税込、送料無料)
文学作品からインスパイアされたシマノフスキの作品を収めた1枚。友人の詩人タデウシュ・ミチンスキの詩に共鳴して書かれた「演奏会用序曲」、 妹ゾフィー・シマノフスカの詩に曲をつけた「おとぎ話の王女の歌」、そしてペルシャの神秘主義の詩人ジャラール・ウッディーン・ルーミーの詩をミチンスキがポーランド語に翻訳したテキストを用いた「交響曲第3番」の3曲。 イヴォナ・ソボトカは2004年のエリザベート王妃国際音楽コンクールの優勝者。欧州の名門歌劇場やオーケストラに出演し、サイモン・ラトルの指揮でシマノフスキ作品を歌ったアルバムなど が高く評価されています。
収録作曲家:
-
ブルックナー(1824-1896):
交響曲 ニ短調 WAB 100(1869)
(2023年デイヴィッド・チャプマン校訂版) [レミ・バロー(指揮)/聖フローリアン・アルトモンテ管弦楽団]発売日:2024年05月31日
CD価格:2,550円(税込)
ブルックナー演奏の聖地ザンクト・フローリアンにおけるレミ・バローの交響曲全集より
交響曲ニ短調の分売登場リンツ郊外のザンクト・フローリアンにある聖フローリアン修道院は、かつてアントン・ブルックナーが聖歌隊で歌い、オルガニストを務め、今はその墓所となっている場所。ここでは、古くは朝比奈隆と大阪フィルの第7番、カラヤンやブーレーズとウィーン・フィルの第8番など巨匠たちによる記念碑的なブルックナー演奏が繰り広げられてきました。同地でブルックナーの没後100年を記念して1996年に創設されたのが、聖フローリアン・アルトモンテ管弦楽団とブルックナー週間(Bruckner-Tage)音楽祭です。このアルバムは昨年発売された交響曲全集BOXに初出音源として含まれていた交響曲ニ短調の分売です。 演奏にはアメリカの音楽学者ディヴィッド・N・チャップマンの2023年校訂版が用いられており、このシリーズ共通でテンポは遅めで、とりわけ第1楽章は18分という異例の長さ。これは録音場所の持つ長い残響の中で響きを濁らせないためで、チェリビダッケに私淑していたバローのこだわりが感じられます。収録作曲家:
-
コロメル(1966-):
シンフォニック・ジェネシス
交響的作品集 [セルジオ・アラポント(指揮)/スペイン放送交響楽団]COLOMER, J.J.: Symphonic Genesis / Escaping Insanity / Escenas pintorescas (Spanish Radio and Television Symphony, Alapont)
発売日:2024年05月31日
 NMLアルバム番号:IBS-22024
NMLアルバム番号:IBS-22024CD価格:2,475円(税込)
バレンシア生まれの作曲家コロメルの作品集。幼い頃から音楽に触れた彼は、16歳の時にトランペット奏者としてオーケストラに加わった後、ボストンで映画音楽を専門に学びました。 彼が名を上げたのは、1990年代からプラシド・ドミンゴのためにアルバム「クリスマス・イン・ウィーン」の楽曲などいくつかの作品のオーケストレーションを行ったことでしょう。その華麗な響きはドミンゴの歌声とともに多くの聴衆を魅了しました。 このアルバムでは一転、シリアスな作曲家としての顔を見せており、今を新たな時代の入り口ととらえつつ、人類の存続が外的環境と内的環境(精神や文化)の面で危険な状況にあることへの警鐘も鳴らしています。
収録作曲家:
-
フォス(1922-2009):
交響曲 第1番
ルネッサンス協奏曲
3つのアメリカの小品
オード [エイミー・ポーター(フルート)/ニッキ・チューイ(ヴァイオリン)/ジョアン・ファレッタ(指揮)/バッファロー・フィルハーモニー管弦楽団]FOSS, L.: Symphony No. 1 / Renaissance Concerto / 3 American Pieces / Ode (A. Porter, Nikki Chooi, Buffalo Philharmonic, Falletta)
発売日:2024年05月24日
 NMLアルバム番号:8.559938
NMLアルバム番号:8.559938CD価格:1,900円(税込)
ベルリン生まれのフォスは地元で初期の音楽教育を受け、1933年パリに留学。その後、1937年にアメリカにわたりフィラデルフィアのカーティス音楽学校に入学しフリッツ・ライナーから指揮法を学ぶとともに、イェール大学ではパウル・ヒンデミットから作曲を学んでいます。 彼の作品には様々な作曲スタイルが混在しますが、1940年代の3作品は新古典派的なスタイルで書かれており、自身の言葉である「未来に大きく足を踏み入れるには、過去に大きく足を踏み入れなければならない」を具現化したものといえるでしょう。とりわけ交響曲第1番は抒情的かつ田園的な雰囲気の中に、微妙にジャズの影響が感じられるユニークな作品です。 「オード」は第二次世界大戦中に失われた命への追悼曲。「3つのアメリカの小品」はヴァイオリンとピアノのために書かれましたが、後に管弦楽伴奏に編曲された作品。コープランド風の親しみやすい雰囲気に満ちています。1985年の「ルネッサンス協奏曲」はフォスが“世紀を超えた握手”と呼んだ曲。ラモーやモンテヴェルディ作品を借用しながらも、巧みな転調を採り入れたモダンな曲調が魅力的です。 表現力豊かなジョアン・ファレッタの指揮でお聴きください。
収録作曲家:
-
Inventio
J.S.バッハ(1685-1750):
インヴェンションとシンフォニア [菊地裕介(ピアノ)]発売日:2024年05月24日
CD国内盤価格:2,750円(税込)
菊地裕介が繰り広げるドラマティックなバッハのミクロコスモスバッハの「インヴェンションとシンフォニア」。ピアノ学習者にとって必須ともいえるこの曲集ですが、「インベンション=英語で発明、創造」の言葉のとおり、弾き手にとっても、聴き手にとっても常に新しい発見のある曲集です。 菊地裕介の演奏は、一つ一つの音が持つ意味とその存在を克明に捉えながら曲の構造を露わにしていき、ある種のドラマティックなバッハの偉大さも実感させるという素晴らしい仕上がりを見せています。
収録作曲家:
-
シルヴェストロフ(1937-):
ヴァイオリンと管弦楽のための交響曲「献呈」
後奏曲 - ピアノと管弦楽のための [ヤヌシュ・ヴァヴロフスキ(ヴァイオリン)/ユルギス・カルナヴィチウス(ピアノ)/クリストファー・リンドン=ジー(指揮)/リトアニア国立交響楽団]SILVESTROV, V.: Dedication / Postludium (Wawrowski, Karnavičius, Lithuanian National Symphony, Lyndon-Gee)
発売日:2024年05月10日
 NMLアルバム番号:8.574413
NMLアルバム番号:8.574413CD価格:1,900円(税込)
現在ベルリンで生活を送るキーウ出身の作曲家ヴァレンティン・シルヴェストロフ。活動の初期の頃は前衛的な作品を書いていたものの、1974年にソ連作曲家同盟から除名されてしまい公の場での活躍が難しくなりました。彼はこの頃から作風を変換、後期ロマン派を思わせる美しい響きを用いた懐古的な作品を書き始め、これらは現在までに多くの人に愛されています。 このアルバムに収録されているのは、彼の6番目の交響曲にあたる「献呈」と80年代の代表作の一つ「後奏曲」の2作。「献呈」はシルヴェストロフの親友でもあるヴァイオリニスト、ギドン・クレーメルのために作曲され、ミュンヘンでクレーメルによって初演されました。冒頭こそ不協和音に満ちていますが、曲の白眉はマーラーのアダージェットを思わせる最終楽章にあり、自身の演奏の録音を聴いたクレーメルが思わず「映画『ヴェニスに死す』の世界のようだ」と叫んだというほどに、安らぎと憧れに満ちた世界が広がります。 「後奏曲」も冒頭こそ十二音音楽を思わせる激しい曲想ですが、少しずつピアノの優しく懐かしい響きが曲を支配し、最後は静寂の中に音が消えていきます。どちらもシルヴェストロフらしい、調性や伝統的な旋法を用いながらも、ドラマティックさと抒情性が交錯する独自の作風で書かれています。 「献呈」でヴァイオリンを演奏するのはポーランドの名手ヤヌシュ・ヴァヴロフスキ。ポーランド現代作品の初演を数多く行うとともに、録音でも高く評価されており、このアルバムでも1685年製の銘器ストラディヴァリを駆使して、美しい音色でシルヴェストロフの音楽を歌い上げています。
収録作曲家:
-
ファランク(1804-1875):
交響曲 第3番
シューマン(1810-1856):
交響曲 第3番 「ライン」 [ダンカン・ウォード、南オランダ・フィルハーモニー管弦楽団]FARRENC, L.: Symphony No. 3 / SCHUMANN, R.: Symphony No. 3, "Rhenish" (Philzuid, Ward)
発売日:2024年05月03日
 NMLアルバム番号:FUG824
NMLアルバム番号:FUG824CD価格:2,775円(税込)