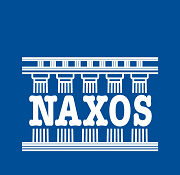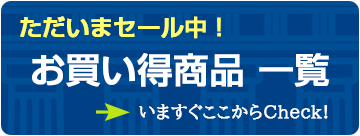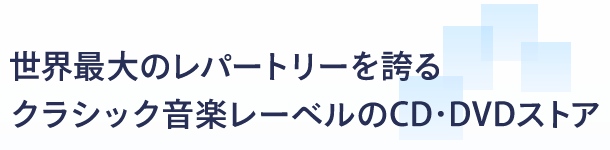マック(ジョヴァンニ・デ) Macque, Giovanni de
| 生没年 | 1548-1614 | 国 | フランス、イタリア |
|---|---|---|---|
| 辞書順 | 「マ」 | NML作曲家番号 | 68901 |
-
デ・マック(1548-1614):
5声のマドリガル 第6巻より(ヴァネツィア 1613)
+独奏オルガンのためのカプリッチョとカンツォーナ [マンフレート・コルデス (音楽監督)/ブレーメン・ヴェーザー=ルネサンス]MACQUE, G. de: Madrigals, Book 6 (Sesto libro de madrigali, 1613) / Organ Works (Bellotti, Bremen Weser-Renaissance, Cordes)
発売日:2018年12月21日
 NMLアルバム番号:777977-2
NMLアルバム番号:777977-2CD価格:2,640円(税込)
フランドル楽派の最後の世代に属する作曲家ジョヴァンニ・デ・マック。生涯のエピソードはほとんど知られていませんが、幸いにも数多くの作品が残されています。なかでも生前高く評価されたのがマドリガル集であり、初期の作品は保守的なローマスタイルで書かれていますが、晩年になるにしたがって半音階的な手法が目立つかなり実験的な作品も書かれています。 このアルバムに収録されているのは、彼が死去する1年前にヴェネツィアで出版された曲集から採られたマドリガルであり、多くのテキストはアルカディア神話によるもので、人間の悲しみや絶望、喜びなどの感情が豊かに表現されています。曲間には独奏オルガンのための小品が組み入れられており、アルバムとしてのまとまりも追求されています。
収録作曲家:
-
バロック・ハープの真髄 [西山まりえ]
発売日:2024年08月09日
CD国内盤価格:3,000円(税込、送料無料)
バロック時代のハープは声楽、器楽、宗教、世俗のあらゆる音楽を彩り、人々を強く魅了した楽器であった。17世紀初期には3列弦(白鍵、黒鍵、白鍵に相当)の楽器が考案され、ナポリの作曲家たちによるハープの黄金時代が到来する。王宮礼拝堂楽長マックの2人の高弟、トラバーチとマイヨーネは『ハープのための』作品を残しており、マイヨーネ自身は卓越したハープ奏者でもあった。ここに収録された6人の作曲家は全てナポリ出身あるいはナポリを縁とする者である。音楽史では触れられることは少ないが、彼らは新しい鍵盤音楽様式を先導し、ハープの可能性を大きく開いた点で注目すべき存在である。 鍵盤とハープ、この2つの楽器の間を自由に行き来する西山まりえもまた領域を持たない演奏家である。その類まれな音空間の感覚、透徹されたピアニッシモ、銀糸のように繊細な歌いとダイナミックな息遣いにより「バロック・ハープの真髄」が浮かび上がる。そこにはナポリの音楽家たちの精神が無限に広がっている。 『バロック・ハープとの出会い』に続く西山まりえ第2弾のバロック・ハープ・ソロアルバム。
-
フレスコバルディと
南イタリアの作曲家たち
~16-17世紀ナポリ前衛音楽の影響~ [フランチェスコ・コルティ]FRESCOBALDI AND THE SOUTH - Intendomi chi può che m'intend'io (Corti)
発売日:2023年07月07日
 NMLアルバム番号:A547
NMLアルバム番号:A547CD国内仕様 解説日本語訳付き価格:3,300円(税込、送料無料)
イタリア式チェンバロの美音が解き明かすナポリ流儀の影響。
名手コルティの快挙!2018年の単独来日で話題を呼び、ARCANAレーベルではヘンデル『八つの組曲』(A499/NYCX-10285)が大きなヒットとなったイタリアの実力派チェンバロ奏者フランチェスコ・コルティ。古楽器楽団イル・ポモ・ドーロとのバロック・オペラやバッハ協奏曲でも名盤を連発していますが、今回は古楽鍵盤奏者としての原点に立ち返り、17世紀前半にローマ教皇庁のオルガン奏者として活躍しバロック鍵盤音楽史上に不滅の地位を築いたフレスコバルディに迫ります。 この重要作曲家の精巧にして多面的な音楽語法は無から生じたわけではなく、前世紀以来ナポリで育まれていた、不協和音を多用する実験精神旺盛な鍵盤技法から大きな影響を受けていたことが音楽史研究の末明らかになっていますが、ここでは具体的な作品の演奏を通じてその影響関係を探求。バロック期のイタリアのモデルに基づく2台のチェンバロを駆使し、1600年前後の和声感覚に立ち返って織り上げられる高雅な解釈に触れるうち、フレスコバルディの傑作群という金字塔的存在の「下絵」が明かされてゆくような、発見に満ちた選曲と曲順となっています(有名なトッカータや変奏曲が多数含まれている点も好感度大)。欧州古楽界に数多くの愛奏者を持つ名工フィリップ・ユモーが手掛けた楽器はいずれも、イタリア式楽器ならではの鋭角的な音の立ち上がりが急速なパッセージで粒立ちの良さを失わないばかりか、各音に含まれる豊饒な音色成分がこの上なく魅力的。 数々の古楽名盤の録音場所にもなっている教会のほどよい残響をよく伝える、ALPHAレーベルでの活躍も目覚ましいエンジニア吉田研の精妙な仕事も頼もしい1枚です。 -
スプレッツァトゥーラ
~さりげなく~ [イ・フィラトーリ・ディ・ムジカ]発売日:2023年06月16日
CD国内盤価格:3,000円(税込、送料無料)
2人が操る4種類の楽器の魅力
16-17世紀イタリアの作品―『イ・フィラトーリ・ディ・ムジカ』の初アルバム。2人が操る4種類の楽器の魅力が活きる、16世紀後半から17世紀のイタリアの作品に焦点を当て、リサーチの先にある自由な表現を追求する1枚。 ― イ・フィラトーリ・ディ・ムジカは東京藝術大学で出会った中島恵美(リコーダー/フラウト・トラヴェルソ)、曽根田駿(チェンバロ/古楽ハープ)の2人によって結成されたデュオ。2014年から活動を開始し、中世からバロックまでの音楽をレパートリーとしている。「歴史的演奏法;Historically informed performance」の追及に力を入れ、資料を研究することによって、より自由でより豊かな演奏を目指して活動している。 -
ジョン・コプラリオと
16世紀のマドリガーレ作曲家たち
~コプラリオはただのオウムか、
それとも才能あるパロディストか?~ [プルート・アンサンブル、ハトホル・コンソート]Fantasias on Madrigals - FERRABOSCO I, A. / PALESTRINA, G.P. / MARENZIO, L. (John Coprario - Parrot or Ingenious Parodist) (Lischka)
発売日:2022年09月09日
 NMLアルバム番号:RAM2107
NMLアルバム番号:RAM2107CD価格:2,475円(税込)
欧州古楽シーン最前線の名手たちが、イタリア音楽贔屓のルネサンス英国で活躍した作曲家の素顔に迫るイングランドがヨーロッパ屈指の音楽大国だった16世紀。その終わり頃には、新たな音楽拠点イタリアの先進的な音楽が英国人たちにも注目されるようになりました。 1570年頃に生まれたジョン・コプラリオ(コペラリオ)はそうした時代を象徴する英国人作曲家。イタリア渡航を機にジョン・クーパーという本名よりコプラリオとイタリアめかした名で作品を発表するようになり、同時代のイタリア人作曲家たちの声楽作品を下敷きにした器楽合奏曲を書くなど両地域の文化交流に大きく貢献する活動を続けました。 ここでは同時代のイタリアとイングランドの音楽を器楽・声楽の双方に渡って集め、コプラリオの合奏版と元歌となった作品を並べるなど入念な曲順を通じ、16世紀末の英国音楽の活況にイタリア・ルネサンス音楽が、どれほど新たな風として吹きこんでいたかを探る興味深いプログラムが提案されています。 古楽大国ベルギーを拠点にユニークな活躍を続けるガンバ合奏団ハトホル・コンソートに加え、声楽パートにはコレギウム・ヴォカーレ・ヘントやカピーリャ・フラメンカなどでも絶妙なアンサンブルを聴かせてきたマルニクス・デ・カットを中心に、ソリストとしての活動も目立つバスのハリー・ファン・デル・カンプも加わる実力派集団プルート・アンサンブルが参加。単なる「オウム返し」ではないコプラリオ芸術の奥深さを解き明かす、最前線の古楽プレイヤーたちによる筋の通ったプログラムに興味が尽きません。
-
ラージの七弦琴
~イタリア初期バロック、詩人歌手の作曲した音楽を集めて~ [リッカルド・ピザーニ、フランチェスコ・チェーラ、アンサンブル・アルテ・ムジカ]RASI, F.: Kithara of Seven Strings (The) (Pisani, Ensemble Arte Musica, Cera)
発売日:2021年11月19日
 NMLアルバム番号:A492
NMLアルバム番号:A492CD価格:2,475円(税込)
バロック様式草創期の超重要人物の素顔に迫った、
イタリア古楽勢ならではの快挙多声の絡み合い重視のルネサンス音楽から一転、独唱に光を当て、言語による演劇的表現と音楽性とを融合させた新しい音楽を目指したのが、1600年前後のイタリアの作曲家たち。こうして生まれた新たな音楽様式はのちに「バロック」と呼ばれますが、その最初期の発展があくまで「言語」への強い関心から生まれたものであったことは、バロック音楽を知れば知るほど実感されるのではないでしょうか。 このアルバムはそうしたバロック草創期のイタリアにあって、さまざまな重要作曲家たちと知遇を得て多面的な活躍をみせたフランチェスコ・ラージが主人公。彼はモンテヴェルディの傑作《オルフェオ》初演時にタイトルロールを演じ歌い、ジェズアルドとの交流でも知られたほか、多くの作曲家たちがマドリガーレの歌詞として使った詩の作者でもあった音楽家=詩人で、いくつもの詩集で名を残したほか、1608年にヴェネツィアで刊行された曲集をはじめ作曲家として音楽も数多く残しています。 このアルバムではイタリア随一の多彩な古楽歌手リッカルド・ピザーニを中心に、この時代の秘曲発掘でも実績を重ねて数多くの名盤がある鍵盤奏者フランチェスコ・チェーラのアンサンブルが器楽隊として参加。幾多の共鳴弦を持つ弓奏低音弦楽器リローネや初期バロック音楽に必須のダブルハープなど、多様な通奏低音楽器の組み合わせを通じて生のままのイタリア古楽世界を蘇らせます。 同世代の画家カラヴァッジョの艶やかで生々しい絵画表現も思い起こさせる、人肌と血潮の温もりを宿した声と古楽器の響きをじっくり味わえる1枚。50ページに及ぶライナーノート(英・仏・伊)の解説もきわめて充実しています。 -
「ドン・ルイ・ロッシの写本」 [アンサンブル・ポイエシス]
Vocal and Instrumental Music - MONTEVERDI, C. / BASSANI, O. / MACQUE, G. de (Este libro es de Don Luis Rossi) (Ensemble Poiesis, Fourquier)
発売日:2019年09月13日
 NMLアルバム番号:ALPHA496
NMLアルバム番号:ALPHA496CD価格:1,425円(税込)
謎に包まれた作曲家ルイージ・ロッシ(1598頃-1653)の手書きによる、現在は大英博物館の収蔵となる写本。モンテヴェルディ「オリンピアの嘆き」とジュズアルド「王のフランスの歌」の唯一の譜例でも知られるこの写本に残された、1600年前後のイタリア音楽を集めたアルバム。ソプラノとテノール、トリプリハープ、ガンバ、リローネという編成で、マントヴァ、フィレンツェ、ローマからナポリに至るイタリア南北の初期バロックの魅力を縦横無尽に引き出した隠れた名録音。 Zig Zag Territoires初期の名盤が嬉しい低価格で再発売です。
-
-★『レコード芸術』特選盤(2019年9月号)★-
「理性の死」
~ルネサンス、美と混沌の音楽芸術 ~
器楽作品集 [ジョヴァンニ・アントニーニ(各種リコーダー、ドゥルツィアン&総指揮)、イル・ジャルディーノ・アルモニコ(古楽器使用)]Instrumental Ensemble Music - AGRICOLA, A. / CARESANA, C. / MAINERIO, G. / RUFFO, V. (La morte della ragione) (Il Giardino Armonico, Antonini)
発売日:2019年05月17日
 NMLアルバム番号:ALPHA450
NMLアルバム番号:ALPHA450CD+BOOK国内仕様 日本語解説付価格:2,970円(税込)
エッジの効いたスリリングなヴィヴァルディ録音で注目を集め、本場イタリアに新たな古楽の息吹きあり! と、リコーダー奏者ジョヴァンニ・アントニーニとイル・ジャルディーノ・アルモニコが世界を瞠目させたのが、今からおよそ30年前。その後アントニーニはレパートリーを古典派まで広げ、今ではハイドンやベートーヴェンの交響曲でも驚くべき録音を世に送り出しています。しかし、彼はなによりリコーダー奏者。その原点に立ち返り、ルネサンス期の音楽に全てを捧げた思いがけない新録音をAlphaレーベルからリリースします。 神の秩序と理性的調和が全てだった16世紀にも、混沌は何かと人の世を脅かしもすれば、予測不能の奔放さが人を強く惹きつけることもありました。英国からイタリアまで広範な地域にわたる音楽の実例から、アントニーニが厳選した選曲と曲順にぜひ振りまわされたいもの。カラー図版満載の解説書(国内仕様では解説部分訳と、バーゼルで音楽学を専攻するリコーダー奏者菅沼起一氏による別途解題を封入)も見ごたえたっぷり、選曲の妙を読み解く楽しみも尽きません。各種リコーダーと木管コルネット、古雅なる弦楽器を交えてのルネサンス・オーケストラ編成に酔いしれる痛快な新録音です。
-
霊的な劇場
1610年前後ローマ・ヌオーヴァ教会
初期バロック 告解の音楽 [インアルト/アリス・フォクルール/レイナウト・ファン・メヘレン/ステファニー・ルクレール/オリヴィエ・コワフェ/ギヨーム・オルリー/ギィ・ハンセン/スザンナ・デフェンディ/シャルロット・ファン・パッセン/バルト・フローメン /ロドニー・プラダ/ノエリア・レベルテ・レチェ/シモーネ・ヴァッレロトンダ/クリストフ・ゾマー /マルク・マイゼル /ランベール・コルソン]Vocal and Chamber Music (17th Century) - ANERIO, G.F. / CAVALIERI, E. de' / MACQUE, G. de / QUAGLIATI, P. (Teatro spirituale) (InAlto, Colson)
発売日:2019年04月12日
 NMLアルバム番号:RIC399
NMLアルバム番号:RIC399CD価格:2,475円(税込)
ベルギーの木管コルネット&ツィンク奏者、ランベール・コルソン率いる古楽集団インアルトによる、ローマのヌオーヴァ教会に伝わる詩篇を中心としたアルバム。 1600年にカヴァリエーリの「魂と肉体の劇」が初めて上演されたこの教会に保存された17世紀初頭の写本には、「告解の秘跡の詩篇」と呼ばれる作曲者不詳の詩篇7曲が含まれていました。これらは初期オペラの旋律を思わせるモノディ形式のレチタール・カンタンド(旋律と伴奏がはっきりとして歌詞が聞き取りやすい、現在では一般的な歌の形)で書かれており、これは当時、それまでの多声音楽と比較すると画期的なものでした。さらに今聴いても斬新に響く不協和音なども用いられており、それはこのアルバムのコンセプト、演奏に大きな影響を与えています。 名オルガン奏者ベルナール・フォクルールの愛娘アリスをメインとする声楽陣、4本ものトロンボーン(サックバット)が響く器楽陣をコルソンがまとめ上げ、あくまでもオリジナルの譜面を尊重しながらも、当時の風習に沿ったオリジナルの解釈も加えた新鮮な演奏を聴かせてくれます。