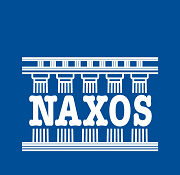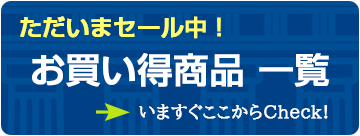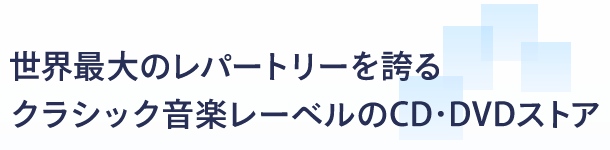ボワモルティエ(ジョゼフ・ボダン・ド) Boismortier, Joseph Bodin de
| 生没年 | 1689-1755 | 国 | フランス |
|---|---|---|---|
| 辞書順 | 「ホ」 | NML作曲家番号 | 122071 |
-
ボワモルティエ(1689-1755):
《公爵夫人家のドン・キホーテ》 [エルヴェ・ニケ、ル・コンセール・スピリチュエル マティアス・ヴィダル、ジャン=ガブリエル・サン=マルタン、シャンタル・サントン=ジェフェリ ほか]発売日:2022年09月23日
CD価格:2,475円(税込)
鬼才ニケが入れ込む「ラモーを凌ぐ」天才作曲家の秘作、圧巻の最新録音!フランス・バロック復興の勢いを数十年にわたり第一線の演奏シーンで支え、今やバロックのみならずロマン派以降のフランス音楽でも名演を連発している鬼才指揮者エルヴェ・ニケ。作曲家の現在の知名度にこだわることなく、演奏機会の少ない作品の発掘にも意欲的に取り組んでいますが、18世紀に誰よりも早くフリーランス作曲家として自活を達成した人気作曲家ボワモルティエには「同世代のラモーより先をゆく先進的作曲家」と絶賛を惜しみません。 彼が早くから入れ込み実演でも頻繁にとりあげてきた《公爵夫人家のドン・キホーテ》は、NAXOSに録音している(8.553647)ほかALPHAで映像もリリースしていますが(ALPHA711)、今回はヴェルサイユでCDを再録音しました。従者サンチョ・パンサとともに所領に迷い込んだドン・キホーテをからかうべく公爵夫人が素人芝居を開催、恋するアルティシドールやニッポンの女帝に扮して二人を翻弄する荒唐無稽な物語を、ロココ期のフランス音楽ならではの典雅な魅力たっぷりに聴かせてくれます。 コロナ禍によるスケジュール変更の間隙をぬって実現したという贅沢布陣の録音で、主人公のドン・キホーテと公爵夫人はそれぞれヴィダルとサントン=ジェフェリという現代フランス最前線を行く名歌手が鮮やかに演じ切り、合唱と合奏が織りなす連携の面白さもル・コンセール・スピリチュエルの俊才陣によってひときわ魅力的に響きます。 旧盤CDから四半世紀をへて、ニケ自身も解釈の深まりを自負する名演で、起伏に富んだ物語の面白さをじっくり堪能できます。
収録作曲家:
-
『「ユリス」の登場人物たち』
ルベル(1666-1747)&
ボワモルティエ(1689-1755):
2台のクラヴサンによる組曲集 [ロリス・バリュカン (クラヴサン) クレマン・ジョフロワ (クラヴサン)]REBEL, J.-F. / BOISMORTIER, J.B. de: Suites for 2 Harpsichords (Barrucand, Geoffroy)
発売日:2020年03月27日
 NMLアルバム番号:CVS021
NMLアルバム番号:CVS021CD価格:2,475円(税込)
豪華絢爛、効果絶大!
『四大元素』含むフランス・バロックの王道を、ヴェルサイユ伝来の2台のクラヴサンで!フランス・バロック最盛期に活躍した二人の作曲家による作品を、2台のクラヴサン(チェンバロ)で演奏したアルバム。18世紀中盤にかけ、フランス・クラヴサン音楽の語法が格段に華やかになってゆく時期の音楽の魅力が、歴史的楽器で最大限に伝えられます。 使われている楽器は2台ともヴェルサイユ宮殿に伝わるもので、ルイ15世の娘でクラヴサン演奏を愛したヴィクトワール王女の居室だった場所に置かれています。うち1台は18世紀フランスで名高かったアントウェルペンのリュッケルス製。早い時期にヴェルサイユに持ち込まれ、やがてフランス・バロック型へ大きな改修(ラヴァルマン)を受けています。もう1台の楽器にはパリの楽器製作者フランソワ=エティエンヌ・ブランシェによる1746年の署名があり、ルイ15世の治世のパリにおける典型的な楽器。2台のクラヴサンがたいへん豪華に響き、『四大元素』の冒頭「カオス」の有名な不協和音のインパクトも絶大です。 -
発売日:2017年09月22日
CD価格:2,100円(税込)
フランス・バロック期の作曲家の一人、ボワモルティエの代表的名曲「6つのソナタOp.51」。イタリアの協奏曲様式をフランスに導入した人として知られ、とりわけ、フルートを用いた作品で人気を獲得しました。 この6つのソナタは、フルートとヴァイオリンのデュオですが、ヴァイオリンの重音奏法を巧みに生かすことで、充実したポリフォニーと、ロココ調の優雅さが生まれています。“エリジウム・アンサンブル”は1985年に設立されれ25年以上も活動を続けてきたデュオ。きわめて息のあった対話が生まれています。
収録作曲家:
-
弦に頼らずとも
バロック式オーボエ・バンドによる協奏曲、序曲、ソナタ [ラ・プティット・エキュリー]発売日:2024年11月01日
CD価格:2,775円(税込)
これぞオーボエ属の原風景。
フランス風アンサンブルで読み解くバロック欧州世界ルイ14世の王室で活躍したオーボエ属中心の管楽合奏団ラ・グランド・エキュリー(大厩舎楽団)をモデルに、オーボエ属の楽器だけでコンソートを組み室内楽編成で活動するラ・プティット・エキュリー。2022年の英国バロック作品集(A527)に続き、今度は時代も地域も拡げパリ、ロンドン、ハンブルク、ヴェネツィアなど欧州各地の音楽都市で、17世紀末から18世紀にかけ活躍した重要作曲家たちの作品を集めたアルバムを制作しました。 アルバムのタイトルNo Strings Attachedは「見返りを求めず人助けに臨む」という意味の慣用表現ですが、今回はその字面通り弦楽器を使わない彼らなりの編成で、本来ヴァイオリン属の合奏を想定して書かれている曲を数多く選曲。使える楽器だけで編曲演奏することが当然とみなされたバロック期の習慣に立ち返り、基本的にオーボエ属の響きだけで、適宜打楽器も盛り込んでヴィヴァルディやヘンデルの作品を演奏しています。きわめて新鮮な響きでありながら、作品様式をふまえた演奏解釈も相まって、思わぬところで効果的なアクセントを添える打楽器も含め、自然に瑞々しく味わえるのが驚きです。「当時の響き」に対する認識を新たにしてくれる充実の1枚です。 -
輝かしき時代
18世紀フランスにおけるヴァイオリンとヴィオールの共存 [リュシル・ブーランジェ、シモン・ピエール、オリヴィエ・フォルタン]Golden Hour (The) - FRANCOEUR, F. / REBEL, J.-F. / LECLAIR, J.-M. (Boulanger, Pierre, Fortin)
発売日:2024年02月23日
 NMLアルバム番号:ALPHA1059
NMLアルバム番号:ALPHA1059CD価格:2,775円(税込)
ヴィオールとヴァイオリンの共存期に生まれた18世紀フランスの妙なる音世界フランスで近年めざましい活躍をみせるソリストたちによる18世紀フランス室内楽作品集。ルイ14世の治世に、歌心に富み技巧的な演奏に秀でたヴァイオリンを独奏楽器として扱うイタリア風の音楽に抵抗を示したフランスの人々も、老王の逝去後イタリア音楽愛好で知られたオルレアン公が摂政となった時代を経て、ルイ15世の治世下では急速にこの楽器のための音楽を愛好するようになります。 他方、前世紀以来フランスで愛奏されてきたヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)は徐々に姿を消してゆくのですが、本盤はその直前、どちらの楽器もフランスで名手が腕を競っていた頃に書かれた作品を集めており、ヴァイオリンが主役を占めるソナタでも低音部でヴィオールに大きな活躍の場が与えられた曲が多いのが特徴。アルバムの名義はヴィオール奏者のリュシル・ブーランジェが先に立っており、両者が対等の立場で対話を繰り広げる稀有な音楽世界をじっくり味わえます。 鍵盤のオリヴィエ・フォルタンも自身の楽団アンサンブル・マスクで重ねた豊かな室内楽経験を存分に活かし、ボルドー出身のシモン・ピエールのニュアンスに富んだヴァイオリンやブーランジェの雄弁なヴィオールに全く負けない存在感で各作品の魅力を豊かに引き出してゆきます。
-
純朴なる羊飼い
ヴィエラルーのための18世紀フランス音楽 [レインベルト・デ・レーウ(ピアノ&指揮)、コレギウム・ヴォカーレ・ヘント(合唱)、マルニクス・ド・カート(オルガン)]BERGER INNOCENT (LE) (Ensemble Danguy, Humbert, Miller)
発売日:2024年01月12日
 NMLアルバム番号:RIC448
NMLアルバム番号:RIC448CD価格:2,475円(税込)
田園気分に浸るロココの響き、名手トビー・ミラーの真骨頂木製の箱の端につけたハンドルで楽器内の車輪を廻し、その車輪が接する弦を擦ることで音を出す楽器ハーディガーディ。その歴史を中世まで遡れば知識人社会では一時廃れ、農村で伝承曲を奏でる楽器として辛うじて残りましたが、そのイメージが逆に牧歌的な理想郷での田園生活への憧れと結びついたのが18世紀のフランスでした。フランス語でヴィエラルー(車輪式ヴィエル)の名のもと、愛奏者の激増に合わせて上流階級向けの楽器が多く作られ、同時期に同じ事情で流行したミュゼットと共に多くの曲が誕生しました。 21世紀にその名手として活躍、中世音楽からバッハの無伴奏曲までヴィエラルーで弾きこなす俊才トビー・ミラーはここで、独奏楽器としてのヴィエラルーの可能性の広さや声楽との相性を十全に示すべく、多角的な視点で作品を厳選。ミュゼット(演奏は横笛とバグパイプの名手ラザレヴィチ!)やヴァイオリンとの共演やヴィエラルー二重奏なども盛り込むことで、2017年にリリースした技巧派ソナタやカンタートを集めたアルバム(RIC382)とはまた異なる角度からロココのヴィエラルー芸術の面白さを堪能させてくれます。 ふくよかで柔軟なミュゼットの音との対比も、同じ弦を擦るヴァイオリンとの特性の違いも聴きどころ。通奏低音付きソナタではトビー・ミラーが細やかな装飾音や急速なパッセージを流麗に弾きこなし、時に異界感さえ感じさせる曲作りの面白さと相俟って、伸縮自在の音作りでこの楽器の味わいを最大限に楽しませてくれます。 楽器や音色の珍しさに全く甘んじない、圧巻の音楽性あればこその聴きごたえ。多くの人に届いてほしい21世紀ならではの古楽アルバムです。
-
Fakturen ― ハーモニーの四元素 ― [ファゴット・カルテット・ザ・ナッツ]
FAKTUREN - 4 Elements of Harmony (Nuts Bassoon Quartet, Aichi Chamber Orchestra, Toshiaki Murakami)
発売日:2023年12月22日
 NMLアルバム番号:MYCL-00029
NMLアルバム番号:MYCL-00029CD国内盤価格:3,300円(税込、送料無料)
ファゴット4本が魅せる妙技。
ファゴット・カルテット・ザ・ナッツ デビュー!名古屋フィル3名と愛知室内オーケストラ1名のファゴット奏者によるアンサンブル、「ザ・ナッツ」のデビュー・アルバムです。注目は、日本初演となったケーパーのファゴット・カルテットと管弦楽のための協奏曲「Fakturen」です。珍しいファゴット4本のために書かれた協奏曲で、美しいメロディと色彩豊かなオーケストレーションが楽しめる作品です。 その他にもボワモルティエや團伊玖磨などの古今東西のオリジナル作品が並び、ファゴットの音色、妙技で埋め尽くされています。ファゴットという楽器が持つ表現力の幅に驚くことでしょう。「ザ・ナッツ」のメンバーによる軽やかなサウンドと表情豊かな演奏をぜひお聴きください。 -
『暗闇と深淵』
独唱と通奏低音によるルソン・ド・テネブル、
18世紀フランス語圏から [ウジェーヌ・ルフェーヴル、リュシル・テシエ、アンサンブル・ルヴィアタン]発売日:2023年03月10日
CD価格:2,475円(税込)
「ルソン」の静謐な響きを、ヴェルサイユ宮殿に集うフランス最前線の俊才たちとキリスト教社会で春の日曜日に祝われる復活祭に先立ち、救世主イエスが現世で十字架にかけられ苦しみぬいて絶命したことを思い返しながら、人類の罪深さを考え直す「聖週間」。バロック期のフランス語圏では、この時期の夜明け前に行われていた祈りの時間帯をずらし、日中に小編成の峻厳・清廉な音楽を通じて行うルソン・ド・テネブル(暗闇の朝課)の儀式があり、そのために書かれた楽曲が多く現存しています。 その特質上、華美な響きを避けてオルガン一つ、ないしそこに低音楽器を添える程度で独唱者が歌う小編成の音楽に仕上げられますが、ここではフランス古楽シーン最前線で活躍する若き名手たちが、バスーン、ヴィオール(ガンバ)、ヴィオローネ、チェロという4種の低音楽器を用い、クラヴサンやオルガンとともに、趣深いくすんだ響きで18世紀初頭の祈りの場を再現。 近年発見された手稿譜によるフォルクレ父子どちらかの組曲や人気作曲家ボワモルティエの名品編曲など器楽トラックも充実していますが、躍進めざましい独唱者ウジェーヌ・ルフェーヴルの温もり豊かな独唱がこれらの古楽器の響きと実によくなじむ一連のルソンは、演奏機会の少なさが不思議なほど魅力的に聴こえ興趣が尽きません。 ブリュッセルのイタリア系作曲家フィオッコやブルゴーニュ地方ディジョンのジョゼフ・ミシェルなど、フランス王室に縛られない選曲で視野を広げてくれるプログラムも好感度大。ヴェルサイユ宮殿の小礼拝堂の穏やかな音響をよく捉えた自然派録音でお楽しみください。
-
「ニレの木陰で」
18世紀フランスのブリュネットとコントルダンス [フランソワ・ラザレヴィチ(指揮、フラウト・トラヴェルソ、ミュゼット)/レ・ミュジシャン・ド・サン=ジュリアン(古楽器使用)]Vocal and Chamber Music - SCELLERY, C.-E.B. de / BOUSSET, J.-B. de (À l'ombre d'un ormeau) (Les Musiciens de Saint-Julien, Lazarevitch)
発売日:2018年09月12日
 NMLアルバム番号:ALPHA342
NMLアルバム番号:ALPHA342CD価格:1,520円(税込)
18世紀フランスの人々を夢中にさせた音楽を集めたアルバム。ここに集められたブリュネットと呼ばれる歌や、英国のカントリー・ダンスが輸入されて発展したコントルダンスなどは、農民の音楽を元にしたものとして貴族階級から火がつき、やがてパリの市民たちの間にまで広がっていきました。ふいご付きのバグパイプ(ミュゼット)を中心に、ハーディガーディ、フルートなどの多彩な音色が、当時の日常生活の中で豊かに奏でられた音楽の楽しさ、美しさを私達に存分に味あわせてくれます。