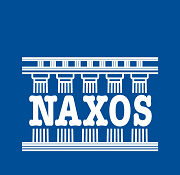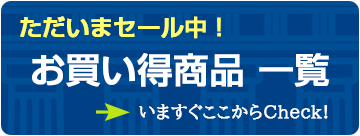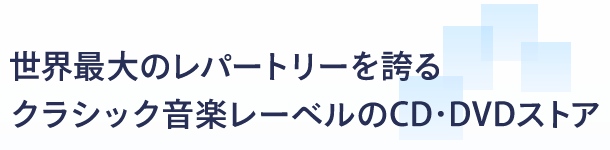グレフ(オリヴィエ) Greif, Olivier
| 生没年 | 1950-2000 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 辞書順 | 「ク」 | NML作曲家番号 | 52093 |
-
DANSE DES MORTS - 死者のダンス
オリヴィエ・グレフ(1950-2000):
作品集 [エドウィン・ファルディーニ(バリトン)/アトリエ・ドゥ・ムジケ/ピエール・デュムソー(指揮)/シュテファン・ゲンツ(バリトン)/オリヴィエ・グレフ(ピアノ)/ピエール・フシュヌレ(ヴァイオリン)/リーズ・ベルトー(ヴィオラ)/ヤン・ルヴィオノワ(チェロ)/フィリップ・アタ(ピアノ)]GREIF, O.: Quadruple Concerto, "La Danse des morts" / Livre des Saints Irlandais / Symphony (Fardini, Genz, Greif, L'Atelier de musique, Dumoussaud)
発売日:2021年09月10日
 NMLアルバム番号:LBM035
NMLアルバム番号:LBM035CD価格:2,475円(税込)
フランスの作曲家・ピアニスト、オリヴィエ・グレフ。パリ音楽院を経てジュリアード音楽院で研鑽を積み、一時期はルチアーノ・ベリオにも師事。初期には前衛的な作品を書いていましたが、次第に古楽や文学、神秘主義をモティーフにし、機能和声を用いた調性感のある音楽を創り上げるようになりました。多くの演奏家たちが彼の作品を採り上げ出した矢先、2020年に急逝したことで、その独自性の高い作品に注目が集まっています。 グレフの生誕70周年を記念して作られたこのアルバムには、第25回ドーヴィル・イースター・フェスティヴァルで若い演奏家たちによって演奏された2作品のライヴ録音と、1998年の同音楽祭で作曲家自身がピアノを弾き、シュテファン・ゲンツが歌った「アイルランドの聖人の書」のアーカイヴ録音を収録。また「声のための交響曲」では注目の指揮者デュムソーが全体をまとめています。 グレフの魅力を伝える1枚です。
収録作曲家:
-
グレフ(1950-2000):
LES CHANTS DE L'ÂME - 魂の歌
パリの遊歩道
エスケシュ(1965-):
D'UNE DOULEUR MUETTE [マリー=ロール・ガルニエ(ソプラノ)/クレメンティーヌ・デクトゥール(ソプラノ)/パコ・ガルシア(テノール)/ヤン・ルヴィオノワ(チェロ)/フィリップ・アタ(ピアノ)]GREIF, O.: Chants de l’Âme (Les) / Les Trottoirs de Paris (M.-L. Garnier, P. Garcia, Decouture, Y. Levionnois, Hattat)
発売日:2020年02月21日
 NMLアルバム番号:LBM024
NMLアルバム番号:LBM024CD価格:2,475円(税込)
2020年は、フランスの近代作曲家オリヴィエ・グレフの没後20周年。ルチアーノ・ベリオに師事しながらも決して前衛的な作風を採用することはなく、詩的な作品を350作以上も書き続けたグレフ。活動初期には認められなかった彼の作品が評価され始めたのは、1990年以降のことであり、中でも1992年に作曲されたチェロとピアノのための「ソナタ・ド・レクイエム」はいくつかの録音により広く親しまれています。 このアルバムには、1979年から1995年に渡って構想された歌曲集「魂の歌」を中心に、同じくグレフの「パリの遊歩道」と、1965年生まれのエスケシュの作品を収録。抒情的で豊かなハーモニーを持つこれらの曲を、名手アタの伴奏のもと若く優れた歌手たちが歌います。
-
『HYPNOS(ヒュプノス) 眠り』 [シモン=ピエール・ベスティオン、マッテオ・パストリーノ、アドリアン・マビール、ラ・タンペート]
Choral Concert: Tempête (La) - FÉVIN, A. de / GREIF, O. / ISAAC, H. / SCELSI, G. / TAVENER, J. (Hypnos)
発売日:2022年01月14日
 NMLアルバム番号:ALPHA786
NMLアルバム番号:ALPHA786CD価格:2,475円(税込)
中世とルネサンス、瞑想的な20世紀音楽。
眠りと死をたゆたう静謐な合唱空間古楽レパートリーに希有ともいえる適性を見せながら、アルバム作りに際しては必ず20世紀以降の作品など近現代の要素をバロック以前の音楽に交え、あくまでオーガニックな響きを保ちながら常に新鮮な音楽体験へ誘ってくれるフランスの声楽アンサンブル、ラ・タンペート。これまでにも近東伝統歌謡とドイツ初期バロック、ないしマショーとストラヴィンスキーなどを並列的に扱ったユニークなアルバムをリリースしていますが、今回のテーマは「眠りと死」。表題のヒュプノスとは古代ギリシャの眠りの神で(「催眠術」をあらわす欧州言語ヒュプノシスの語源)、神話では兄弟のタナトス(死の神)とともに夜の女神から生まれたとされています。 指揮者ベスティオンは原初のキリスト教会における礼拝を想像上で自由に再現することを意識しながら、西と東が交わるギリシャの地にも思いを馳せつつ、ほのかな異界感を漂わせたグレゴリオ聖歌以前のカトリック聖歌にまで遡る、ルネサンス以前の音楽を味わい深いア・カペラ中心の響きで今に甦らせてゆきます。 それらの音と違和感なく並ぶ20世紀作品もみな自然な響きの魅力を活かした楽曲ばかり。ピュアな和声感に二度や七度の不協和なはずの音の重なりが自然と隣り合うサウンドは、ラ・タンペートのやや東洋的趣きも感じられる独特な古楽歌唱の効果と言ってよいでしょう。 現代性と昔日らしさの補助線のように、バス・クラリネットと古楽器コルネットが声楽を支える音作りも精妙。「深く聴く」という体験の余韻をじっくり味あわせながら、此岸と彼岸の境が静かに溶けてゆく音の流れに出会える1枚です。