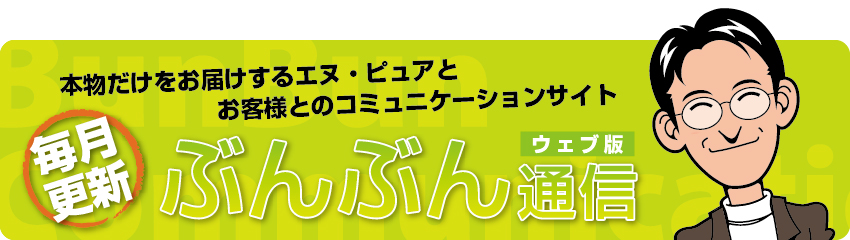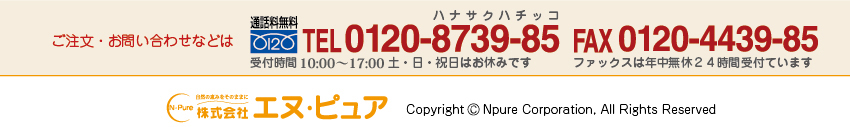Vol.34 ゲスト:辻和之先生 【3】


長寿と健康のコツ
辻 漢方治療の範囲というのはとても広くて、本当にいろいろな領域の患者さんが来院されます。最近は腰や膝などの整形外科疾患、アトピー性皮膚炎の患者さんが特に多いですね。東洋医学は、病名ではなく症状を聞いたうえで体質や生活習慣などを考慮して、その方に合った漢方薬を煎じて処方しますから効果の実感が早いのだと思います。糖尿病の相談も多いですね。糖尿病の方には内臓脂肪を減らしながら生活習慣も含めたアドバイスをしていますので、とても喜んで頂いています。
鳴海 個人の体質や生活習慣まで網羅して行なう治療方法は「人間は自然界の一部である」という東洋医学の考え方そのものですね。
東洋では、太陽と月、男と女、プラスとマイナスといった相反するもの(陰陽)と、木火土金水(五行)という要素でこの世の中は成り立っているという「陰陽五行」という考え方がありますが、東洋医学でもこうした考え方は用いられているのでしょうか?
辻 人間は自然界の一部ですから「陰陽五行説」はそのまま人間の身体にも当てはまります。体質も食べ物も陰性と陽性に分かれますし、内臓を表す五臓はそのまま五行に当てはまるんです。(図①参照)
病気は、気・血・津液の不足や巡りの悪さで発症しますが、その要因には、五臓の心、肝、脾、肺、腎の病態が絡み合い、さらに外邪(外的な要因)との関係では、正気が不足している状態になった時に外邪に負けて病気になります。治癒に必要な要素は、気・血・津液が過不足なくあること、そして巡りが順調に行なわれていることです。不足しているものを補い、余分なものを瀉す。巡りの悪い場合は、巡りを改善させる。そのためにはその生成や巡りに関与するそれぞれの五臓の状態を健全にさせる必要があります。それらを治療する手段として漢方薬や鍼灸などがあるわけです。自然界と人間の身体を相似性として捉えた先人達の感性と智恵の深さには本当に驚かされますね。

鳴海 東洋医学というのは本当に奥が深いですね。
長い歴史の中で先人達が追い求めてきた理想の医学、そして理想の生き方を、私たちもこうして受け継いでいることが実感として沸いてきます。
辻 理想の医学、理想の生き方を追い求めてきた長い歴史の中でわかっている健康のコツがいくつかあります。
一つは「食べ過ぎないこと」つまり「腹八分目」です。これは江戸時代に「養生訓」を著した貝原益軒さんもおっしゃっていますね。
二つめは「適度な運動をすること」。激しい運動ではなく、歩いたり、日常的な家事をまめにこなしたりといった程度でも充分です。
どちらも生活習慣そのものですよね。「過食」と「運動不足」がすべての病気の基になると言っても過言ではないでしょう。
それに「新しいことに常にチャレンジする気持ちを持つこと」も、若々しさを保つ秘訣ではないでしょうか。97歳になった今でも診療をし、講演会などで全国を飛び回っている聖路加病院・名誉院長の日野原重明先生もそうおっしゃっています。日野原先生が言うと説得力がありますよね。(笑)
鳴海 過食を慎み、なるべく身体を動かす。そして新しいことにチャレンジしてみることで、いつまでも若々しく元気でいたいものですね。 今日もとても良い勉強をさせて頂きました。貴重なお話を頂きどうもありがとうございました。
(季刊ぶんぶん通信Vol.34 2009年夏号)
辻和之 プロフィール
 昭和26年 北海道江差町に生まれる
昭和26年 北海道江差町に生まれる
昭和50年 千葉大学薬学部卒業
昭和57年 旭川医科大学卒業
平成 4年 医学博士取得
平成10年 新十津川で医療法人和漢全人会
花月クリニック開設
日本東洋医学会 専門医
日本内科学会 認定医
日本内視鏡学会 認定医