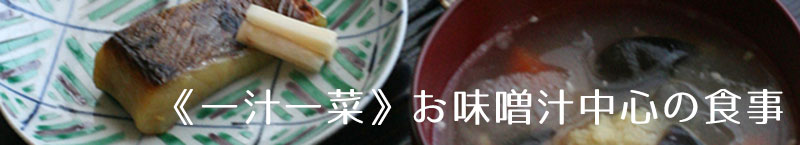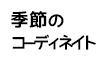【一汁一菜】お味噌汁中心の食事 蛤のお吸い物
奈良国立博物館前に「下下味亭」というごはん屋さんがあったのを覚えていらっしゃる方もあると思います。そのお店の一汁一菜は絶品で、何とか記録に残すために本にしたいと思っているうちにごはん屋さんは止めてしまわれました。
さまざま思い起こしながら少し私の想いも入れつつ、お味噌汁を中心とした食事の基本、一汁一菜を始めてみたく思います。
今年は春が遅く桜は四月に入って咲き始めるようです(2012年春筆)。たのしみが先になるのもよいものでございますね。
この頃になると母は必ず若ごぼうを煮てくれました。貝のお汁と春らしいものの入ったごはん、そして菜の花のおつけもの。そんな食卓を思い浮かべながら、今年は蛤のお汁にいたしました。蛤の下に生湯葉を敷き、独活と木の芽を入れます。お椀は「木地溜内黒蓋付椀」、大変丈夫な椀で、ある料理屋さんがこれ一つを毎日五年使われて、まだ新しく見えると感心なさっていました。蓋付の椀としては大変リーズナブルな良い椀でございます。
若牛蒡は昔の八尾産のものよりも香りが薄くなったように思いますが、どんな理由でしょうか。この牛蒡の茎を若牛蒡といって食べるのは限られた関西(特に大阪)だけらしく、京都の方も奈良の方も知らないとおっしゃいます。八尾のあたり河内の特産だったからなのでしょうか。とても美味しいものです。刷毛目向付は福森さんご自身の作品で、もう何十年も作り続けていらっしゃいます。何を盛ってもよく「愛用する」という言葉通り、一生愛しんで使っていただけます。
桜の花漬は京都の「原了郭」さんのものです。色が美しく、水でもどして丁寧に水気をとりご飯と混ぜ、控え目にお塩を少々。よい香りです。
お漬物は菜の花の糠漬けと、もう冬の名残りの大根の塩もみ。正木さんの桜文皿が久し振りに参りました。控え目な桜の小紋が何とも好もしい盛りやすいお皿です。カレーを入れたりお寿司を盛ったり、さまざまな用い方が出来る形をしています。
よろしき浅春の夕餉となってほしいものです。
若牛蒡煮
醤油で味付けした(お砂糖は入れないで下さい)少しの出汁で薄揚げを煮ておきます。
若牛蒡はよく洗って茎と根を切りはなし、茎と根の間の1.5cmは捨ててください。まな板の上に平らにしてすりこぎの様なもので軽くつぶれない程度に全体をたたきます。根の方も軽くたたきます。それを5〜6cm位に切って水にさらします。二度くらい水をとりかえて3〜4分であくが抜けますので、水を切って、できれば太白のごま油でしっかり炒めます。これを先程の出汁に移してさっと5分くらい煮ます。
白瓷飯碗・大

ほんのりと水色かかった白。素地はとても貴重となった天草陶石です。
海老ヶ瀬
4,840円
木地溜内黒蓋付椀

温かいものを温かく・・・。蓋付きのお椀で、作り手の気持ちもたっぷり込めて・・・。
守田漆器
22,000円
雅造刷毛目蓮弁向付

蓮の花びらのやさしい小鉢です。
福森雅武
13,200円
染付桜文皿・大

お皿の上に桜が満開!桜の模様はひとつずつ丁寧に丁寧に描かれています。
正木春蔵
11,550円
3.5寸長角皿・緑

素朴で繊細・・・、そんな印象の杉本太郎さんから、こちらは小さな小皿です。
杉本太郎
1,980円
黒尺6雪才

ティーセットを(重いですが)6人分乗せることができる大きなお盆です。
奥田志郎
44,000円