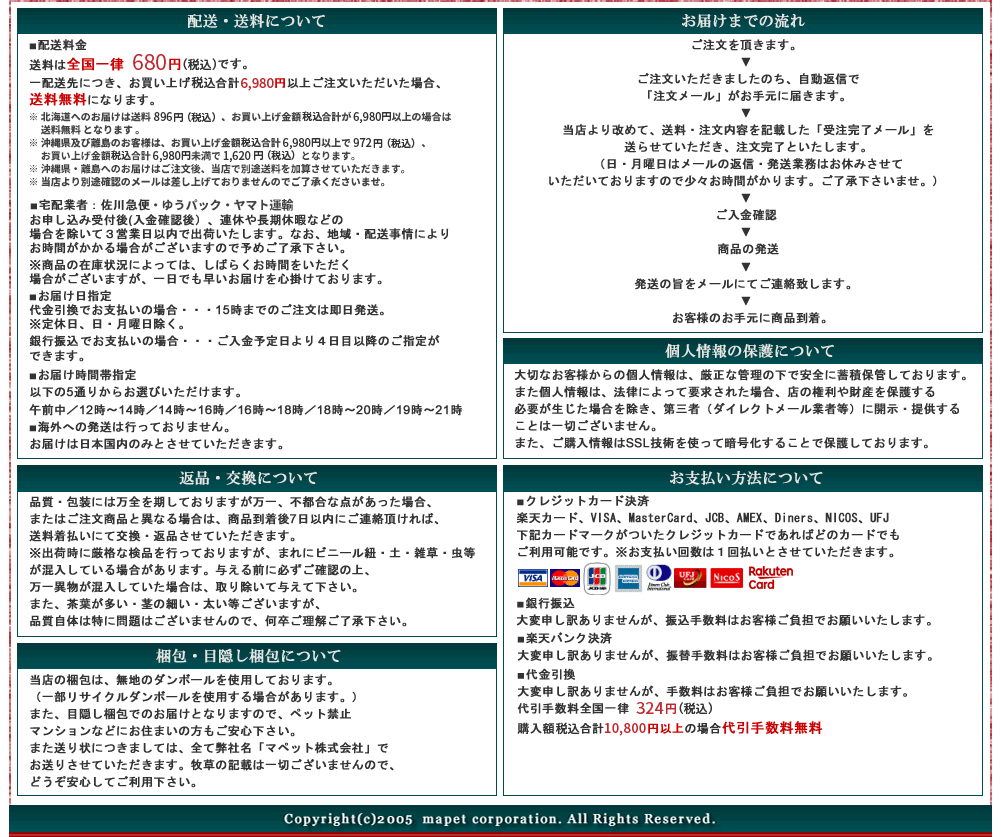小動物の病気
いざという時のために知っておきたい小動物の病気
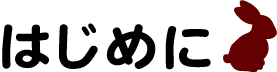
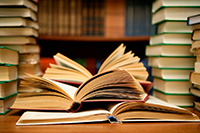
ここでは私が、信憑性の高い書籍などから得た知識を下に、代表的な病気を幾つかご紹介しました。一部、私独自の考え・解釈によるものであるため、飼い主の皆さんには、その点を考慮したうえでご判断頂きたいと思います。
また、ここで書いた以外にも沢山の病気があります。うさぎなどの小動物は、人間と比べて病気や怪我に対しての抵抗力が非常に弱いにもかかわらず、自分で痛みや不調を訴えることができません。ですから、飼い主様が普段から、いつもと違った様子がないか、よく観察する必要があります。
万一、いつもと様子が違うと思ったら、ご自分で判断せず、早めに獣医さんに連れて行って下さい。「たいした事ないだろう」「まだ大丈夫だろう」の安易な気持ちから手遅れになるケースも多いのです。
病気は先天的で、やむをえなく起こるものもありますが、総じて飼育環境が不衛生であったり、食餌の偏りやブラッシングなど、普段からのケアを怠っていることが原因で起こります。
飼い主さんが日々、ご自分の家族(子供)と同様にたっぷりの愛情を注ぎ、責任を持って飼育していくことで、ペットが病気になる確率は、間違いなく少なくなります。そして双方の『HAPPY』が実現できるのです!
是非、がんばって良い飼育環境作りを目指して下さいね!!
また私の経験から、新しくうさぎなど小動物を迎え入れようとされている方に一つ知っておいて頂きたい事があります。意外と知られていないのですが、小動物をちゃんと診察することが出来る獣医さんは、はっきり言ってかなり少ないです。
もちろん、通常どこの獣医さんでも診察はしてもらえるので、軽い症状であればさほど問題ありません。しかし、犬猫では発症しない特有の病気になった時には、特別な専門知識がないと治療が難しい場合も多いようです。
そのため、病気になって慌てて近くで診てもらえる獣医さんを探したが見つけられず、しかたなく犬・猫専門の病院に連れて行き、間違った治療を受けたために、治らなかったり、手遅れになったという声も実際にあるのです。
あらかじめ小動物に対しての専門知識を持った近くの獣医さんを、知人に聞いておいたり、情報誌・ネットなどで下調べをしておいて、いざという時に慌てず済むように備えておいて下さい。

うさぎをはじめ、げっ歯目のハムスター・モルモット・チンチラ・プレーリーの歯は一生伸び続けます。そのため、牧草や繊維質の多く含まれる食餌を食べる事で咀嚼回数を増やし、歯を適度な長さに磨耗させる必要があります。正常な場合、上下の歯は一定の長さに保たれて、きっちり合わさっています。

しかしペットとして飼われ、繊維質の少ないペレットや、やわらかい食餌、おやつ類中心の食生活をとることで、歯が削れなくなったり、ねじれて生える事が非常に多くなってきています。そうした食餌ばかり与えていると、糞の状態も軟便や下痢に近い症状になる事があります。その他の原因としては、突然の事故などで上下の歯がずれたり、生まれつき噛み合わせが悪い場合にも、どんどん歯が伸びてしまいます。
症状としては、口外に歯がはみだし酷くなれば歯茎に刺さったり、口の中を傷つけたり、口がちゃんと閉じないため、よだれを垂らすようになる事もあります。また、痛みから食欲低下を招き、餌が食べられなくなったりもします。体の小さな小動物にとって、たとえ1日や2日であっても絶食することは命取りになりかねません。
定期的に歯のチェックをし、もし噛みあわせがおかしくなっていれば、速やかに、獣医さんに連れて行き歯をカットするか削ってもらいましょう。飼い主さんご自身でニッパーなどで切ったり、やすりで削ったりする方もいるようですが、歯が縦に割れるなどの事故が起こりやすいため、あまりお勧めできません。控えた方が無難です。
予防策として、普段から牧草や繊維質の多い野菜など、なるべく咀嚼回数が多くなる食べ物をあげることで、歯が磨耗しやすいようにしてあげて下さい。また、繊維質を多く与える事で、軟便も予防できます。
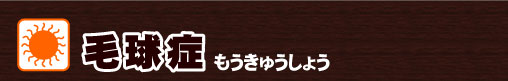
うさぎなどは毛繕いした時の毛を飲み込んでしまいます。

そして一度飲み込んだものを嘔吐する事が出来ないために、胃や腸の中で毛が蓄積され、毛球が出来てしまいます。
普段から正しい餌を食べいて健康な状態であれば、糞と一緒に排出されるので特に問題は無いのですが、繊維の少ないフードばかりを与えていると胃腸の働きが鈍くなり毛球症にかかりやすくなります。
もともと自然界の小動物は、繊維質の多い硬い食物などを何時も食べていたため、飲み込んだ毛を糞と一緒に効率よく排泄していました。ペット化された現在より胃腸の働き自体も丈夫で活発だったそうです。
しかしペット化されたうさぎなどの小動物は、飼い主にとって便利なペレットやオヤツ類など、消化の良い物を多く食べるようになった事により、もともと丈夫に出来ていた胃腸の働きが減退していったのです。
そのため、本来必要とされないはずの、売られている様々なサプリメントの力を借りて糞と一緒に排出する必要性が出てきたという事に繋がるのです。
毛球症の初期症状は糞が不揃いになることや、小さくなる程度なのですが、ほっておくと糞が出なくなり餌をあまり食べなくなって死に至る事もあります。
さらには、毛球がつまって腸閉塞を起こし急死することもある怖い病気です。
この病気は先ず、毛球を取り除く(溶かす)薬や胃腸の働きを活発にする薬を与えてください。
治らない場合は病院で手術をする事になりますが、うさぎなどの手術は、かなりのリスクが伴う事をお忘れになられないで下さい。
やはり、普段から牧草や繊維質の多い野菜類などの食生活にする事はもとより、まめなブラッシングなどで予防をしていく事が重要ですね。
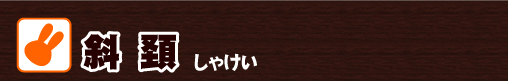
細菌感染した脳神経の障害が原因であったり、外耳炎・内耳炎等の原因で首が傾き、真っすぐ歩けなくなります。酷くなると同じ所をクルクル回るようになります。

高い所から落として脳神経に異常をきたしたり、パスツレラ菌に感染したことによっても発症するので、ケージ・トイレなどを清潔に保つように衛生面の注意も心がけて下さい。
症状は見た目にもわかり易いので、少しでもおかしいと思ったら直ぐに獣医さんに連れて行き、抗生物質投与などの治療をする事で、完治の確率は高くなります。

別名ソアホックといい、何らかの原因で足底の毛がはげ、赤く炎症を起こす病気です。
うさぎの足裏は、肉球がなく毛で覆われています。スタンピングや生まれつき足裏の毛が薄い事や、ケージの底網に毛が挟まって抜けて傷がつく事が原因の多くです。
酷くなると傷口が化膿し、夏場など暑い時期に気付くのが遅れるとあっという間に腐って手遅れになったという話も実際にあります。

普段部屋で放し飼いの場合は、特にフローリング床や硬いゴムマット状の床も良くありません。
爪が引っ掛からないカーペットなど滑りにくく、軟らかくクッション性のある物を敷き詰めたり、ケージの底にスノコを敷く事など、うさぎが普段歩き回るエリアには、とにかく足裏にやさしい物を敷いておく事で予防ができます。
毛が抜けた部分は赤く見えますが、よく観察して軽い症状であれば消毒液を塗り、その後、軟膏やグルーミングスプレーをやさしくマッサージするようにすり込んで下さい。なかなか治りにくい場合は、獣医さんに連れて行き抗生物質入りの薬を処方して貰って下さい。
普段からブラッシングや爪きりの時には足底をよくチェックするようにして下さい。特にかかとの周辺がなり易いです。

パスツレラ菌という細菌により、くしゃみ・鼻水が出るなど風邪に良く似た症状です。酷くなると、肺炎や結膜炎、まれに内耳炎を起こし斜頚になる事もあります。健康なうさぎもパスツレラ菌を持っている事がありますが、全て発病するものではありません。
原因としては、急激な室温や環境の変化などをはじめとした様々な原因でストレスを感じ、体力低下を招いて細菌感染し、発病する事が多いです。
治療は抗生物質(バイトリル・クロマイ)などを病院で処方してもらいましょう。なかなか直ぐには治りにくいですが、気長に治療して下さい。
元気が無いときは、ストレスを掛けないように出来るだけそっとしておいて、生野菜・穀物類・アルファルファなど、栄養価の高い物や好きなおやつ類を多く与えて、体力回復に繋がるように努めてあげて下さい。
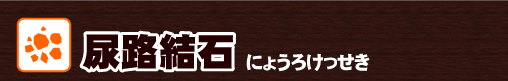
慢性的な水分不足や、カルシュウムの取り過ぎなどから、尿道に結石(小石状の塊)が出来て、尿道が詰まったり傷つけたりする病気です。

うさぎをはじめ草食動物は、尿からカルシウムをたくさん排出します。
そのため、他の動物に比べて尿路結石の発症率が高い傾向にあります。
症状としては、痛みが非常に強いため、うずくまり、時々お腹のあたりが、痙攣のように震えます。
本当に痛くて辛そうですよ!
酷くなると黒っぽい血尿がでたり、尿道を結石が完全に塞ぎ尿をする仕草はしても全く出なくなる事もあります。このようになる前に、早めに気付いてあげて大至急獣医さんに連れて行ってあげて下さいね!
予防策として、普段から水は何時でも飲める状態にしておく事と、7ヶ月以上の大人になったら、ペレットや牧草に含まれる成分に気をつけて、カルシュウムの少ない食餌にし、牧草はチモシーなどのイネ科を与えて下さい。

水分の取りすぎや環境の変化でストレスを感じてしまうと、胃腸の弱い子は下痢になりやすいようです。またケージやトイレを不衛生にしていると菌に感染してなる事もあるので、普段から飼育環境をこまめに掃除をし、清潔にする事を心掛けて下さい。
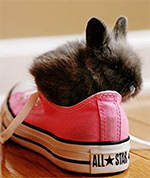
うさぎをはじめ草食動物は、尿からカルシウムをたくさん排出します。
水分の摂り過ぎで起こった下痢であれば、比較的簡単に治る事が多いのですが、やっかいなのは、コクシジウム・クロストリジンム・大腸菌・腸性毒症などの細菌やウイルスからくる腸炎です。
この場合はたいてい水溶性の下痢であり一刻を争うものです。速やかに新しい糞を持参して獣医さんに連れて行きましょう。
また、子うさぎは腸内の細菌数が不安定なため大人うさぎと比べて下痢になりやすいようです。下痢になるとかなりの重症になることが多く、あっけなく死んでしまうこともあるので、特に気を付けてあげて下さい。
普段グルーミングの時に、お尻が糞で汚れていないか、糞の形は正常かなど、チェックを怠らないようにしましょう。
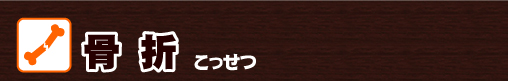
そもそも、うさぎを始め多くの草食動物は、野生の中で生きていくために、攻撃力の無さを逃げることや隠れることで命を守ってきました。
なかでもうさぎは、全速力で走りだすと、あの小さな体からは想像できないくらいに逃げ足が速いです!
そのため、体の形状はスポーツカーのように軽量化され、ちょっとした事で骨が折れてしまいますので、特に気を付けてあげて下さいね!
だっこして下に落としたり、暴れた時に強く抑えすぎたり、ビックリして逃げた拍子に壁にぶつかったりして骨折する事が多いようです。
症状は足を引きずる・足を着かずに歩く・全く歩かなくなるなどです。

骨折は基本的にほっといて治るということは、考えられません。
なぜなら人間のように、折れた箇所をかばって動かさないようにするといった意識があまりないため、よほどの痛みがあれば動かさないのですが、痛みがあまり無いと、完全に治っていなくても動かしてしまうため、治りにくいという事があるようです。
ですからおかしいと思ったら、早いうちに獣医さんに連れて行き適切な処置をして貰って下さい。
因みに脊髄骨折の場合は人間同様に、体の硬直・運動麻痺が起こり病院で治療しても完全には治らない場合もあります。

栄養状態の偏り、飼育環境が不衛生な事が原因して、体力低下を招いたときに感染しやすくなる皮膚病です。
カビが皮膚に感染することで、頭部・耳・四肢などに発症し、体中の毛が抜けたり、皮膚がカサカサになって、フケのような物が出てきます。
程度にもよりますが、それほど酷くなければグルーミングスプレーをかけて、皮膚を傷つけないようにやさしくブラッシングし、皮膚の表面をきれいにしておきましょう。 そのあとペットショップで売られている専用の軟膏を塗っておき様子を見て下さい。

治りにくい場合や酷い場合は、獣医さんに連れて行き、抗生物質などの治療をしてもらって下さい。
予防策は、餌・おやつを見直し、栄養バランスの良い物に換えることや、普段から、ケージ中や飼育環境全体をこまめに掃除して衛生的にしておきましょう。

さまざまな外敵要因で、出来た小さな傷口から細菌が入った事により発症し、白っぽい乳液状の膿が溜まります。

皮下だけでなく歯茎・肺・お腹の中などに出来ると発見しにくく手遅れになるケースが非常に多いようです。 酷くなると皮膚が腐ったり、骨が溶ける怖い病気です。
初期症状としては、じっとしていることが多くなり、食欲低下をおこします。このような状態が少しでも見受けられたら、直ちに獣医さんに連れて行き、抗生物質の投与など、適切な処置をすれば完治の確率は高いようです。
普段から飼育環境の場面において、怪我を招く原因となりうる要素を色々考えて、取り除いてあげる努力や工夫をして下さい。
ケージの底網などがささくれだっていて、足底の皮膚を傷つけたりする事も多いようですよ。一度飼い主様の手でさわってチェックしてみましょう。

慢性の下痢・水のみボトルの漏れ・尿・涙・よだれなどが皮膚を濡らしていたり、湿らせている事が普段よくあれば要注意です!
草食小動物の体毛は、非常にきめ細かく密集して生えているため、一度濡れるとなかなか乾きにくくなっています。これは、良い気候を探し求めて移動しながら生息していく動物と違い、一生を同じ地域で過ごすため、大自然の寒い冬に体温を奪われないようにするためのものです。
症状としては、湿った環境を好む細菌が皮膚に繁殖して、毛が抜けたりカサブタができたり、時にはカビが繁殖して毛が緑色っぽく変色することもあります。

極端に湿度の高い環境は避け、普段からこまめなチェックをして下さい。また定期的に日光浴をさせることで皮膚が清潔に保て、消毒にもなり、細菌が繁殖しにくい皮膚環境を作り上げることができます。
もし、体毛が湿っていたり濡れているようなら、ドライヤーで乾かしてあげて下さい。その際、風が近すぎて熱くなりすぎないように、遠目の風でゆっくり乾かしてあげて下さい。
タオルで拭きながらドライヤーを当てると早く乾きますよ!
軽い症状の場合はペットショップで売られている専用の軟膏を塗ることで治ると思いますが、症状が進んでいる場合は抗生物質の投与が必要な場合もあるため、早めに獣医さんで診察してもらう事をお勧めします。
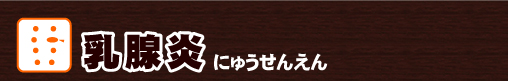
不衛生にしている事などで細菌が繁殖し、乳頭から透明ぽい分泌液がでてきたり、乳頭が硬く腫れ上がったり、黒く変色することもあるようです。
酷くなると発熱し、食欲が無くなることにより、著しい体力低下を招きます。そのため、色々な病気を併発したり手遅れになるケースもある怖い病気です。安易に考えずに早めに獣医さんに連れて行き診てもらいましょう。
卵巣子宮を摘出手術することで予防でき、発症率はほぼゼロになります。
また、飼育環境を清潔にする事である程度の予防は出来ます。
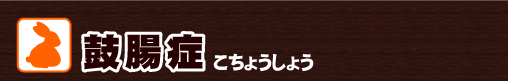
症状として胃腸にガスが溜まりお腹が張った事によって、ある日突然食欲が無くなったり、餌を食べた後うずくまって動かなくなることです。

ほおっておいて酷くなると死に至る事もある、一刻を争う怖い病気です。
少しでもこういった状態であれば、速やかに獣医さんに連れて行きましょう。
原因としては幾つか考えられますが、一番多い原因としてアルファルファ・クローバー・サツマイモ・新芽の豆科植物など、醗酵し易い餌を多くとり過ぎている事が考えられます。
こういった食餌は、嗜好性が高い(おいしい)ため、たくさん欲しがります。そのためついつい多く与えてしまいがちですが、これが良くないのです。
あくまでもオヤツと捉え、元気が無いときや、何かのご褒美として与える程度に抑えてください。
予防として、普段から牧草や野菜類の中でも、特に繊維質の高い餌を多く与えることで、整腸作用が活発化し、強い胃腸が作られ発症しにくくなります。
また胃腸の弱い子は餌の後、一日1回〜2回、オヤツ代わりに市販の乳酸菌などのサプリメントを与えるのも良いでしょう。※ただし、これも与えすぎないように気を付けて下さい。
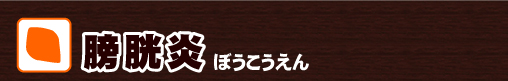
うさぎなどの尿は濁っているのが普通であり、ちょうど乳酸菌飲料のような色をしています。これはカルシウムなどの栄養素が尿に溶け出しているためのものであり、正常な状態ですので心配する必要はありません。
たまに黄・赤・茶色っぽい色に変色することもありますが、これも食べ物の色素が尿に溶け出して変色しているだけなので、特に心配は要りません。

しかし、不衛生にしている事などが原因で、膀胱が細菌感染する事により発症した場合は、頻尿・血尿、時には膿尿(ドロっとした乳液状)など、尿の状態が普段と明らかに違ってきます。
膀胱炎に一旦かかると、ほおっておいて治ることはまずないので、速やかに獣医さんに連れて行き治療してもらいましょう。
飼い主様が、尿のチェックを毎日していれば、比較的簡単に異常を発見できるのですが、トイレ砂や敷藁の上で尿をした場合は、染み込んでしまうため、時間がたつと判りにくくなります。
そのため、酷くなるまで気付かない事があるようです。
普段から飼育環境を清潔に保ち、新鮮な水を与えるようにして下さい。そして注意深く、尿の回数・色・状態をじっくり観察するようにして下さい。