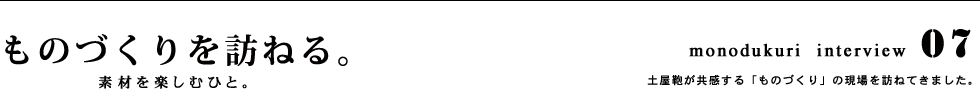

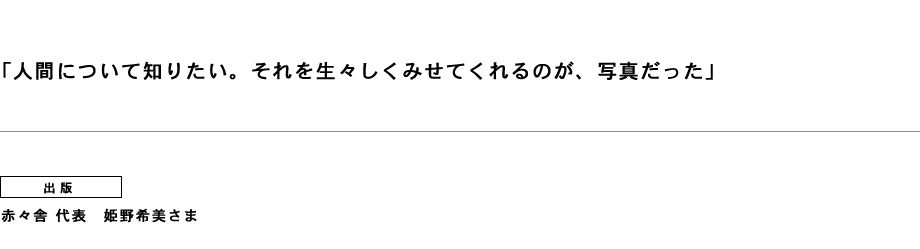
自分の部屋に、写真集が何冊くらいあるだろうか。
写真集を購入するという行為は、すこし非日常的なことかもしれない。
市場規模からしても、文庫本や雑誌を買うような頻度で写真集を購入するひとは少ないだろうし、なかなか高価だったりすると、ハードルがぐっとあがる。
取材に訪れたのは、東京・六本木駅からすこし歩いたところにある、緑に覆われた事務所。写真集をメインに出版する赤々舎だ。
代表の姫野希美さんのお話は、取材よりずいぶん前に別の機会でお聴きしたことがあった。その際に、落ち着いた空気をまといながらも、なんともいえない圧倒的なエネルギーを感じた。姫野さんの源になにがあって、こんなに写真集と向かい合ういまの姫野さんをつくりあげているのか知りたい。もっとお話をうかがってみたい、という想いを引き起こさせた。

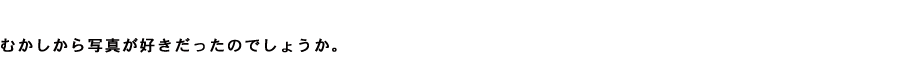
「とくに写真との接点というのはなかったですね。むしろ、父親がもっていた世界の名画全集や日本の仏像とか、そういったシリーズ本をみるのがものすごい好きでした。そこにもちろん写真は介在するわけなんですけれども、格別写真を意識するということはまるでなかったんですよ」
もしかしたら学生のころから写真に興味があり、撮影経験も豊富なのでは、という勝手なイメージは大きくはずれていた。
「私は、カメラをもっていないんですよ。自分でシャッターを押したという経験が、人生のなかでたぶん数回くらいしかなくて」と姫野さんは言う。
「だんだんと、世の中のひとが言ういわゆる“うまい”技術があろうというのは、わかってきた。でも、私にはあまり関係ないというか、大事なのはそこではない。技術がなくても、いい写真はあるだろうと確信していて」

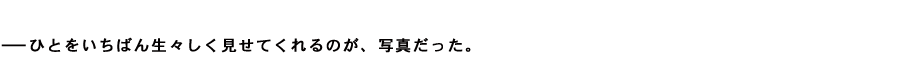
写真集という、なかなか爆発的な売上にはつながらない本を手がけることについて、「私、もしかしたら自虐的なのかしら」なんて思ったこともあるという。経済行為からすると、まだ志半ば。作家にとっても、もっと写真集が売れるようにならないと、という想いがある。もちろん社会的な責任感や使命感は多少はあるけれど、それだけでは続けられない。
写真集を出版する。
姫野さんの写真集に向かう力の根底には、なにがあるのか。
「私はたぶん、自分の欲求として人間について知りたいというか、みんなそうなんじゃないかと思うんですけどね。ひとはやっぱりひとに興味がある。“生(せい)”の不可解さも含めて、そこを知りたい。その欲求が原動力」
それをいちばん生々しく見せてくれるのが、写真だった。
「ひとはどういう存在で、人間は何をつくりだすことができるのかすごく興味があって。だから、本をつくるという“凝縮して表す”ということをやっている。いちばん生々しさをたたえた表現形態であった。いやおうなく、生理的に反応してしまうところがあったと思うんですよね」


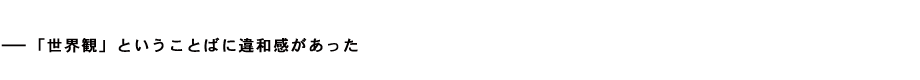
“世界”と“世界観”。このふたつは似ているようで、ぜんぜん別物だ。
「すこし前に、世界観ということばが若い写真家の間でよくやりとりされていたことがあったんですけど、そのときからすこし違和感があって。便利なことばなんですけどね」
自分の見方や見え方、あるいは自分のとらえる範囲のことをあらわす“世界観”。姫野さんは、やはりこのことばはあまり好きじゃなかった、と教えてくれた。
「自分の価値観とか見え方、美意識で自分の“世界観”をつくるのではなくて、むしろ写真にとって大事なのは、そういうものが届かない、全部の言語が届かない自分が把握できないもののほうだと思うんですよね。それが、“世界”なんじゃないかって」
写真が関わるべきなのは、“世界”。
大事なのは、わけのわからない混沌としているそのものに、やりとりしていくエネルギー。そのやりとりがないと、写真のなかに“生”の時間が流れない。
写真家本人に宿っている生命力、親密に関わる力、シャッターを押すときの衝動。
「シャッターを押すとき、その指にはそのひとが生きてきた時間が流れていて、そこには思考があるかもしれないし、いろんな考えすべてが入っているんだろうな、と思うんですよね。そこからはからずも感じる厚みというか、そのひとの背骨みたいなものっていうのは、非常に迫ってくるものがあります」



写真集をつくる一連の流れで、姫野さんがいちばん大事な瞬間だと思うところは、「一対一で向かって話すとき」だという。
できるだけ透明な感じになって、そのひとや写真のことをできるだけ深くみたい。「透明な感じ」という表現は、姫野さんとことばを交わすとじんわりとわかる。なにもない透明ではなくて、包み込まれるような透明。
「自分のことを、穴みたいって思うことがあるんです。どう考えても突起しているというよりは、中が空っぽの穴。空洞というか。それが、私のあり方としてはとても大事だと思っています」
そこを通りかかったひとは、ゴミを捨てたりのぞき込んだりするかもしれない。なかには、自分の秘密や何かをささやいたり、こぼしていくかもしれない。雨が降ったら、水たまりになるかもしれない。穴だから、いくらでも入る。
一対一で向かいあう始まりは大事だから、はじめて会ったときに、できるだけ穴として透明に向かいあえるようにしたい。


姫野さんにとって「はじめて写真の場にふれたかも」という、いまの根っこになる部分をつくってくれた作品集がある。彫刻家・舟越 桂さんの作品集だ。
彫刻作品ではなかなかめずらしい「撮りおろし」の作品集をつくろうと、舟越さんに手紙を書くことからはじまった。
素朴に考えたら、彫刻っていうのは立体だから、私は普段彫刻をみるときに前からもうしろからもみるし、あるいは近寄って目の表情をみたりとかディテールをみる。そういうふうに写真にとりたいって思ったの。そうすると、彫刻の存在感が体感される本になるんじゃないかって。
「当時、ポジとネガも知らなかったの。白いホリゾントも知らなくて、土足で歩いてしまったり。いろいろすべて知らなかったんだけど、そういうのはあとからでもなんとでもなります」
彫刻の梱包が大変だったことや、撮影には毎回舟越さんがいらしていたこと、当時を思い出すように語られる。
「撮影現場では、このようなアングルで撮りますって、ファインダをのぞかせてくれた。それをみて“もうちょっと左でもいいんじゃないか”って言ったり。そういうことって素人でもできることなんですよね。正直に自分の感じたことっていうのは言っていけるし、的外れでもはずかしいことではないんです」
最近、舟越さんの講演での話がとても印象に残っているという。
「舟越さんがひとにとって大事だと思うもののなかのひとつに、本があったんです。“人間がつくりだした、もっとも美しいものだと思ってる”ということばにすごい感動して。やはりひとの存在が許されるべきものというか、すごくうれしかったんです」


「そのひとの写真にとってなにか、こう“ターニングポイント”だったりそういう節目に立ち会うことができたら、やっぱり幸せだなっていう気持ちはあります。特に若い方の場合、それがデビュー作になる可能性がすごい高いから、おもしろさというか喜びがありますよね」
姫野さんは、これまで自分から写真家を探して出版につなげたということがあまりないという。出会うべきときに、出会うものなのかもしれない。
「これからはもうちょっと、なにか雑誌などで作品の一部を拝見して“あっ”と思ったときや、見ていいなって思ったものについて、できるだけ関わっていきたいという想いがあります」
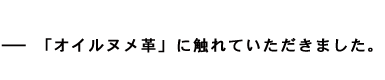
姫野さんに、ご自身がお使いの身近な革製品はなにかをお聞きしたところ、革のバッグやカード入れ、お財布というこたえが返ってきた。
「革は、ひとの手で触れると変化していくものってすごく思っていて、そこが魅力だなって思ってたんですよね。小物になった状態でしか見たことがなかったので、こういう大きな革の状態で見ると、びっくりします。けっこう重いですね。すごく強さを感じます」
赤々舎
東京都港区西麻布1-9-13
TEL 03-6434-0636
url. http://www.akaaka.com/
2012年7月に取材










