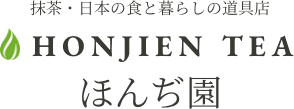はじめに

日本の伝統文化である「茶道」ですが、近年では現代の暮らしに馴染むデザインの茶道具がたくさん生まれています。
その中でも今回は、発売開始以来ご好評をいただいている、通常の茶筅より柄の部分が長く作られている「マドラー茶筅」についてご紹介致します。マドラー茶筅と通常茶筅の違い、使用感や泡立ち感など、徹底解剖しました!また、抹茶と茶筅の間で切り離せない抹茶の「泡立ち」についても解説しています。
ぜひ今回の記事で「マドラー茶筅」が気になった方は商品ページも覗いてみてくださいね。
第1章《 茶筅の種類 》

茶筅は茶道具の中でも特に、抹茶の味わいを左右する重要なお道具です。種類は様々ですが、一般的には上記画像のように穂先の数によって区別します。
当サイトでもよくご質問いただく、茶筅の穂先が違うと、どう違うの?何が違うの?どう選べばいいんだろう?という茶道ビギナーなお客様からの問い合わせ。
穂先が多くなるとどうなるのかというと、同じように点てたとしてもより泡立ちがよく、慣れていなくてお茶を点てやすくなります。
さらに、「穂先が多い = たくさん竹を割く必要がある = 太目の竹を使用する必要がある」。その為穂先の数字が大きくなればなるほど、持ち手部分が太くなり若干持ちにくさを感じます。

次に、通常の茶筅とは異なる形状の”変わり種”茶筌をご紹介します。
(画像左から)
・翠華園 泡点つ茶筌 …翠華園さんオリジナルの泡が点ちやすい形状の茶筅
・マドラー茶筅 …柄の部分が長く穂先が小さい形状の茶筅/中国製
・竹茗堂 マドラー型茶筌 …竹茗堂さんの柄の部分が長い茶筅/日本製(奈良高山)
・翠華園 茶筌-En- …翠華園さんの通常サイズ茶筅/サイズ目安は数穂(70本立)程度
上記にように、現代の暮らしに合わせた設計のお道具も数多く作られています。これも茶道具という長い歴史をたどった茶の湯文化ならではの変化と言えるでしょう。「伝統文化をそのまま体験」も、とっても素敵ですが、やはり現代の暮らしになかなかフィットしない・特別感がでてしまう、というのがリアルな悩み。素晴らしい文化はそのままに、少しだけ現代の暮らしに合わせて改良を加える、そんなメーカー様たちの試行錯誤が伺えます。
また、「泡立ち」にこだわったお道具も開発されているのにも注目。抹茶といえば、よく見る茶筅でシャカシャカ。そもそも、なぜ抹茶は泡がたつのだろう?また、なぜ泡立てるの?次章では「抹茶の泡」について解説致します!
第2章《 抹茶の泡立ち/流派による違い 》

まず、抹茶が泡立つ理由。それは抹茶に含まれる「サポニン」という成分のおかげ。大豆などのマメ科の植物のほか、ゴボウや高麗人参、お茶などに含まれている成分で、石鹸のように安定した泡を作り出します作用があります。
この効果からラテン語で石鹸を意味する「サポ」が名前の由来となっています。また、このサポニンには強い苦みとエグみがあり、抹茶の他にコーヒーにも含まれています。
抹茶に含まれるその他成分は?→《 良い抹茶とは?#抹茶の健康効果 》こちらから
そしてなぜ泡立てるのかというと、お湯と抹茶を十分に混ぜ合わせ美味しくいただく為!はい、とってもシンプルです!笑。
抹茶は茶葉を細かくすりつぶしてできているので、水には完全に溶け切りません。またとても粒子が細かい為、インスタントコーヒーのように抹茶にトポトポとお湯だけ入れてスプーンでまぜまぜ〜なんてしても抹茶が混ざりきらずダマダマで美味しくないのですね。(ココア粉をイメージしていただければわかりやすいかと思います)その為、いただく直前に(重要!)茶筅で泡立てるわけですね。

さらに、この抹茶の泡立ちですが、実は流派によってお作法が分かれており、あまり泡を立てないことを良しとしている流派もあります。
ここで少し寄り道小話。茶道の流派は主に3つに分かれており、「表千家」「裏千家」「武者小路千家」といいます。
=== 茶道の豆知識 ===
「三千家(さんせんけ)」とは?
◎鎌倉時代中国から伝わった抹茶ですが、様々な流派が生まれ500以上の流派が存在すると言われています。その中でも最もメジャーなのが「裏千家」「表千家」「武者小路千家」。その3つを合わせて「三千家」と呼びます。なぜメジャーなのかというと、千利休(せんのりきゅう)の孫である千宗旦(せんのそうたん)の子どもたちが作った、千利休から続く流派だからです。
◎「表千家(おもてせんけ)」…三千家の中でいわゆる「本家」に当たります。よって、現在も保守的で伝統を重んじる流派で、道具や作法は質素です。
◎「裏千家(うらせんけ)」…いわゆる「分家」である裏千家は、伝統を重んじながらも新しいスタイルを取り入れ、現在は最も多い弟子数となっている流派です。
◎「武者小路千家(むしゃのこうじせんけ)」…三千家の中で、規模は比較的小さい武者小路千家。茶室や所作の、無駄のない合理性が特徴です。
使うお道具やお点前の仕方・作法など違いはありますが、対立してるわけではなく、どの流派も千利休の大成したわび茶の精神や茶を点てて客人をもてなす心を変わらず引き継いでいます。
この中でも
・表千家、武者小路千家は泡を立てない流派
・裏千家は泡立てる流派
です。下の画像をご参考下さい。よく抹茶としてイメージされがちなのは右の「裏千家」の方ではないでしょうか。

=== 茶道の豆知識 ===
流派別抹茶の点て方
◎「裏千家(画像右)」…手首のスナップを聞かせて茶筅をよく振り、キメ細かい泡がふっくらと覆うように点て、最後は「の」の字を書いて茶筅を抜き、真ん中が盛り上がるようにします。裏千家ではキメの細かいカプチーノのようなふわふわの泡が良いとされています。
◎「表千家(画像左)」…手首だけでなく腕全体を動かすようにお茶を点て、適度に泡立てたら、泡の無い部分が半月状に残るように茶筅を引き上げます。表千家では部分的に泡のない部分が望ましく、三日月のようにあえて残すことを「景色」と呼びます。武者小路千家では全く泡がないことが望ましいとされています。
(※筆者もあまり茶道に精通していないので、もし間違ってたらぜひお知らせください…汗。画像はフリー画像をお借りしました!)
上記のように流派によって点て方が異なる理由・発祥については残念ながら調べきれませんでした。ご存じの方がいらしたらぜひ教えてください!笑
(個人的な意見としては、裏千家の方が柔軟性があり新しいスタイルを取り入れるという特徴があるので、ちょっとハイカラな雰囲気のするクリーミー感が時代の流れと共に浸透していったのかな?と想像したりしました。)
流儀による違いは上記のようになりますが、抹茶を味わうという観点からみると点て方によって下記のように変わってきます。
泡多め(裏千家流)…
泡を立てることで口当たりをまろやかにする効果があります。 また、抹茶自体に雑味があるので、泡に雑味を逃がしているとも言われています。
泡少な目(表千家・武者小路千家流)…
あまり泡立てないことで雑味を出さないようにしているそうです。 その為、泡立てた時とくらべて苦みを感じつつもすっきりと抹茶本来の味を感じられます。
流儀による点て方の違いはあるものの、個人的に楽しむならば好みに合わせてどちらのやり方でも全然OKです。使用する抹茶によっても味は随分変わってきますので、ぜひ抹茶の味比べ・点て方比べをしながらあなただけの最高の一服を極めてみてくださいね。 ではでは、次章では本題の茶筅の道具比べを検証してみます!
第3章《 茶筌使ってみた!》
さて、では最初の章でご紹介した「変わり種」茶筅。これらを実際に使ってみて泡立ちや使いやすさなど比較していこうと思います。今回比較する茶筅はこちら。
・翠華園 泡点つ茶筌
・マドラー茶筅(中国製)
・竹茗堂 マドラー型茶筌
・翠華園 茶筌-En-
▼ まずは、大きさ比較。手に持ったサイズ感は下画像のようになります。

柄の長さを通常タイプを標準として、マドラー系のものは長め、「泡点つ茶筌」はその中間という感じです。
また穂先も「泡点つ茶筌」は通常タイプより長めな作りになっています。
マドラー茶筅の穂先も違いがあり、「マドラー茶筅(中国製)」のものはすっきりと小さ目、「竹茗堂 マドラー茶筅」は少し広がり気味でボリュームのあるつくりになっています。
▼ 次に抹茶碗に入れた時はこんな感じになります。

「泡点つ茶筌」の柄の長さと細さがよくわかりますね。
▼では、抹茶を泡立ててみます。

▼茶筅縁-En-(通常タイプ)

▼泡点つ茶筌

うーん…(-_-;) 私の点て方でしょうか…あまり違いがなくて申し訳ございません…。
そして一応裏千家流のふわふわのキメ細やかな泡を目指したのですが…。このようにぶくぶくと”泡立っている”状態は、あまりいいものではありません…汗。
出来栄えについては、見ての通りなのですが(土下座)点てている時の感想としては、”泡点つ茶筌”はあまり力をいれずにふることができたなと感じました。以前当店スタッフでこれらの茶筅を使って比較会をした時に、お茶をあまり点てたことのないスタッフさんはこの「泡点つ茶筌」が使いやすいと仰っていました。
茶筅であのキメ細かい泡を立てるためには、お菓子作りの泡だて器のようにぐるぐると円をかくように混ぜるのではなく、肘から下は固定し、手首のスナップをきかせて茶碗の中で「N」を書くように素早く”縦”にふるのが重要です。
それが、割と慣れていない方は難しかったりするのですが、「泡点つ茶筌」ならば、手首のスナップをあまり気にせず振ってもそれなりに泡立つなと感じました。最初見た時お料理に使う泡だて器の形状に似ているなぁと思ったのですが、絶妙なこのサイズ感が茶碗の中で振るのに最適なのだと思います。
「N」書き点てをする必要はありますが、お作法は気にせず気軽に抹茶を楽しむカジュアル抹茶点てにはぴったりのお道具ではないでしょうか。
▼マドラー茶筅でも実践。通常はマグカップでの使用を想定されていますが、比較の為同じ抹茶碗にて行います。

▼マドラー茶筅(中国製)

▼竹茗堂 マドラー型茶筌
※茶筅を横に並べた画像を撮影し忘れておりました…。申し訳ございません。(土下座2)

やはり、穂先が小さい分、通常タイプのものほど泡立ちませんでした。
通常、茶筅を茶碗の中で振るとき、結構茶碗の底に押し付ける感じでシャカシャカするのですが、マドラータイプだとそれもできないので、やはり抹茶碗には、通常タイプの茶筅がベストだなと思いました!
ですが、抹茶のダマ残りなどもなくお湯とのきちんと混ざりあっていました。後でご紹介しますが、よく茶筅の代用として使われるドレッシングなどを混ぜる時に使うミニ泡だて器(100円ショップなどにもありますね!)や、ミルクフォーマー。ミルクフォーマーはそこそこ泡立ちますが、ミニ泡だて器は結構ダマが残ってきちんと混ざりきっていなかったりします。
▼次に、マドラー茶筅をマグカップでも使用してみました。

▼マドラー茶筅(中国製)

あ、泡が消滅してしまいました…!汗汗
マドラー系の茶筅は総じて泡立ちにくいように感じました。ですが、抹茶とお湯の攪拌具合が普通に混ぜるより断然良いので抹茶が美味しくいただけると思います。表千家流の点て方のように、あえて泡立てず抹茶のすっきりとした味わいを楽しめます。
抹茶碗は持っていなくてできればお気に入りの手持ちのカップで抹茶を楽しみたい、という方には最適なのではないでしょうか。抹茶碗は取っ手がなく陶器を直に持つので、感じる人からすれば熱いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが(寒い時期にはそのほっこり感がよかったりもしますが)、マグカップなら取っ手があるのでその心配もいらないですよね。
▼《番外編》お家にあるもので抹茶点ててみた
お料理で使う「ミニ泡だて器」と、カフェラテのミルクを泡立てる機械「ミルクフォーマー」。ミルクフォーマーは機械による性能の違いもありますが、今回は自宅にあった電池で動く簡易的なもので試してみました。


表面にできる泡立ちと、混ざり具合の確認(ダマや沈殿物などがないか)。
ちょっと画像だとわかりにくいかもしれませんが…「ミニ泡だて器」はかなりダマが残ってしまっています。「ミルクフォーマー」は表面の泡立ちが若干粗いですが、沈殿物やダマ残りも少なく、きちんと混ざっていました。
第4章《 まとめ 》
では、今回のまとめは以下になります!
● 抹茶の泡立ちは「サポニン」という成分によるもの
● 抹茶の泡には雑味を苦し、口当たりをマイルドにする効果がある
● 抹茶の泡は流派によって捉え方が異なる
● 抹茶を泡立てる為には…
→ 竹製の茶筅を使うとダマなく抹茶とお湯がよく混ざる
→ 抹茶碗には通常タイプ(柄が短く穂先が大きいもの)の茶筅が最適
→ 茶筅に慣れていない方は「泡点つ茶筌」がおすすめ
→ マグカップを使用する場合「マドラー系」がおすすめ

抹茶の泡がもたらす味の変化や道具による違いは上記のようになりますが、個人的に思う抹茶を茶筅で点てることのもうひとつの意味合いとして、日本の伝統文化を体験する、という心理的効果もあるかなと思います。
またはお茶を点てることによるリラックス効果であったり、ゆったりと手間暇かけて一服いただくというその時間が日々の中で癒しになったりしますよね。
マドラー茶筅から随分脱線してしまいましたが、ぜひ、こちらの記事がお道具選び、お抹茶選びのご参考になれば嬉しいです!
最後までお読みいただきありがとうございました!ではでは!