「Walk Together」をテーマに、同じ悩みや目標を持つ楽天市場出店者同士の出会いを通じて、店舗運営に役立つ学びを得る「楽天新春カンファレンス2020」。私たちは企業や組織の中にある「わかりあえなさ」のために、さまざまな課題に直面します。実はその多くが「自分自身が問題の一部となっている」ということに気付くことで解決に向かうと説くのが、埼玉大学経済経営系大学院准教授である宇田川元一(うだがわ・もとかず)氏です。「対話」という手法を通じて、わかりあえないと思っていた相手の「ナラティブ」を読み解くというアプローチの有効性について、豊富な事例を元にお話しいただきました。
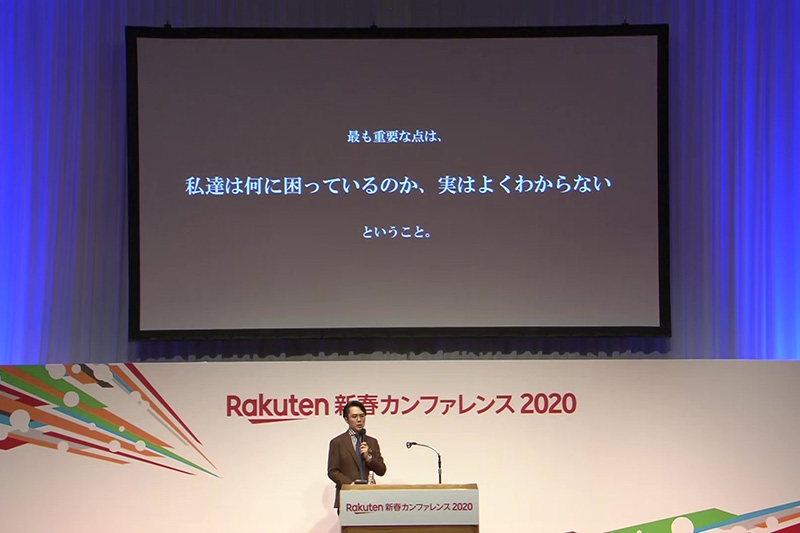
宇田川 元一 氏
1977年東京都生まれ。2006年早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、2007年長崎大学経済学部講師・准教授、2010年西南学院大学商学部准教授を経て、2016年より現職。専門は、経営戦略論、組織論。ナラティヴ・アプローチに基づいた経営変革、イノベーション推進、戦略開発を中心に研究を行っている。また、様々な企業のアドバイザー、メンターとして、その実践を支援している。2007年度経営学史学会賞(論文部門奨励賞)受賞。『他者と働くーー「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング)著者。
著書はこちら(楽天ブックス)
向き合うべき「本当の問題」から目を背けない。
先日、とある求人サービスで「経営戦略」と検索してみたら、「占い師」という仕事がヒットしました(笑)。それくらい、経営者の方は困っているということですよね。依存状態にあることからいかに回復していくかという問題は、アルコール依存や薬物依存の方たちだけの世界ではなく、「日常の中で孤立し、何とか自分で自分を助けようとして頑張っている方がたくさんいる」という問題に向き合うことそのものではないかと思います。
最も重要な点は、「私たちは何に困っているのか、実はよくわからない」ということです。何に困っていて、知識やノウハウを得ようとするのでしょうか。非常によく私が受ける相談に、「部下のモチベーションが低いのですが、どうしたらいいでしょうか?」というものがあります。モチベーションが低いことに困っているのでしょうか。よく聞いて紐解いてみると、「実は、仕事のプレッシャーが自分にかかっている」ということが背後にあったりします。だから、モチベーションの低い部下を見ていると過剰に心配になるんですね。依存症の話からわかるように、「我々は、表出している問題の背後にある『苦労』というものと向き合えず、何に困っているのかよくわからない」ということがあるわけです。
こうした実態と正面から向き合っている組織・集団が日本の中にあるだろうか? そう思って探したところ、これがあったんです。それが、北海道にある「べてるの家*1」という精神障害ケアコミュニティです。精神障害ケアと謳っていますが、この組織はビジネスをして自分たちでお金を稼いで生活をしています。ですから、彼らは自分たちのことを「企業」と呼んでいます。「べてるの家」の言葉に、「病気はあなたを助けにきている」「主観・反転・『非』常識」という言葉があります。「病気はあなたを助けにきている」という言葉の意味を説明します。例えば、ある統合失調症の当事者の方が自分の病気を研究したんです。これを当事者研究と言います。幻聴にもいろいろあって、罵るような言葉(ダメダメ幻聴)が聞こえて辛いという場合もあれば、「君、最近よくがんばっているね」というように褒めて励ますような幻聴(褒め褒め幻聴)の場合もあるそうです。ある方が、この「褒めてくれる幻聴(褒め褒め幻聴)」を増やしたいという研究を行いました。「どういう時に『ダメダメ幻聴』が増えて、どういう時に『褒め褒め幻聴』が増えるか」という研究をすると、一生懸命に人とのつながりをつくっている時は「褒め褒め幻聴」が増えて、人とのつながりが切れている時は「ダメダメ幻聴」が増えるということがわかってきたんですね。つまり、その人が困っていたのは、「幻聴が聞こえる」ことではなく、「孤立して寂しい」ということだったわけです。
でも、それを医師が治すのかと言うと、それは違いますよね。医師にとっては、良い幻聴も悪い幻聴も等しく幻聴であって、幻聴を治すためには薬を処方するしか基本的には手がありません。専門家が技術的に解決できることは非常に限られているわけです。「何に困っているのか」という点としっかり向き合い、「それだったら連絡してよ。寂しかったらいつでも言ってよ」という他者との関係が構築できれば、「褒め褒め幻聴」が増えるわけですね。逆に、薬で幻聴を抑えるというように、表に出ている問題をすぐに解決しようとすると、大事な人生の苦労に向き合えなくなるという問題があるわけです。我々は、ノウハウやハウツーといった解決策を探すことによって、向き合うべき苦労から目を背けていないか? 「べてるの家」から、そのことを学びました。
対話によって、「本当の問題の存在」を明らかにする。
『べてるの家の「当事者研究」』という本に書かれていますが、「べてるの家」でもう一つ面白いのが、「主観・反転・『非』常識」という考え方です。特に「反転」という考え方です。これはどういうことか。過食・嘔吐を伴う摂食障害の方の研究ですが、普通、摂食障害の方の場合は「過食・嘔吐を治そう」とするんですが、この方は過食・嘔吐に至ったプロセスを理解するために、「どうしたら、あなたも過食・嘔吐になれるか?」ということを研究したんです。つまり「反転」させたわけです。問題を解決するのではなく、問題がどのようなプロセスで生じたのかを紐解くために、問題をさらに悪化させたり、問題発生の再現性を持たせるために必要なことを考えたということです。すると、「常に親の顔色を気にしながら生活する」「人生にできるだけ高い目標を持つ」「決して弱音を吐かない」というような、過食・嘔吐に至った人生の物語が見えてきたと言います。つまり、ライフストーリーが紐解かれ、ある意味で、自分を助けるために病気になっていたということが見えてきました。でも、それがわかると、自分の中に自分を助けるもっといい方法を考えられるようにもなってきます。このように依存症や精神障害ケアの世界を研究することで、「実は何に困っているのか」という点が見えてくると、もっと良い「自分の助け方」や、組織をもっとよくする「糸口」がありそうだということが見えてきたんですね。こうした行動は「ナラティヴ・アプローチ」や「対話」と呼ばれる方法論においても行っていることです。
「対話」とは、向き合ってじっくり仲良くお話することではありません。これは現在開発中の方法で「2on2」と呼んでいるんですが、「一体、我々は何に困っているのか?」を掘り下げる対話をやってみました。例を挙げてご説明します。ある会社で新規事業に取り組まなくてはいけない部署のマネージャーが、メンバーの方向性が揃っていないため、非常に困っていました。「メンバーの方向性を揃えるにはどうしたらいいか?」という困りごとを解決したいと考え、対話の場に来ました。そこでメンバーも交えていろいろと話していくと、メンバーの口から出てきたのは「このチームの方向性がよくわからなくて困っている」ということでした。すると、そのマネージャーが「実はそうなんだよ。敢えて方向性をガチッと決めないようにしていたんだよ」と言うんですね。「なぜかというと、過去の自分の経験で、方向性がガチッと決まっているプロジェクトに途中から参加した時に、うまく馴染めなかったんですよね。だから、方向性をガチッと決めなかったんです」と。すると部下の人が言いました。「いや、実は私もそのことはなんとなくわかっていました。でも、そのことでマネージャーが困っているんじゃないかと思っていたんです」と言うわけです。
つまり、お互いになんとなく問題はわかっていたのに、忖度して言えなかったということですよね。私はその場で、「忖度して言えない『ソンタック』という妖怪が来てるんじゃないですか?」と言って、絵に描いてみました。どこかの会社の風邪薬っぽい見た目ですね(笑)。でも、これがなかなかよくて、地面の上に上半分の顔が出ていて、マネージャーの顔はニコニコ笑っています。メンバーはその笑った顔しか見ていないのでわからないんですが、地面の下に隠れたお腹の中では忖度をどんどん溜め込んで、ある時、それが爆発するんです。「では、『ソンタック』がどんな時に大きくなって、どんな時に小さくなるのか、生態を研究してみましょうか」というような提案をしたら、その問題が何の問題だったのかだんだん分かってきたし、マネージャー自身が「部下の方向性が揃っていない」という問題の一部であるということもわかってきました。表に見えている問題というのは、背後にあるより複雑で一筋縄では解決できない問題の存在を伝えてくれる重要なメッセージであるということなんですね。我々は、表に見えている問題をすぐに解決したいと思って、いろいろな方法を探します。ですが、もう一歩、対話的に掘り下げていくことによって、より良い道が見えてくるということがあるわけですね。

「技術的問題」と「適応課題」。その見極めが第一歩となる。
先程から「対話」「対話」と言っていますが、そもそも「対話」とは何なのでしょうか。私が書いた『他者と働く 「わかりあえなさ」から始める組織論』は、マルティン・ブーバー(Martin Buber)*2というユダヤ人の神学者・哲学者の『我と汝(I and Thou)*3』をベースにしています。彼は人間の関係性を大きく2つに分類しました。1つは「私とそれ」という関係性(道具的関係性)と、もう1つは「我と汝」という関係性(対話的関係性)です。著書の中では後者を「私とあなた」と書いています。「私とそれ」というのは「私にとって、あなたは道具である」という関係性です。「喉が乾いたら、水を飲む」というように、自分の目的に対して相手を使うというのが「私とそれ」という関係性です。一方、「我と汝」というのは「相手の中に自分を見る」という関係性のことを言います。そして、この「我と汝」という関係性を作っていくことこそが「対話」であるとブーバーは語っています。
これをリーダーシップ論の中で展開したのが、ハーバード・ケネディスクール(Harvard Kennedy School)*4のロナルド・ハイフェッツ(Ronald Heifetz)*5という研究者です。彼は「問題には、大きく2つの状況がある」と述べています。1つは「技術的問題(Technical Problem)」、もう1つは「適応課題(Adaptive Challenge)」と言われるものです。「技術的問題」というのは、「喉が渇けば水を飲めばいい」ですし、「データのストレージに問題があるならクラウドを導入すればいい」というように、「目的に対して手段が簡単に見つかるもの」「既存の解決策で解決できる問題」を言います。それに対して「適応課題」というのは、もっと複雑です。例えば、みなさんが友達から人生相談を受けたとします。あなたは「それだったら、こうしたらいいんじゃない?」とアドバイスすると、友達が「確かにそうなんだけど... ちょっとね... うーん...」と答えたとしたら、背後にこちらからは見えない、もっと複雑な問題が潜んでいることを知らせているわけですね。このように「適応課題」というのは、「技術的問題」と比較して、もっと複雑で困難な問題を指し、「適応課題」を解決することは時に痛みを伴います。
私は、「適応課題」に挑む上で、「観察」「解釈」「介入」という3つのプロセスが必要だと書きました。正論を伝えても相手が動かない場合、そうなる理由をこちらがよくわかっていない状態であるため、相手が置かれている状況をよく知らなければなりません。それが「観察」のフェーズです。そして、相手の置かれた状況をよく知った上で、どのようにアプローチするのか考えるのが「解釈」のフェーズ、そこから具体的にアプローチするのが「介入」のフェーズです。最初の段階では問題がはっきりしないので、よく「観察」しなくてはいけません。「観察」することで徐々に情報が増えてくるため、「解釈」や「介入」ができるようになっていくわけです。「介入」の段階まで来れば、世の中にあるハウツーや理論も有効に機能すると思います。
ところが、問題が何であるかをよくわかっていない段階で、いきなり「介入」する策を講じようとしても全く動かないわけです。「離職率が高い」という課題があった時に、「だったら、エンゲージメントを高める取り組みをやろう」と簡単に「介入」してしまいがちです。そもそも、どんな問題から派生して離職率が高くなっているのか。離職率の高さが告げるのは何の問題なのか。その点がよくわかっていないのに、巷に転がっているエンゲージメント向上策をやると、社員たちが「ああ、わかっていないなぁ...」と思って、さらに離職していくということが起こるんですね。だから、「自分たちは一体何がわかっていないのか?」ということを、しっかりと理解する必要があります。
「観察」「解釈」「介入」とありますが、実はその前があります。それは「準備」です。ここが絶対必要だと思います。つまり、今起きていることは「技術的問題」ではなく、既存の解決策では解決できない「適応課題」であるということに気づく必要があります。「私は、部下もしくは上司のことを、よくわかっていないんだ」と受け入れるのが「準備」の段階です。多くのビジネスパーソンの話を聞いていると、日本の企業社会はこの「準備」の段階に、かなりの課題があるということが見えてきました。多くの方は、「モチベーションを上げるためには、どうすればいいか?」「離職率を下げるためには、どうすればいいか?」「パフォーマンスを上げるためには、どうすればいいか?」という問題を「技術的問題」だと思っているわけです。ところが、実際にはこれらは「技術的問題」ではなく「適応課題」なんです。この事実を受け入れていくのが「対話」の一歩目になります。ここが難しいというのが、日本の企業社会の問題です。
「自分自身が問題の一部である」という気付き。
例えば、「権威主義的な上司は、自分の提案を歯牙にもかけません。上司が変わらないならば職場は何も変わらないのではないですか?」という相談をよく受けます。ある方からこういうことを言われたことがあります。「先生の言うことはよくわかりましたが、上司は全然話を聞いてくれないし、経営者はバカだからいくらやっても無駄だと思います。経営者が変わらないと企業は変わらないと思います」と言ってきた方がいました。そこで私が「確かにそう思われる筋もあるでしょう。でも、あなたが良いと思った提案を、上司はなぜ受け入れないんだと思いますか?」と聞くと、「権威主義的だからじゃないですか?」と答えるんですね。「権威主義的ってどういう意味ですか?」と聞くと、「前例がないことをやりたくないっていうことじゃないですか」と言う。さらに「じゃあ、なんで、前例がないことをやりたくないんだと思う?」と聞くと、「うーん... よくわかりません」と。そういうことがよくあります。
実際によく話を聞いてみると、上司は提案を潰そうとしているわけではなくて、「その提案内容をやる時に、人員配置をどう考えるのか? お客さんは来るのか?」と聞かれたようなんです。「それは上司の立場からすると、人員配置や顧客見込を用意すればやってみてもいいかもって言っているんじゃないの?」とその方に言いました。すると、「あ〜、そう考えたことはなかったです」と言っていました。そうした準備なしに「これはいいと思う!」と相手にぶつけても、それを受け止めて実際にやろうとすれば、相手側にも痛みや恐れがあるわけですよね。上司のことを、何かやるための「道具」だと考える「私とそれ」という関係性(道具的関係性)で考えている限り、上司の痛みや恐れを知ろうとすることもないわけです。それではそもそも相手について「観察」をしようとは思わないでしょう。だから、「私と同じように、上司も新しいことをやろうとする時には、当然、痛みや恐れを感じる存在なのだ」ということを受け入れるのが、「対話」の重要な入り口になるのです。

「なんでも提案してくれと言って、提案制度や社内ベンチャー制度を作ったのに、良い提案が全然出てこないんです。どうしたらいいでしょうか?」という質問を受けたこともあります。「良い」という言葉にピリッと来たので聞いてみました。「あなたの部下たちは、なぜ提案をしてこないんだと思いますか? 部下たちが能力不足だと思っていませんか?」と。また「ところで、『良い』提案が出てこないと言いましたが、これまで提案数はゼロだったんですか?」と聞いたら、「確かにいくつかはありましたよ。でもね、全然話にならないんですよ。こんな提案では話にならないから、もっと『良い』提案を持って来いと言って突き返したんですよ」と言うんですね。この状況、反対側の部下の側から考えると、まず何が「良い」提案なのかがわからないわけですよね。かつ、有効な示唆が何も得られないようなフィードバックをされると、提案する気も失せますよね。
この2つの話から言いたいことは、「実は、自分もその問題の一部だ」ということです。「部下が提案して来ない」ということに対して、「自分がその要因の一部になっている」ということに気付く必要があります。これが「対話」の重要なポイントです。「あなたに責任があるぞ!」と言いたいわけではありません。「自分が問題の一部であるならば、その問題にアプローチする方法がある」ということなんです。我々は、組織の中でお互いのことをよく知らず、孤立した状態で「何か良い方法はないか?」と探している存在です。そうではなく、きちんとつながりを再構築していくための「観察」を丁寧に行うことによって、外側にある解決策で組織を変えようという依存症的な方向に走らずとも、もっと良い方法を見つけられる。そのことを申し上げたかったわけです。
「相手の生きている物語」を観察する。
まず相手をよく知ろうとするということですね。そして、相手から自分はどう見えているのか、よく考えてみる、想像してみる。そうすることによって、八方塞がりだと思っていた状況でも、実はいろいろやりようがあるということが見えてきます。例えば「せっかく開発した製品なのに、隣の営業部が全然売ってくれない。すごく腹が立つ。しっかりと売るようプレゼンテーションで説明したのに、全然わかってくれない。あの人たちは一体何なんだ!」というようなことはよく耳にします。ところが、営業部を観察してみると、最近、クライアント企業の元に競合が現れて、その対応に四苦八苦しているために新製品の営業まで手が回らない、という状況であることがわかってきた。相手が困っている状況に対して、新製品がどのように貢献できるのかという筋を作って説明すれば、「それなら助かるわ!」と一緒に売ってくれることになるかもしれません。相手の状況をよく観察すると、さらなる可能性が見えてくるということです。「相手の生きている世界」「相手の解釈の枠組み」のことを「ナラティヴ」と言います。「語り」とか「物語」ということですね。相手がどういう「物語」「ナラティヴ」に生きているのかをよく知ること、それが「対話」ということです。
*1 べてるの家 | 1984年、北海道浦河町に設立された精神障害などを抱える当事者の地域活動拠点。「社会福祉法人浦河べてるの家」や「有限会社福祉ショップべてる」などの活動総体。特に、この施設を発祥とする「当事者研究」で広く知られる。自身の病気にオリジナルの病名(自己病名)を付けたり、病気や生活の苦労のパターンやメカニズムを研究して経過や自分の助け方(対処)を実践するなど、その研究はプログラム化され、多くの施設で取り入れられている。元来「べてる」とは、旧約聖書『創世記』28章の故事に登場する「神の家」を示す言葉であるが、この「べてるの家」については、障害の有無に関わらず人々が平和のうちに暮らしてきたドイツの街・ベーテル(Bethel)に由来し、浦河協会牧師であった宮島利光によって名付けられた。
*2 マルティン・ブーバー(Martin Buber) | オーストリア・ウィーンの正統派ユダヤ教徒の家庭に生まれた宗教哲学者・社会学者。イマニュエル・カント(Immanuel Kant)、セーレン・キェルケゴール(Soren Aabye Kierkegaard)、フリードリヒ・ニーチェ(Friedrich Wilhelm Nietzsche)などに触れるなかで、哲学、文学、芸術への興味を深めた。1924年、フランクフルト大学教授に就任すると、ヘブライ語聖書のドイツ語訳に携わった。ナチス台頭で諸国を流浪した後、1938年にパレスティナに着き、ヘブライ大学で教鞭を執った。独語で執筆された主著『我と汝』は英語、仏語、日本語などへと訳され、特に西洋思想の発展に大きな影響を与えたとされる。1965年、エルサレムにて死去。
*3 我と汝(I and Thou) | 著者であるマルティン・ブーバー(Martin Buber)は、幾多の迫害や苦難の中を生き抜きながら、その生涯を通じて「我と汝」に関する施策を深め続けた。世界は人間の取る2つの態度(著書では「根源語」と読んでいる)、すなわち「我と汝」「我とそれ」があると説き、語られる根源語によりその人自身のあり方、また、人が世界と関係するその仕方が2つに分かれる、ということを主張している。
*4 ハーバード・ケネディスクール(Harvard Kennedy School) | 1936年に設立されたハーバード大学の公共政策大学院。1966年、第35代大統領 ジョン・F・ケネディ(John Fitzgerald "Jack" Kennedy)の名を冠して名称が改められた。公共政策や国際開発分野において、世界有数の研究機関として知られる。アメリカにおける政権交代時の人材共有源として重要な役割を果たしている。
*5 ロナルド・ハイフェッツ(Ronald Heifetz) | ハーバード・ケネディスクール(Harvard Kennedy School)で30年以上にわたり、政府・非営利団体・企業と協力しながら、リーダーシップの教育と実践に携わる。主な著書に『Leadership on the Line(最前線のリーダーシップ – 何が生死を分けるのか)』『The Practice of Adaptive Leadership(最難関のリーダーシップ - 変革をやり遂げる意志とスキル)』などがある。




