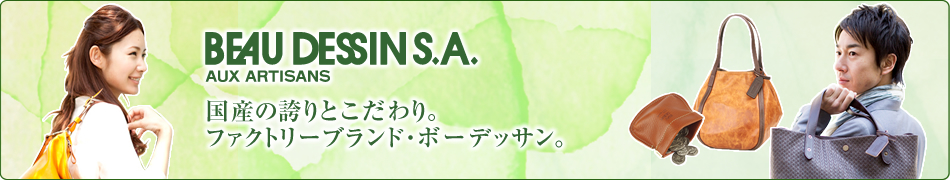BEAU DESSIN インタビュー

BEAU DESSIN S.A. 生嶋様(写真左)、
インタビュアー:店長 金山(写真右/テキスト赤色部分)
上質な素材でシンプルな表現を。ボーデッサンの始まり

—今日はよろしくお願いします。
それでは早速ですが、BEAU DESSIN S.A.が生まれた経緯を教えていただけますでしょうか。
ボーデッサンは1979年、35年前に創業しました。当時日本のバッグ業界では、ライセンスブランドを扱う大きな問屋さんが影響力を持っていました。大半のメーカーはその指示のもと、ひたすらバッグを作っていたと記憶しています。
(当時のビジネスの形ではなく)もっとみんなの期待に応えられるようなものを作りたいと、もっとヨーロッパやイタリアに負けないようなものを日本でも作れないかと、血気盛んなメンバーと共に、夢とロマンを持って、会社を設立しようということになりました。
会社が出来てからも、試行錯誤しながらオリジナル商品を世に問うというまでには、2〜3年はかかったと思います。

そんな中、業界の先輩に実際にヨーロッパに連れて行ってもらう機会がありました。日本には問屋という大きな会社があって、何人も人がいて、企業として成り立っているのに、向こうに行ったときふと気づいたら、そうしたものがないぞと。
作り手=ブランドであり、作り手が発信しているのが普通という世界を知りました。日本特有の業態、問屋という大きな企業は見えなかった。

―なるほど。ものづくりの形が、日本とは異なっていたわけですね。
ええ。そこで、熱い想いを抱き、日本に帰ってもそういう作り手であり会社でありたいと思うようになりました。展示会を開き、商品を見て頂いて、注文を受けてという作業が、本当にそこから始まりましたね。
それがいいのか悪いのかは別としても、バッグに関して当時素人から始まり先入観がなかった分、作るものを新鮮に見て頂けたように思います。
いわゆるお堅いハンドバッグであったり、(当時決まりきったような形しかなかった)よくあるバッグではないものが、ボーデッサンにいけばある、というようなポジションをその時代、コツコツコツコツ作っていった、というのが当初のストーリーだと思います。
ボーデッサンのコンセプトについて

—BEAU DESSIN S.A.のコンセプトについて、お話をうかがえますか。
上質な素材でシンプルな表現をして、持ってくれている人のバッグが前へ前へ主張するのではなくて、その人のセンスとか、知性とか、ライフスタイルとか、生き方をちょっと後押しができるような、そういう存在のバッグを目指しています。
—BEAU DESSIN S.A.のバッグは、シンプルなんだけれど、やっぱりどこか違うんですよね。私が初めて持ったBEAU DESSIN S.A.のバッグが、オイルバッファローのカーペンターバッグでした。初めて見たとき「何だこのバッグは…!」と衝撃を受けて、惚れ込んだのを今でも覚えています(笑)
ありがとうございます。そう感じてもらえたら非常に嬉しいですし、励みになります。真面目すぎてもいけない、クスッとさせるわけではないけれど、ちょっと立ち止まってもらえる、ちょっとだけルールから外れる、ちょっとだけストーリーから外れる、そういうことができないかなというのはいつもあります。


ボーデッサンのバッグには説明しにくい主張があるのと同時に、じゃあこれは仕事で持つのか、どこで持つのか、そういった用途・設定が限定されていないバッグは多いと思います。
レディースやメンズの境目までも分かりにくいものがありますが、そう言ってもらえると「良し!」と思いますね(笑)性別や年齢を指定しない、いかにもいかにもしていないものが大好物なんです。「そうそうそう、こういう感じの方に持ってもらって、こういう感じこういう感じ」って、あんまりはまらないもの。
作り手の個性と素材の個性のジョイントから生まれるボーデッサンのバッグ

—そうしたコンセプト・ものづくりへの想いは、製品にどのように表現されていますか?
作り手の個性にさからわないこと、素材の個性に逆らわないことで表現しています。作り手の表現と、素材の質感のジョイントというのか。素材に逆らわない、その素材が無理せず、質感が伝わるのは、色もこういう色だろうな、この素材ならこんな色が魅力的だな、という風に組み立てていきます。
 こんな色のバッグを作りたい、というのはこれまでも一切なく、例えばこの職人なら、こういうものを作るとそういう味が出る、例えばこの素材なら、あの作り手とジョイントして組み立ててプロデュースをすると、この素材が活きる、という具合です。
こんな色のバッグを作りたい、というのはこれまでも一切なく、例えばこの職人なら、こういうものを作るとそういう味が出る、例えばこの素材なら、あの作り手とジョイントして組み立ててプロデュースをすると、この素材が活きる、という具合です。
作り手にも1人1人個性があります。もちろん技術レベルは要求するけれども、その職人のプライドであったり、革の厚みであったり、ステッチの間隔であったり、例え同じ型紙で同じ革で縫製しても、作る人で別のものになるんです。そうした人や素材との出会いに、感謝ですね。分かりにくい個性かもしれませんが、感じてもらえると嬉しいです。





あとは—、そうですね、頭の中でシミュレーションをします。どうしたらいいんだ?どういうステッチにしよう。糸をどうしよう。パーツをどうしよう。こうするとこうなるはずだ、なればいいな、そういう方向に自分で判断してセットをしていって、組み立てていくんですね。そうして思っているものが出来上がったときというのは、幸せですね。それが支持されたときは、本当に嬉しいです。
簡単にはいかない、ものづくり


—ものづくりをされる中で、ご苦労された点などあればうかがえますか。
ものを作るというのは、簡単にはいかないです。簡単に出来るものは簡単には持っていただけないし、相応の魅力があるものは、やっぱり簡単には出来ないんですね。
肩の力を抜いたものを作りたいと思うんですけれど、どこは肩の力を抜いて、どこはプロとしてしっかり押さえるか。間違えるとチープなものになるし、逆に間違えると、コッテリしてて、作り手の自己満足になってしまうし。そこの判断はむずかしいです。ボーデッサンオーアルチザンって(ブランドの名前に)ついている限り、どこかでものづくりやクオリティにプロフェッショナルなものをきっちり見せないといけない。

また、苦労というのかは分かりませんが—、創業当時「こんな新しいものを作りたい」「そうじゃなくて、こんなことができないか」と作り手、素材屋さんに話をしても、なかなかこちらを向いてくれる作り手、素材屋さんがいなかった。わざわざそんな新しい試みなどしなくても、当時はみなさんお忙しかったので。

革を裁断するのに自分のところで出来ないから、革を裁断屋さんに運んで、お願いしに行くんです。うちなんか1枚1枚違う革が多いから大変で。素材感や革の質感を出そう、ここにふくらみがあって、しなったほうがいい、ただの通した袋にしたい。
…そういうことを言い出すと、どうしても大きな型紙のバッグになるんですよ。そしたら、裁断屋さんには『こんな革でこんな型紙なんか革1枚でバッグ1本分もとれないぞ!』って突っ返されたりするんですよ(笑)
—(笑)

結果、裁断はやっぱり自社でしなきゃと思いました。ダイナミックな型紙でいいんだ、裁ち落としの際の無駄な部分を考えよう、工夫すれば大丈夫だと。
最初に(金型の)プレスを社内に置いたときには、感動しましたね。毎日自分たちで革を運び、自分たちで裁断ができる。そのプレスは、今でも工場で現役で動いてくれています。
—なるほど…。ボーデッサンのバッグの独特のデザイン・佇まいは、そうしたご苦労や、ひとつひとつのこだわりの上に成り立っているんですね。
インスピレーションが湧いてくるとき

—ものづくりのインスピレーションは、どんなときに湧いてくるのでしょうか。
自分がアンテナを立てて日々行動をしていないと、魅力的なモノやシーンや人を通過してしまうんですね。そういうことのないようにと、いつも思っています。
—インスピレーションを受ける場所などはあるのでしょうか?
ヨーロッパに出かけているとき、インスピレーションを受けることは多いです。イタリアにでかけて、素材…革、生地に触れる。素材の作り、開発力で言うとやっぱりイタリアって本当にすごいって私は思うんですよ。その後、必ずパリへ寄ります。主に、左岸の6区界隈が好きです。1日〜2日ほどいるとスッと(インスピレーションが)胸に降りてきて、ワクワクしてきます。風景・人・ファッション、色んな物を感じて帰って来れるんですよ。
—ボーデッサンの製品は、日本の中だけにいたらできないデザイン、そのように思います。
かもしれないです。そういう空気をやっぱり好んでいる部分はあります。極端にいえばイタリアの素材を、パリの空気で表現できたらな、というような。いみじくもBEAU DESSIN(美しいデザインの意)って、フレンチネームですしね(笑)
MADE IN JAPANのものづくり

—ボーデッサンの考える、MADE IN JAPANについてお話をうかがえますか。
日本で作る、職人気質(かたぎ)、浪花節的な、伝統的な日本を主張するのもそれはそれでいいと思いますし。革製品で作ることで、クラフトチックになってしまって、「This is 革です」みたいなものもいいとは思うんです。
ただ、私はもっと洒落た、センスのある、浪花節でもない演歌でもない、洒落た表現ができないかと思っています。日本でそうしたものが出来るんだぞ、という事がしたい。
私自身も含めて、ボーデッサンが歩んできたストーリーで、日本の人とものを作ってるわけです。ものを作っていく上で、ときには無理を聞いてもらったり、面倒を見てもらったり、夜なべしてもらったりしている。
そのストーリーの中で、こんなに一緒に頑張ってくれてるのに、まだまだ恩返しができていないわけです。一緒にやってきた人たちと、一緒になって前を向いていきたいという想いがあります。

—まずは身近な人たちから、ということですね。作り手・売り手・使う人の距離が近いということが、すごく幸せなことじゃないかと考えているのですが、共感させていただく点が多いです。
実際です、身近な靴の職人さん、つながりのある方々と話をしていても、これから日本でものづくりをしていくのは非常に厳しいと感じます。革の値段の高騰もそうですし、色んな意味で地盤沈下が起きているのは事実です。
そんな中、身近な人たちにボーデッサンと協力して良かった、間違ってなかった、そういう風に思ってもらいたい。日本製のものづくりが厳しい時代であることは分かっていますが、それは一つの目標であり、モチベーションでもありますね。
ナチュラルな革のもつデメリットとの戦いに挑めるか

—革素材へのこだわりをお聞かせ願えますか。
今でも、革として"こんがり"に魅力的な向かえる革、"こんがり"なってくれる革、そういう革らしい革って、唯一お財布くらいでしか最近はなかなか見ないですよね。それはバッグにするには値段など含め贅沢すぎるということと、半分はナチュラルな革は手入れが必要だし。
革が劣化していって芯が抜けてグダグダになって。それが味として捉えていただけるか、ダメになっちゃったと捉えられてしまうか、といった危険、デメリットはあります。ナチュラルな革を使って大きい袋を作ると、デメリットとの戦いが半分。
よく考えてみたら、海外の一流ブランド—それこそ素晴らしい値段のブランドの革製品で、ナチュラルな革の製品って見たことあります?
—ないですね。
ないでしょ?それは無理だからです、結局。
世界中で、パリもミラノも東京も香港もロンドンも、世界のショップで同じクオリティが店頭に並ぶ、そんなことはナチュラルな革では不可能です。
日本だけじゃないでしょうか。"こんがり"をテーマにしてもらえるなんて、そのような形でお客様と接点がまだあるのは。
海外なら絶対に傷もつきそうにない顔料の乗った型押しの素材、そんな革製品が大半です。一部ナチュラルな"こんがり"な革でできてるものは、それこそ超高級で、特別贅沢なものというか、そういう捉え方です。「ナチュラルな革のもつデメリットとの戦いに挑めるか」どうかが、私たちの大きな課題といえるでしょう。

世代もどんどん変わって行って、自分の娘などもそうですが、別に合皮になんの抵抗もなければ、展示会にいらっしゃるバッグ屋さんですら「すいません、これはリアルレザーですか?」「すごいですね、リアルですね!」なんて言われちゃう(笑)
—(笑)
例えばボーデッサンにワビサビというシリーズがあります。ワビサビは全く逆の素材と言えるんですけど、かっこいいんですよね。だからそうした視点もいつも持っていないとと思いますよ。使っててこうなりました、っていう素材は本当に一部ですから、革でも。革全体として必ずしもこんがりして、エイジングが愉しめて味わいが深くなっていくわけではない、っていうこともきちっとお客様と向かい合っていかなければならないなと、最近感じています。
地球上でファッション素材とすれば、こんなに自然なものって革だけですからね。—そうですね。その自然の恵みというのか、素晴らしいものを顔料でベタベタにしてしまうっていうのは、個人的にはもったいない、いやだなぁと思いますけれどね。
その、いやだなぁと思う人がどんどん減ってきているんです今。別にいいじゃんって(笑)(顔料を塗れば)傷がつかないし、色は褪めないし。ただ、自分の中で許せる範囲、許せない範囲がありますから、だからといってこれでいいとは思わないっていうこだわりがあるので、それはそれで、思うんですけれどね。
思い入れのある革やシリーズについて

—生嶋様が思い入れのある革やシリーズはありますか。
まさしく、さっき言ってくれたバッファローのカーペンターバッグ。最初は大サイズしか作ってなかったんですよ。モデルとすれば非常にあれには思い入れがあるし、アイテムとすれば色んな表現をしますけれど、『クラッター』のシリーズは、ニュートラルで、やっぱり革らしいナチュラルな部分を残しながら、表現が「こりゃやっぱボーデッサンだな」って、自分の中で思い入れがあるアイテムですね。
—私もクラッターのバッグを愛用していますが、『THE・ボーデッサン』みたいな…
パンパカパーン!ですね(笑)
—(笑) …みたいなものは感じますね。
例えばこの(持っているクラッターのバッグを見せながら)ハンドルの付け根のクロスしてる縫製ですとか、なんかこう…ないんですよ。一見シンプルなトートバッグなんですけれど、ないんですよね、そういうデザインって。
基本的には引き算したいんですよね。ものを、表現を。でも引きすぎるとつまんない、何だかぼーっとしたものになってしまうから、ほんとそこはいつも一番企画するときに難しいですね。“物足りなく感じさせないシンプルなもの"ってなんなのか?といつも悩むというか。
クラッターのメッセンジャーバッグがあるんですけど、CL482っていう、太い手紐の。

—いいですね、あのバッグは。
あれも思い入れがありますね。海外、外へ出るとめちゃくちゃうけます。「それどこで買ったんだ」「どこのバッグだ」とか「いやこれうちで作ってるバッグだ」「どこいったら売ってんだ」「こっちではどこで売ってんだ」「いやこっちでは売ってない」「なんで売らないんだ」って責められる(笑)
—責められる(笑)すごいですね。
でも、正直いってね、今もし発想しても、ああいう風に作れるかというのは分からない(笑)あの時代だから、あんな手紐の幅、ショルダーの手紐だけでバッグ一本作れるんじゃないかって、革の使用量がですね、今じゃそんな勇気起きないかもしれないですね。
—あれは贅沢な革の使い方ですよね。
その時代、自分も先入観がないから。そんなベルト作ったら大変なことになるぞって(笑)。深く考えず「太いほうがいい」って思うだけで。だんだん邪念がはいってきて、ダイナミックさがかけてきてるのかもしれませんね(笑)
—(笑)CL482のような定番以外にも、ボーデッサンの魅力は変わることなく、新作からも素晴らしい魅力を感じます。
愛用のお品を拝見!
—生嶋様が長年愛用されているボーデッサンのお気に入りのお品などみせていただけますか?

7〜8年前まで毎日持ってたのが、このミネルバボックスのブリーフ。もうドロドロになるまで毎日それこそ手入れの手の字もない毎日で。
—おぉ…!これは…素敵ですね!もともとはチョコ色でしょうか、これはいいですねぇ。
いつも持って歩いていました、得意な顔して(笑)
—(笑)(バッグを見ながら)貫録がありますね。
ありがとうございます。袋なんですよ。うちのバッグはね、袋なんです、袋仕立て。こういうポケットもシンプルに切り込みを入れて、ファスナーを配置して、奇をてらっていない。
—それなのに、佇まいからどこかボーデッサン“らしさ”を確かに感じます。
この質感と、素材がものを言ってくれているんですよ。素材の個性に逆らわないで作っていますから。ちなみに、年とってこれはちょっと重いなって思って(笑)今はこれを使っています。(バッグを取り出す生嶋様)

—軽いから。笑
これ、この素材すごいんですよ、この素材。(リモンタの高密度ナイロン)今この形が、非常に自分の中でも自分と同じ線上に立ってて。袋です、袋。
魅力的な素材を探して


—素材を調達するために、様々な国を駆け巡っていらっしゃいますよね。
当時素材探しをしていて、今みたいに情報がなかったですからね。これなんだろう、この革、この生地。そうなると、とにかく突撃部隊しかないですから(笑)尋ねていくしかないですから、素材探しに限らず。気になって、イタリアのトップブランドさんの工場にお邪魔したこともあります(笑)当然初めは「なんだなんだ」ってなるんですけど、熱意が伝わったのか、お話をいろいろうかがったり。
素材といえば—、古い、リモンタ社との付き合いもそう。そのイタリアのトップブランドも使っている。どこいったら買えるんだろう、って疑問に思ったら突撃、ですね。そして関わることになれば、20年30年付き合う。そういう覚悟です。私としては、別に世界を駆け巡っているというわけでもなく(笑)、ただいいなぁと、やってみたいなぁと思ったら執念というか。自分で感じて、見つけて、覚悟してリスクはって、材料を頼んで作るっていう想いです。
1色何デシ(※革の面積の単位、1デシ=10cm×10cm)頼んだらその革を買えるか、必死の覚悟がいりましたからね。そういう素材にトライするときは。
また、世界だけでなく日本にも魅力的な革があります。例えばウォッシュ・ガーメントシリーズの革は、下地の段階でフィニッシュの色にどこまで近づけるかを追及しています。けっこう画期的なんですよ。
今後の展望について

—今後の展望など、お聞かせ願えますか。
今までやってきたストーリーを、表現は時代によって変わりますけれども、ものを作っていくっていうことを、いかに継続して先につなげていくか。おんなじことをやっていてはいけないわけで。いろんなことを勉強して、ボーデッサンのストーリーが続くようにすることが最大の目標です。
そして作り手―社員も含めてきちっとした、努力の甲斐のある会社にしたいなと。将来いつかはね、浪花節じゃやだって言ってるんですから、ヨーロッパの人たちに、直接問う場面をつくってみたい、ていうのはあります。
その方法、私アナログですからなかなかそういう世界との通じ方はわかりませんけど、近い将来、この作業をがんばっていく中で、そういう場面をつくりたいってのはあります。またそういうことを考えたりやろうとしないと、若い作り手たちも夢やロマンがないですからね。
職人の皆様のお声

職人の皆様と。
- お名前:野勢 和正 様
- 職人歴:10年
- 担当されている工程:縫製部の中にある1つのチーム(4~5名)のリーダー。日々の製作の他、年2回の展示会に向けての企画参加と、サンプリング(型おこし)。
- 思い入れのあるシリーズ:ウォッシュ・ガーメントシリーズ。この素材のバッグを毎日使用していますが、良い感じに味が出てきています。作り手ながら、いいバッグだなぁと。改めてボーデッサンの良さを感じます。
- お客様へのメッセージ:1つのモデルを何本作ろうと、1人のお客様と出会える1本が納得していただける様、気持ちを込めて作っています。 ボーデッサンブランドをよろしくお願いいたします。
- お名前:秋田 浩 様
- 職人歴:14年
- 担当されている工程:工場1Fでの革の裁断。日々の製作の他、年2回の展示会に向けての企画参加と、サンプリング(型おこし)。
- 思い入れのあるシリーズ:PW(ポニー・ワックス)シリーズ。10年以上前、初めてこの革を見た時、色むらとシミがすごく、どこを裁断すれば良いのか途方にくれましたが、出来上がったバッグが、その特徴を生かした味わいのあるものになっているのを見て、苦労のしがいを感じました。
- ものづくりで一番大切にされていること:ボーデッサンの扱う革は、そのほとんどがキズの隠れないナチュラルなもので、1枚1枚色の違いもあり、神経をすり減らす作業なので、集中力を切らさない事です。
—ボーデッサン 生嶋様・職人の皆様、貴重なお話をありがとうございました!