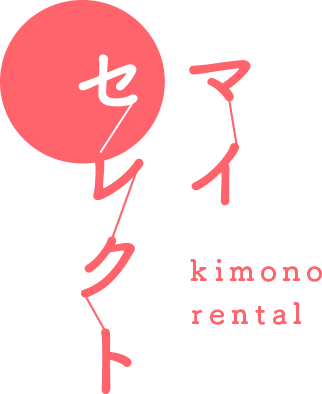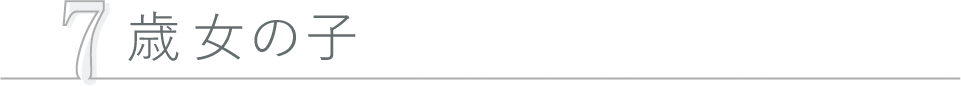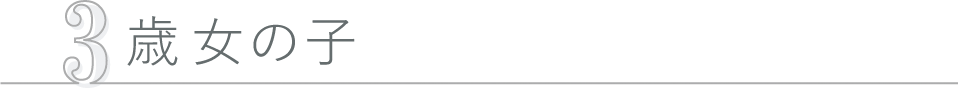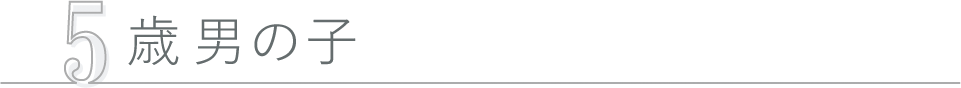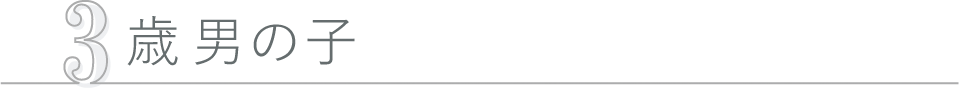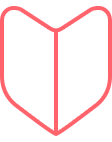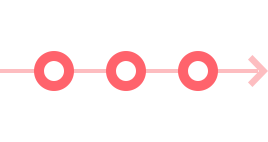実はあまり知られていない基本情報をご紹介!
最終更新日:2022.08.07

秋になると小さな子供たちが家族と一緒に着物姿で神社を訪れる姿をよく見かけますよね。
七五三は子供の成長を祝う大切な行事で、毎年11月15日に3歳・5歳・7歳の子供たちを祝うのが慣例です。
でも実は、どうして七五三のお祝いをするのか、なぜこの年齢なのか、など、背景はあまり知られていません。
お子さんやご家族の七五三のお祝いをする前に、少し七五三について知ってみませんか?
この記事では、七五三についての基本情報をご紹介していきます。
-
ICHIHA
-
JILLSTUART
-
SUGAR KEI
-
九重
↑人気商品 7歳七五三衣裳↑
七五三はどのように始まった?

七五三のルーツをたどると、古くから3つの儀式が執り行われていたことがわかります。
髪置きの儀(かみおきのぎ):
古くは平安時代、武家では男女の子供がそれまで短く剃っていた髪を伸ばし始める3歳ごろに行われていた儀式です。
袴着の儀(はかまぎのぎ)または着袴の儀(ちゃっこのぎ):
同じく平安時代に、5~7歳の男の子が初めて大人のように袴を着用する際に行われた儀式です。
その後、江戸時代に入ると5歳の男の子お祝いとして定着しました。
髪置きの儀と合わせ、これらの儀式が一番古い七五三の起源とされています。
帯解の儀(おびときのぎ):
鎌倉時代に入ると、9歳の男女に行われる儀式が始まりました。この儀式より大人と同じように帯を結ぶようになります。
その後室町時代までは、男女ともに9歳に行われていましたが、江戸時代に入り、5歳の男の子・7歳の女の子と変わっていきました。
これらの儀式が徐々に庶民にも広がり、近代になって現在のような「七五三」として定着していきました。
-
ICHIHA
-
JILLSTUART
-
ICHIHA
-
華徒然
↑人気商品 3歳女の子 七五三衣裳↑
七五三を祝う意味とは。

七五三には子供が無事にその年齢を迎えられたことに感謝し、さらなる成長を祈る親の思いが込められていますが、なぜそんな行事を行うようになったのでしょうか。
七五三の起源となる時代には、子供が健康に大人に成長するということは、とても幸運なことでした。現代と違い、小さな子供は亡くなることも多かった時代です。
3歳?7歳は特に病気にもなりやすかったため、この時期に子供の成長を祈祷することがとても大切にされていました。
現代でも子供の健やかな成長を願う親の気持ちは変わらないもの。
昔の人の切実な願いを大切にして、家族みんなでお祝いしたいものですね。
-
PetitPri
-
PetitPri
-
PetitPri
-
PetitPri
↑人気商品 5歳男の子 七五三衣裳↑
七五三は正式にはいつ?

毎年11月15日が七五三の日とされています。
由来は諸説ありますが、鬼が出歩かない日、江戸幕府第四大将軍である徳川綱吉が長男の健康を祈った日、旧暦での満月の日、などと言われています。
現代では学校や仕事の関係上、平日に七五三詣に出向くことが難しいのでこの日にこだわらず行われています。
最近では撮影メインで季節を問わず家族でお祝いをしている傾向があります。
上記画像は桜をバックに春に七五三ロケーション撮影をしております。
-
PetitPri
-
PetitPri
-
PetitPri
-
PetitPri
↑人気商品 3歳男の子 七五三衣裳↑
男の子と女の子のちがい

七五三の起源でもご紹介した通り、古い歴史のある七五三は男女それぞれの儀式があります。3歳・5歳・7歳の全ての男女にお祝いをするわけではありません。
年齢と性別は下記のように定義づけられています。
3歳:男女とも
5歳:男の子のみ
7歳:女の子のみ
これは起源の儀式が3歳で男女ともに髪を伸ばし、5歳で男の子は袴を着始め、7歳で女の子は帯をつけ始めたためです。
男の子は3歳・5歳、女の子は3歳・7歳と覚えてくださいね。
七五三の当日は何をすればいい?

七五三のお祝いには着物を着て、神社へお参りするのが一般的です。
七五三の日は11月15日とされていますが、11月15日に必ず行かなければならないという訳ではないので、15日当日が平日の場合には、前後の週末や祝日など休日に合わせて神社へお参りする場合がほとんどです。
事前にご家族で決めておくべきことは、
・行く神社
・お参りだけ?祈祷を受ける?
・お参りの後の予定
などです。
行く神社に決まりはありませんので、小さなお子さんの負担にならないようにご自宅からの距離やゆかりのある神社など事前に調べ、ご家族で決めましょう。
また神社でお参りするだけではなく、祈祷を受けることもできます。
祈祷とは、神社で神主さんに祈りを捧げていただく儀式です。「ご祈祷料」などのお礼を納める事が一般的ですので、事前に神社に確認しましょう。
また、お参りの後に食事会やご近所に挨拶をするご家庭もあります。
七五三の日の一日のスケジュールは予め決めておくとスムーズです。
まとめ

七五三の基本情報についてご紹介しましたが、起源をたどると、実はあまり一般的に知られていない背景や歴史があり、子供への健やかな成長を祈る家族の思いが詰まったものであるということが分かりますね。
七五三の起源、年齢、男女差、日にちなどもぜひ参考にしていただき、ご家族にとってより思い出深い七五三にしてくださいね。