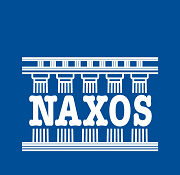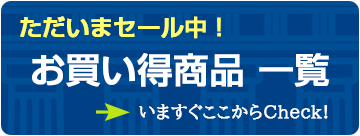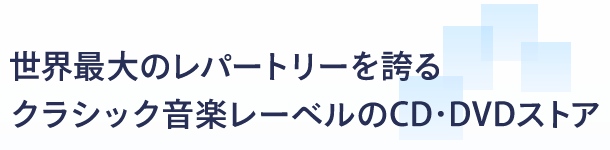【ナクソス】 ブラジルの音楽
13 件 / 13件中
-
ロレンゾ・フェルナンデス(1897-1948):
組曲「田園風東方の三博士祭」
交響曲 第1番
交響曲 第2番「エメラルド・ハンター」 [ファビオ・メケッティ (指揮)/ミナスジェライス・フィルハーモニー管弦楽団]発売日:2024年06月07日
CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
20世紀に活躍したブラジルの多くの作曲家と同様、フェルナンデスは民族主義的な作風から出発し、それらを国際的な技法や様式と統合することを試みました。 「田園風東方の三博士祭」組曲は初期の民族主義的な路線による代表作。クリスマスをモチーフにした親しみ易い音楽で、特に覚えやすくノリ易い第3曲「バトゥーキ」はブラジル管弦楽名曲集の定番の一つ。2022年に東京で行われたブラジル独立記念200周年コンサートでも演奏され喝采を博しました。 交響曲第1番はバルトークに影響されて書いた4楽章形式の力作。古典的な構成による純粋音楽を目指しつつもブラジルらしいリズムや旋律が随所に顔を出します。エメラルドを求めて密林に入り、先住民や大自然の脅威に直面した冒険家を描いた第2番は標題音楽の性格が強く、ドラマティックな作品。作曲者は初演を聴くことなく世を去りました。 ※国内仕様盤には木許裕介氏(指揮者/日本ヴィラ=ロボス協会会長)の日本語解説が付属します。
収録作曲家:
-
ゲーハ=ペイシ(1914-1993):
ラグーナからの撤退(管弦楽作品集) [アブネル・ランディム(ヴァイオリン)/ニール・トムソン(指揮)/ゴイアス・フィルハーモニー管弦楽団]GUERRA-PEIXE, C.: Retirada da Laguna (A) / Violin Concertino / Museu da Inconfidência (Landim, Goiás Philharmonic, N. Thomson)
発売日:2024年03月22日
 NMLアルバム番号:8.573924
NMLアルバム番号:8.573924CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
「交響的組曲第1番、第2番」のCD(NYCX-10322/8.573925)が『レコード芸術』や『朝日新聞』等で称賛され、突如として注目を集めた20世紀ブラジルの作曲家セーザル・ゲーハ=ペイシ、待望の新録音が登場。「ラテンのノリ」というイメージに相応しいリズムと色彩に、時としてショスタコーヴィチを思わせる劇的でシリアスな場面描写を伴う作品群に注目です。 ゲーハ=ペイシは、ポルトガル移民でアマチュアの音楽家だった父からギターを学び、音楽学校でヴァイオリンを学んだ後、指揮者・教育者として活躍。ラジオ・テレビ番組や映画のための音楽も手掛け、ブラジルのフォーク・ミュージックの要素を取り入れた作品を残しています。 冒頭の「ラグーナからの撤退」は、1867年のブラジルとパラグアイの戦争を描いた小説にインスパイアされた交響組曲風の作品。演奏時間40分余りの大作で、勇壮で高揚感のある第1部、恐怖、飢饉、疫病などさまざまな危機に直面するブラジル軍を描いた第2部、戦死者たちを悼みながら撤退する兵士たちを描く第3部で構成されており、最後は悲劇を浄化し平和を願うかのような抒情的な旋律で締めくくられます。最後の 「インコフィデンシア博物館」は、ポルトガルからの独立運動の引き金となった事件の指導者で悲劇的な死を遂げたチラデンテスへのオマージュ的作品です。両曲とも場面や心情描写に長けたゲーハ=ペイシの手腕が遺憾なく発揮されており、熱気をはらみ、時として鬼気迫るようなサウンドと共に、聴く人の心にストレートに迫る力をもっています。 悲劇的要素の強い2作に挟まれた「独奏ヴァイオリンと室内管弦楽のためのコンチェルティーノ」は、ヴァイオリニストでもあったゲーハ=ペイシの面目躍如とした陽気でエンターテインメント性の高いコンサート・ピース。ブラジル北部の民族文化を取り入れながら新しい作品の創作をめざす「アルモリアル運動」から生まれた作品で、民族色豊かな旋律とリズムに乗ってソロが華麗な技巧を披露してゆく音楽は理屈抜きに楽しめるものです。 ※国内仕様盤には木許裕介氏(指揮者/日本ヴィラ=ロボス協会会長)の日本語解説が付属します。
収録作曲家:
-
アウメイダ・プラド(1943-2010):
ヴァイオリンとチェロのための作品集 [エマヌエーレ・バルディーニ(ヴァイオリン)/ハファエル・セザリオ(チェロ)]REZENDE de ALMEIDA PRADO, J.A.: Violin and Cello Works (E. Baldini, Cesario)
発売日:2024年01月12日
 NMLアルバム番号:8.574459
NMLアルバム番号:8.574459CD価格:1,900円(税込)
ナクソスがブラジル外務省との提携で進めているブラジル音楽のシリーズの最新作は、アウメイダ・プラドのヴァイオリンとチェロのための作品集。20世紀後半から21世紀初頭にかけてブラジルで活躍したプラドは、小鳥のさえずりから緑豊かな森の音、銀河系の星々、そして民間伝承まであらゆるものにインスピレーションを見出し、様々な編成の作品を書き上げました。 このアルバムの冒頭に収録されている「シャンゴの魔法の本」は以前発売された「オリシャーたちの交響曲」(NYCX-10400国内仕様盤/8.574411輸入盤)と同じ時期に書かれた作品で、アフリカ由来の伝統宗教に登場する神々たちが描かれています。 1999年の「シランダス」は、彼の友人たちに捧げられた、民俗舞踊の要素が強く表れた耳なじみの良い音楽。生き生きとした無伴奏ヴァイオリン・ソナタと抒情的なカプリッチョは、ヴァイオリンの表現力を最大限に引き出すものであり、優れたヴァイオリニストとなった彼の娘コンスタンサのために書かれました。 「四季」はブラジル音楽に取り組む若い音楽家のコンクールの課題曲として作曲されたもので、各楽章では奏者の技術が試されるように工夫されています。
収録作曲家:
-
クリーゲル(1928-2022):
〈管弦楽作品集〉
カンティクム・ナトゥラーレ他 [ニール・トムソン(指揮)/ゴイアス・フィルハーモニー管弦楽団]KRIEGER, E.: Orchestral Works - Canticum Naturale / Ludus Symphonicus (F. Fernandes, São Paulo Symphony Choir, Goiás Philharmonic, Neil Thomson)
発売日:2023年11月10日
 NMLアルバム番号:8.574408
NMLアルバム番号:8.574408CD価格:1,900円(税込)
エジノ・クリーゲルは幼いころからヴァイオリンの才能を発揮。リオデジャネイロでブラジル作曲界の指導的な存在であったケルロイターに作曲を学んだ後、コープランドの招きで渡米してタングルウッドやジュリアードなどで学びました。一旦帰国した後、英国王立音楽院でバークリーに師事。帰国後は作曲を続ける傍ら、放送局付きのオーケストラの指揮者及び音楽番組のディレクターとして欧米の最新の動向を紹介するなどしてブラジル音楽界に影響を与えました。その作風はセリー主義、新古典主義を経て、伝統と前衛の融合が図られており、作曲年代によってさまざまな表現が楽しめます。 アルバムには6作品が収録されていますが、その中でも「カンティクム・ナトゥラーレ」は広大なアマゾンを音で描いたクリーゲルの代表作の一つです。 世界初録音となる「ファンファーレとシークエンス」は合唱を伴う5分程度の小品。3つのトランペットと4つのホルンが呼び交わす中で奏されます。「Variações Elementares=諸要素の変奏曲」は短い旋律がモティーフとして用いられた10の変奏からなる作品。17世紀のポリフォニーも駆使しながら発展していく音楽です。また「ノバ・フリブルゴの3つの映像」はリオデジャネイロ州の山岳地帯ノバ・フリブルゴ市からの委嘱作。弦楽オーケストラとチェンバロのために書かれており、弦の特殊奏法など楽器テクニックを要する作品です。 ブラジル音楽シリーズでおなじみのニール・トムソンが指揮するゴイアス・フィルハーモニー管弦楽団による演奏です。
収録作曲家:
-
サントロ(1919-1989):
〈交響曲全集 第3集〉
交響曲 第8番
チェロ協奏曲他 [マリーナ・マルチンス (チェロ)/デニーシ・ジ・フレイタス (メゾ・ソプラノ)/ニール・トムソン (指揮)/ゴイアス・フィルハーモニー管弦楽団]SANTORO, C.: Symphonies (Complete), Vol. 3 - No. 8 / Cello Concerto (D. de Freitas, Marina Martins, Goiás Philharmonic, N. Thomson)
発売日:2023年07月14日
 NMLアルバム番号:8.574410
NMLアルバム番号:8.574410CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
ブラジル外務省が主導するプロジェクト「Brasil em Concerto」。19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲のブラジル音楽をブラジルのオーケストラが演奏、録音するという、これまでになかった大がかりな企画です。その中でもブラジルを代表するシンフォニストであるクラウジオ・サントロの交響曲全集は注目の企画です。 このアルバムには1960年代の作品を収録。この時期は波乱に富んだサントロの人生の中でも特筆に値する激動の時代であり、単に交響曲全集のうちの1枚というだけでなく、その時代を映した選曲がなされていることも興味を惹きます。 1960年、サントロは西ドイツ(当時)政府の招きでケルンを訪れ、その後電子音楽を研究するためにベルリンへ移ります。そこで体調を崩し資金にも難渋したサントロに支援を申し出たのが東ドイツの作曲家連盟で、彼は1961年夏を東ベルリンで迎え、8月13日のベルリンの壁着工を目撃することとなりました。 (曲目・内容欄へ続く)
収録作曲家:
-
アルメイダ・プラド(1943-2010):
オリシャたちの交響曲
ささやかなる葬送歌 [クラリッサ・カブラル(メゾ・ソプラノ)/サバ・テイシェイラ(バス・バリトン)/ニール・トムソン(指揮)/サンパウロ交響楽団&合唱団]REZENDE DE ALMEIDA PRADO, J.A.: Sinfonia dos orixás / Pequenos funerais cantantes (São Paulo Symphony Choir and Orchestra, Neil Thomson)
発売日:2023年05月26日
 NMLアルバム番号:8.574411
NMLアルバム番号:8.574411CD国内仕様 日本語訳解説付き価格:2,200円(税込)
ブラジル外務省が主導するプロジェクト「Brasil em Concerto」。19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲の作品をブラジルのオーケストラが演奏、録音するという、これまでになかった大がかりな企画です。 このアルバムに登場するアルメイダ・プラドは、20世紀後半から21世紀初頭にかけてブラジルで活躍した作曲家。カマルゴ・グァルニエリから音楽を学んだプラドは、やがてシュトックハウゼンやブーレーズ、リゲティの作品に興味を持ち、奨学金を得てパリに留学。ナディア・ブーランジェに教えを請うとともに、メシアンの神秘主義からも影響を受け、自国のブラジル音楽にこれらのエッセンスを融合させ、ピアノ曲集『カルタス・セレステス=天体の図表』などに見られる独自の作風を確立しました。 このアルバムに収録されている2つの作品は、作曲年代がほぼ20年離れており、彼の異なるスタイルが反映されています。初期の作品「詩人カルロス・マリア・ジ・アラウジョへのささやかなる葬送歌」は若くして命を落とした詩人に捧げる嘆きの調べ。合唱とパーカッションが効果的に用いられたオーケストラのための作品です。 対してカンピーナス市立交響楽団設立10周年のために書かれた「オリシャたちの交響曲」はブラジルの伝統的宗教と儀式、大いなる自然への賛美が描かれており、緻密なオーケストレーションと沸き立つようなリズム使用が際立つ作品です。深い森を思わせる神秘的な音色あり、原始的・異教的なリズムとサウンドの炸裂ありで、「春の祭典」のブラジル版と呼べるかもしれません。 ※ 国内仕様盤には木許裕介(日本ヴィラ=ロボス協会会長)氏による日本語訳解説が付属します。
収録作曲家:
-
カルロス・ゴメス(1836-1896):
オペラ序曲と前奏曲全集 [ファビオ・メケッティ(指揮)/ミナス・ジェライス・フィルハーモニー管弦楽団]発売日:2023年03月31日
CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
注目のNAXOSブラジル音楽シリーズ。
19世紀後半のイタリア・オペラ界に旋風を巻き起こしたカルロス・ゴメスが登場ブラジル外務省が主導するプロジェクト「Brasil em Concerto」。19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲の作品をブラジルのオーケストラが演奏、録音するという、これまでになかった大がかりな企画です。 今作はヨーロッパで成功を収めたブラジル人作曲家の草分け的存在、カルロス・ゴメスの作品です。リオデジャネイロ音楽院でイタリア人作曲家ジョアッキーノ・ジャンニに学び、卒業後すぐの1861年に最初の歌劇《城の夜》を上演。その2年後には2作目の《Joana de Flandres》でも人気を獲得。この2作の成功により当時の皇帝ドン・ペドロ2世から奨学金を授与され、1864年にイタリアへ留学してミラノ音楽院でラウロ・ロッシに学びます。1870年にはブラジルの先住民の物語を題材にした《グワラニー族の男》をスカラ座で初演し、ロッシーニやヴェルディと比肩されるほどの評判となりました。その後はブラジルとイタリアを行き来しながら創作活動を続け、60歳で亡くなるまでに全8作の歌劇と合唱曲、ピアノ曲などを遺しましたが、何と言ってもオペラ作曲家として高く評価されています。 このアルバムにはゴメスが書いた全8作の歌劇の序曲(前奏曲)他を収録。ゴメスの音楽には、20世紀に活躍したブラジル人作曲家の持つ民族的な雰囲気が前面に出ることはありませんが、ヴェリズモ・オペラの名旋律に通じる、パワフルで感情にダイレクトに訴えかける魅力があります。 ファビオ・メケッティはサンパウロ生まれの指揮者。ジュリアード音楽院で学び、ニコライ・マルコ国際指揮者コンクールで優勝。ワシントン・ナショナル交響楽団でロストロポーヴィチのアシスタントを務めました。2008年にミナス・ジェライス・フィルが創設されて以来指揮者を務め、このコンビの録音はグラミー賞に2度ノミネートされるなど、国際的に注目されています。 ※国内仕様盤には木許裕介(指揮者・日本ヴィラ=ロボス協会会長)氏による日本語解説が付属します。収録作曲家:
-
サントロ(1919-1989):
南アメリカ幻想曲集
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ [ナタリア・アウレア(ソプラノ)/クラウディア・ナシメント(フルート)/アルカディオ・ミンチュク(オーボエ)/オバニル・ブオシ(クラリネット) 他]SANTORO, C.: Fantasias Sul América / Sonata for Solo Violin (Soloists of the São Paulo Symphony)
発売日:2023年01月20日
 NMLアルバム番号:8.574407
NMLアルバム番号:8.574407CD価格:1,900円(税込)
ブラジル外務省が主導するプロジェクト「Brasil em Concerto」の1枚。19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲のブラジル音楽をブラジルのオーケストラが演奏、録音するという、これまでになかった大がかりな企画です。このアルバムでは、14の交響曲を含む600曲にものぼる作品を書いたクラウジオ・サントロの室内楽曲を聴くことができます。 1983年、リオデジャネイロで開催された若手音楽家のコンクール用に課題曲を求められたことがきっかけとなり、サントロは15曲から成る「南アメリカ幻想曲集」を作曲しました。当時彼が傾倒していた十二音と無調を基調としつつ、多彩なスタイルを持ち、高度な技巧を要求するこれらの作品は、 現在ブラジルの器楽奏者たちの重要なレパートリーとなっています。またトラック2、4、6、8はブラジリア大学の3人の教授からの依頼で作曲された、オーボエ、ファゴット、クラリネットのための短い作品で「南アメリカ幻想曲」の素材が用いられています。 最後に置かれた 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタは、21歳の若きサントロの実験的な作品。サントロ自身によって初演されており、素材の用い方などは後の「南アメリカ幻想曲」に通じるものがあります。
収録作曲家:
-
ブラジル皇帝 ペドロ1世(1798-1834):
テ・デウム
クレド [カルラ・コッテイーニ(ソプラノ)/ルイサ・フランチェスコーニ(メゾ・ソプラノ)/クレイトン・プルジ(テノール)/リチオ・ブルーノ(バス=バリトン)/ファビオ・メケッティ(指揮)/ミナスジェライス・フィルハーモニー管弦楽団/Concentus Musicum de Belo Horizonte(合唱)]PEDRO I of BRAZIL: Te Deum / Credo (Concentus Musicum de Belo Horizonte, Minas Gerais Philharmonic, Mechetti)
発売日:2022年09月09日
 NMLアルバム番号:8.574404
NMLアルバム番号:8.574404CD価格:1,900円(税込)
ナクソスがブラジル外務省との提携で進めているブラジル音楽のシリーズ、これは2022年9月7日のブラジル独立200年の記念日に相応しいリリースです。 ナポレオン戦争に巻き込まれたポルトガルの政治体制が混乱する中で、ポルトガル王家の王太子ペドロを初代皇帝ペドロ1世としてブラジルが独立したのが1822年9月7日。彼の言葉「独立か死か」はブラジル帝国のスローガンの一つとなりましたが、ペドロ1世は音楽の才能も優れ、「本格的な作曲家」として語ることが出来る歴史上稀な王侯貴族の一人です。当盤収録の「序曲」が1832年にパリで演奏された際は、この曲はロッシーニのものだと信じた聴衆が続出したといいます。 長男の洗礼を祝って書かれた「テ・デウム」はオペラを思わせるドラマティックな曲想を持ちます。「クレド」は歓喜に溢れ、ペドロ1世の作品の中でも演奏機会が多い曲の一つ。そして「ブラジル独立讃歌」は1822年から1831年頃までブラジル帝国の国歌として用いられた愛国歌であり、現在でもなおブラジルで愛唱されています。
収録作曲家:
-
Serenata セレナータ
小管弦楽のためのブラジル音楽集 [ニール・トムソン(指揮)/イギリス室内管弦楽団]Chamber Orchestra Music (Brazilian) - GOMES, C. / BRAGA, F. / NEPOMUCENO, A. / MIGUÉZ, L. (Serenata) (English Chamber Orchestra, N. Thomson)
発売日:2022年09月09日
 NMLアルバム番号:8.574405
NMLアルバム番号:8.574405CD価格:1,900円(税込)
-
-★『レコード芸術』特選盤(2022年8月号)★-
グァルニエリ(1907-1993):
ショーロ集 第1巻
セレスタ [オリガ・コピロヴァ(ピアノ)/アレシャンドリ・シウヴェリオ(ファゴット)/クラウディア・ナシメント(フルート)/ダヴィ・グラトン(ヴァイオリン)/サンパウロ交響楽団/イサーク・カラブチェフスキー(指揮)]GUARNIERI, C.: Chôros, Vol. 1 / Seresta (Kopylova, Silvério, Nascimento, Graton, São Paulo Symphony, Karabtchevsky)
発売日:2022年05月20日
 NMLアルバム番号:8.574197
NMLアルバム番号:8.574197CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
グァルニエリの父はイタリア系の移民で音楽を愛し、子供たちに付けた名前は、モーツァルト、ロッシーニ、ベッリーニ、ヴェルディ。カマルゴ・グァルニエリの本名はモザルト(モーツァルト)で、母親から手ほどきを受けたピアノ演奏と作曲で早熟の天才ぶりを発揮しましたが、後にはMozartの代りにM.とだけ書き、母の旧姓カマルゴをとって名前としたそうです。 グァルニエリは、ブラジルの作家・詩人・民俗学者で音楽研究者でもあるマリオ・ジ・アンドラージの民族主義的思想に影響を受け、西洋クラシック音楽をブラジル音楽の語法によって革新しようとしました。彼のショーロのほとんどは、ブラジルの伝統的なショーロとは異なり、3楽章または3部分構成の協奏曲スタイルで書かれています。「セレスタ(セレナード)」と題された曲も実質はショーロ。カルモ(穏やかに)と指示された緩徐楽章に漂う郷愁(サウダージ)や、急速楽章のホットな情熱が楽しめます。 ヴィラ=ロボス:交響曲全集で大きな評判となったカラブチェフスキー指揮、サンパウロ交響楽団の演奏。ソリストも楽団員です。 ※当ディスクは、ブラジル外務省の主導により19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲の作品をブラジルのオーケストラが演奏・録音する大プロジェクト「Brasil em Concerto」の一環です。 *国内仕様盤には指揮者で日本ヴィラ=ロボス協会会長の木許裕介氏の解説が付属します。
収録作曲家:
-
-★『レコード芸術』特選盤(2022年8月号)★-
グァルニエリ(1907-1993):
ショーロ集 第2巻
トレメンベーの花 [オバニル・ブオジ(クラリネット)/オリガ・コピロヴァ(ピアノ)/オラシオ・シャエファー(ヴィオラ)/マティアス・デ・オリベイラ・ピント(チェロ)/サンパウロ交響楽団/ロベルト・チビリサ(指揮)]GUARNIERI, C.: Chôros, Vol. 2 (Buosi, Schaefer, Pinto, Kopylova, São Paulo Symphony, Tibiriçá)
発売日:2022年05月20日
 NMLアルバム番号:8.574403
NMLアルバム番号:8.574403CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
グァルニエリの父はイタリア系の移民で音楽を愛し、子供たちに付けた名前は、モーツァルト、ロッシーニ、ベッリーニ、ヴェルディ。カマルゴ・グァルニエリの本名はモザルト(モーツァルト)で、母親から手ほどきを受けたピアノ演奏と作曲で早熟の天才ぶりを発揮しましたが、後にはMozartの代りにM.とだけ書き、母の旧姓カマルゴをとって名前としたそうです。 グァルニエリは、ブラジルの作家・詩人・民俗学者で音楽研究者でもあるマリオ・ジ・アンドラージの民族主義的思想に影響を受け、西洋クラシック音楽をブラジル音楽の語法によって革新しようとしました。彼のショーロのほとんどは、ブラジルの伝統的なショーロとは異なり、3楽章または3部分構成の協奏曲スタイルで書かれています。サンパウロ近郊の町にちなむ「トレメンベーの花」も3部分構成で、特に第3部分はラテンのノリが全開。20世紀音楽の語法を用いながら、緩徐楽章の哀感も急速楽章のホットな情熱も、これぞブラジル!といった雰囲気が満点です。 サンパウロ生まれのロベルト・チビリサの指揮、サンパウロ交響楽団と、その首席奏者を中心としたメンバーによる演奏です。 ※当ディスクは、ブラジル外務省の主導により19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲の作品をブラジルのオーケストラが演奏・録音する大プロジェクト「Brasil em Concerto」の一環です。 *国内仕様盤には指揮者で日本ヴィラ=ロボス協会会長の木許裕介氏の解説が付属します。
収録作曲家:
-
サントロ(1919-1989):
〈交響曲全集 第1集〉
交響曲 第5番&第7番「ブラジリア」 [ゴイアス・フィルハーモニー管弦楽団/ニール・トムソン(指揮)]発売日:2022年03月11日
CD国内仕様 日本語解説付き価格:2,200円(税込)
ブラジル外務省が主導するプロジェクト「Brasil em Concerto」。19世紀から20世紀にかけて作曲された約100曲の作品をブラジルのオーケストラが演奏、録音するという、これまでになかった大がかりな企画です。 ブラジル独立200周年の2022年、ブラジル音楽史上で最も重要なシンフォニストとされるクラウジオ・サントロの交響曲全曲録音がスタート。パリでナディア・ブーランジェに学んだサントロは、自身の作品にブラジル民謡のイディオムを抽象的に取り入れ、より創造的に発展させた形で表現しました。 1955年作曲、その翌年にリオデジャネイロで初演された「交響曲第5番」はサントロの代表作であり、第1楽章の神秘的な冒頭部分ではブラジル北東部の伝統音楽にみられる増三と短七度の和音を用いながらも、これらはサントロが独自に編み出した対位法の中に組み込まれています。パーカッションが活躍する熱狂的な第2楽章に続き、ブラジルの聖歌が用いられた変奏曲形式の第3楽章、そして終楽章は、ゆったりとした序奏に導かれ、最後に金管が高らかなコラールを奏し壮大に幕を閉じます。 1960年に作曲された「交響曲第7番」はサントロ作品の中でも最も複雑な作品とされており、また作曲家自身のお気に入りでもありました。4つの音符が印象的な第1楽章ではじまり、第2楽章アダージョが続きます。そして活発な第3楽章でも冒頭のモティーフは健在。最終楽章はすべてを統括するかのような多彩なモティーフが現れ、最後は激しいクライマックスを迎えます。 演奏は1980年に創設されたゴイアス・フィルハーモニーと首席指揮者のニール・トムソンが担当。エネルギッシュかつダイナミックな表現で定評があります。 *国内仕様盤には木許裕介(日本ヴィラ=ロボス協会会長)氏の日本語解説が付属します。
収録作曲家:
-
ヴィラ=ロボス(1887-1959):
合唱編曲集
バッハ、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン 他 [ヴァレンティナ・ペレッジ(指揮)/サンパウロ交響合唱団]VILLA-LOBOS, H.: Choral Transcriptions (São Paulo Symphony Choir, Peleggi)
発売日:2021年01月29日
 NMLアルバム番号:8.574286
NMLアルバム番号:8.574286CD国内仕様 日本語解説/歌詞訳付き価格:1,980円(税込)
クラシックの名曲をアレンジして歌った録音は過去に多くありますが、
これはヴィラ=ロボスによる合唱編曲という点に注目!ブラジルの民族音楽に根差したオーケストラ作品やギター曲で知られるヴィラ=ロボス。彼は生涯に1000曲ほどの作品を書きましたが、その中には数多くの合唱作品があります。 このアルバムでは、その中でもとりわけ珍しい“ヴィラ=ロボスによるバッハからロマン派作品の合唱編曲版”を収録。これらは主としてリオデジャネイロで活動していた「Choir of the Orfeão dos Professores=教師の合唱団」のために書かれたもので、ほとんどが1933年から1935年の間に初演されています。 原曲の多くは鍵盤曲ですが、ヴィラ=ロボスはこれらを見事にアレンジ。ベートーヴェンやシューベルト、シューマン、ショパンなどのよく知られた旋律が声による交響楽として生まれ変わっています。すべてア・カペラ(無伴奏)、2曲以外は歌詞を持たないヴォカリーズなので純粋に音楽として楽しめるのも魅力。また、ここには彼が敬愛したバッハの『平均律クラヴィーア曲集』からの合唱アレンジが全て含まれています。 *国内仕様盤には日本ヴィラ=ロボス協会副会長
清水安紀氏の解説・歌詞日本語訳が付属します。