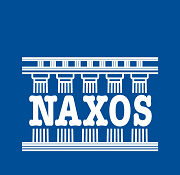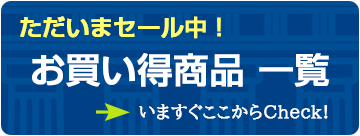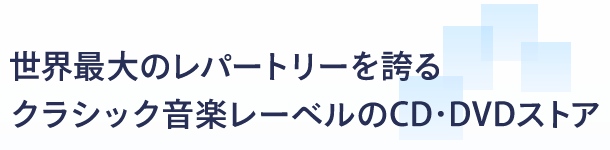ペトラッシ(ゴッフレード) Petrassi, Goffredo
| 生没年 | 1904-2003 | 国 | イタリア |
|---|---|---|---|
| 辞書順 | 「ヘ」 | NML作曲家番号 | 16092 |
-
ペトラッシ(1904-2003):
ピアノ協奏曲
フルート協奏曲
バレエ音楽「オルランドのフォリア」から [アンチロッティ/カニーノ/ローマ響/ラ・ヴェッキア]PETRASSI, G.: Piano Concerto / Flute Concerto / La follia di Orlando Suite (Canino, Ancillotti, Rome Symphony, La Vecchia)
■協奏曲
発売日:2014年03月26日
 NMLアルバム番号:8.573073
NMLアルバム番号:8.573073CD価格:1,900円(税込)
イタリアの作曲家、ゴッフレード・ペトラッシ(1904-2003)。カゼッラやマリピエロ、レスピーギなどの「新音楽協会」を結成した世代より少し遅れて生まれた彼は、そのキャリアのはじめの頃は新古典主義や旋法を用いた作品を書いていましたが、時代の流れには逆らい難く、無調や十二音技法にも興味を持ち、結局はこれらをうまく融合した独自の作風を貫くことで自らの作曲語法を確立させた人でもあります。 このアルバムにはフルート協奏曲とピアノ協奏曲、そして管弦楽曲の3つのジャンルの曲が収録されていて、彼の作風の変遷を辿ることができます。早い年代のピアノ協奏曲はまさに新古典主義の音楽で、プロコフィエフやヒンデミットを思わせるものですが、フルート協奏曲は明瞭な旋律線を感じさせない茫洋とした音楽。時折聞こえるパーカッションの音色が斬新です。バレ音楽はその中庸を行くもので、このまま映画音楽に仕えそうなほど、湧き立つような音の洪水が楽しめます。
収録作曲家:
-
スクロヴァチェフスキ
生誕100年を記念して
モーツァルト:レクイエム
ベートーヴェン:交響曲 第3番「英雄」他 [スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ(指揮)/ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 他]SKROWACZEWSKI, Stanisław: Centennial Tribute (A)
発売日:2023年11月17日
 NMLアルバム番号:CDAccordACD266
NMLアルバム番号:CDAccordACD266CD 3枚組価格:5,100円(税込、送料無料)
スクロヴァチェフスキ生誕100年を記念して
母国ポーランドの貴重音源が初CD化!指揮者・作曲家のスタニスワフ・スクロヴァチェフスキの生誕100年(2023年10月3日)を記念して、母国ポーランドのワルシャワ・フィルハーモニーのアーカイヴから1956年の録音が初CD化。正規盤の無かったモーツァルトのレクイエムや若き日の快速テンポによる「英雄」を含む興味深いリリースです。 スクロヴァチェフスキはポーランドのルヴフ(現ウクライナのリヴィウ)に生まれました。4歳でピアノとヴァイオリンを学び始め、特にピアノで目覚ましい才能を発揮して11歳の時にはデビュー・リサイタルを行うほどでしたが、第2次世界大戦中に手にケガを負い、その後は指揮と作曲に専心します。1946年以降はヴロツワフ、クラクフ、カトヴィツェのオーケストラで指揮者を務め、1956年にはローマで行われた国際指揮者コンクールで優勝。2年後にはジョージ・セルの招きでアメリカ・デビューを果たしました。1956年から59年にかけて、ポーランド国内ではワルシャワ・フィルのポストを得て定期的に指揮。ここに収められた2つのコンサートでは世界へ羽ばたく前夜の指揮を聴くことができます。全6曲中、「英雄」を除く5曲にはスクロヴァチェフスキによる正規録音が無かったので貴重なリリースと言えるでしょう。 (曲目・内容欄に続く)