

| このページは、私、桐田平八が、石川県輪島の漆器工房を訪問したときの知識に基づいて、蒔絵漆器のできるまでの行程を解説したものです。専門家ではないので、内容に不備な点がありましたらご容赦下さい。 | |
漆の木: |
|
 |
漆の実です。 |
 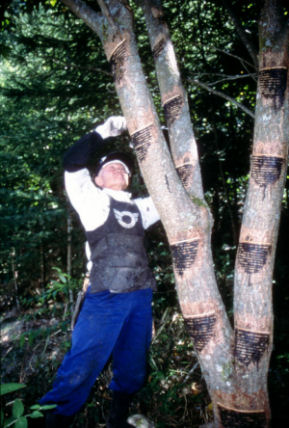 |
|
 |
見学した漆器ショップでは、実物の漆の木と掻く道具を展示していました。 |
| 塗り: 採取された漆液は濾過、精製され、器などに塗られます。 器の素材は当然木製が中心ですが、漆自体は素材を選ばず金属やガラスなどに塗ることも可能です。 塗りは下塗り、中塗り、上塗りを各3回程度ずつ、合計10回近くの重ね塗りを行います。 下塗りはへら、中塗り、上塗りは特殊な刷毛が使われます。 |
|
  |
重ね塗りをするため、器の素材はかなり薄いものが使われます。 |
  |
|
 |
下塗り |
 |
|
 |
上塗り |
 |
乾燥中です。 |
研磨: |
|
 |
下塗りの研磨。 |
 |
|
 |
上塗りの研磨 |
 |
器の各部位の曲線に合わせて、 それぞれ砥石を制作、使用します。 |
 |
箱物の研磨 |
 |
手作業です。 |
| 蒔絵: 漆器の表面に漆で絵や文様、文字などを描き、それが乾かないうちに金や銀などの金属粉を「蒔く」ことで器面に定着させる技法です。 |
|
 |
元絵の図柄を写し取ります。置き目 |
 |
地塗り |
 |
塗り込み |
 |
金粉蒔き |
 |
金粉入れ |
 |
研ぎ出し |
 |
椀のような丸物は展開図で描きます。 (ボールペンもですね。) |
 |
|
 |
|