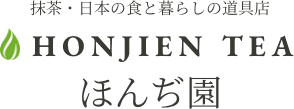はじめに

こんにちは。ほんぢ園にて買い付け・商品企画を担当しておりますマキノです。
今回は、新たにお取り扱いをさせていただくことになりました、木器作家の前田昌輝さんについてご紹介致します。工房にて取材させていただいた様子などもお伝えできたらと思います。
※本ページ掲載画像は2024年に撮影されたものです。掲載されている情報なども2024年当時の情報です。
《 工房紹介 》
前田さんは岐阜県多治見にて2015年より「タジェール・デ・マエダ」という工房で製作活動をされています。岐阜県多治見といえば、美濃焼など焼き物の産地としても有名で、焼き物の専門学校があったり多くの陶芸家さんが活躍されている土地でもあります。
前田さんの工房はご自宅兼作業場になっており、閑静な住宅街の中にありました。
▼ 作業場の前にひっそりと看板がありました。

▼工房内のギャラリーコーナー。

当店ではプロダクト色が強い「リバーシブルプレート」を販売中ですが、前田さんの魅力は素材そのものの魅力を活かす器作り。少し歪んだ形になっていたり、木の割れ目や虫食い後もそのまま活かした1点ものの器もたくさんありました。
《 日本の木工細工 》
ではここで、木工細工の世界について少しお話させていただきます。
日本は森林の多い地域であり、昔から木材を使用した道具が多く作られてきました。それと共に木材の加工技術も発展し、現在では全国で約80品目を超える伝統工芸品があります。木工細工は大きく分けて6つ種類があります。
・指物 (さしもの) 類
・彫物類
・刳物 (くりもの) 類
・挽物 (ひきもの) 類
・曲物類
・箍物 (たがもの) 類
● 指物(さしもの)類…
木の板に臍 (ほぞ) と呼ばれる凹凸をつくり、組み合わせてつくる技法です。約1000種類以上の組手があると言われる。釘を使わず、無駄のない美しさが特徴で、箪笥や棚、箱や本棚、火鉢などがつくられる。伝統的な貴族の調度品や茶道具づくりから発展した京指物と、江戸の武家や町民文化の下で培われた江戸指物が知られる。
● 彫物類…
木に文字や模様を刻んだり、彫ることで物の姿を現すこと。欄間などの建具や看板、家具の装飾、仏像や仏具に用いられることが多い。丸彫り、浮彫り、沈め彫り、透かし彫りなどの技法がある。木彫りのクマなどが有名。
● 刳物 (くりもの) 類…
木のかたまりから形をくりぬく、木工の原始。刳物は、木を鑿(のみ)や小刀などでえぐって鉢などをつくること。最も古い木工技術の一つで、自由な形態につくることが可能で、彫刻の原型とも言える。木の塊を削って食料などを入れる容器をつくったことが始まりとされる。山形県切畑の臼、奈良県の大塔坪杓子(おおとうしゃくし)や広島県のしゃもじなど現在でも器作りに使用されています。
● 挽物 (ひきもの) 類…
挽物は、轆轤(ろくろ)や旋盤(せんばん)に木材を取り付けて回転させ、刃物で削って椀や鉢、盆など円形の器や、家具の脚などの丸棒や筒をつくること。弥生時代には成立していた技法と言われ、現在、挽物の食器は漆を施して漆器として使われることが多い。京都の京漆器、福井県の越前漆器、石川県の輪島塗などが有名。
● 曲物類…
曲物は、薄い板を曲げて筒状にしてつくること。主にヒノキを用いるため、檜物(ひもの)と呼ぶこともある。桶や樽、御櫃や弁当箱といった様々な生活道具がある。秋田県の「大館曲げわっぱ」は曲物で唯一伝統的工芸品の指定を受けている。
● 箍物 (たがもの) 類…
箍物 (たがもの) は、板を円形に並べて箍で締めたもの。曲物にも桶はあるが、箍締めされた桶は結桶として区別された。 曲物よりも側板に厚みを持たせることが可能となったことで強度が増し、酒や味噌の仕込み、醤油や油などの輸送や貯蔵に役立ったことで、製造・流通が飛躍的に増加したようです。
以上が代表的な木工細工の種類です。
《 木工旋盤(もっこうせんばん) 》
木工加工について前述してきましたが、前田さんが加工に使用されているのは木工旋盤(もっこうせんばん)という機械です。上記の木工細工の種類ですと「挽物類」に該当されるものです。
高速回転する機械軸に木材をセットし刃物をあてて削っていくもので、陶芸に使われるろくろに似ていることから「木工ろくろ」と呼ばれることもあるそうです。回転しながら削る為、お皿や球体など丸いものを得意としています。
今回、実際に木工旋盤を使っている様子を見せていただきましたので画像と共にご紹介いたします。

▲ こちらが木工旋盤。左側の回転させる設置軸の部分を「主軸台」、手前に取り付けられているT字のものを「刃物台」と言います。刃物台は字の如く削るとき刃物を置いて加工を安定させるものです。

▲ 右側に映っている四角い木材を椀にしていきます。

▲ 刃物類もたくさん種類がありました。

▲ セットしているところです。主軸台の反対側のドリルのようになっている部分を「心押し台」と言います。

▲ 刃物を当てて削っているところです。

▲ 段々丸みを帯びてきました。

▲ 胴体が正円になりました。さらに椀の側面下部のデザインを整えていきます。この段階ではまだ器の底面は削りません。なぜなら、この後内側の加工を行う際、主軸台へ取り付ける部分が必要になるからです。

▲ 木材を反対側にひっくり返し、内側を削っています。

▲ 美しい木目の椀ができました。

▲ ここで一旦刃物を研ぎます。刃物は割とすぐ傷むので研磨は頻繁に行うそうです。

▲ 内側の仕上げです。紙やすりを当てながら回転させ、表面を滑らかにしていきます。

▲ 外側の仕上げです。
もう一度器をひっくり返し、底面の削りを行います。
内側はすでに仕上げているため主軸台に取り付けることができません。その為、緩衝材になるもの(今回は椀のサイズに合うお皿ですが、場合により色々使われるそうです)を主軸台に取り付け、さらに反対側の心押し台と共に2点で固定します。

▲ 最後の最後、木工旋盤から外したら底面の軸となっていた部分を手で取り、手作業で綺麗に削っていきます。これで完成です。

▲ 作業場全体風景です。旋盤で加工するので木くずもたくさん出ます。

▲ こちら作業中の前田さんです。真剣なまなざしです。

▲ 旋盤ではないですが、こちらは塗りの作業場。

▲ 漆の乾燥はこちらのボックスで。これから何層にも重ねていかれるそうです。

▲ 木材の節や穴などはそのまま活かす、前田さんらしさが詰まった作品です。
《 工房を訪ねてみて 》

今回、前田さんのご好意により木工旋盤を使用している様子まで拝見させていただくことができました。大変貴重な経験となり、ありがとうございました。
今まで陶器やガラスなど様々なクラフト作品に触れてきましたが、木工作品については初めてだったので個人的にすごく新鮮で楽しむことができました。
陶芸をはじめとする工芸品って、意外と、化学反応や物理法則の応用みたいな科学的な知識が必要だなって思うシーンがあるのですが、前田さんが使用されている旋盤による加工は、陶芸などの工芸品より工業的というか、機械的な要素が多いように感じました。実際モーター回転の機械を使用しているわけなので、機械のメンテナンスも自分でやる必要があるのかな?とか。
実際、前田さんの前職は車の整備をされていたようで、機械的な仕組みや思考など得意そう。(と、個人的に感じただけなのですが…笑)
前田さんがクラフト作家を目指すに至った経緯や、仕事や人生観に対する価値観などもたくさんお伺いすることができました。元サラリーマンという経緯に親近感を感じつつ、常にチャレンジ思考で前向きに行動されている姿勢に個人的に勇気づけられる思いです。
仕事とプライベートのワークライフバランスを大事にされている前田さん、そんな生き方の中で木工作品という職業に出会われたそうで、前田さんの作品の中には木が持つ癒し効果や優しさであふれています。食卓や暮らしの中で安心・安全な木の器があるということ、そんな思いを作品からは感じられます。
ぜひ、前田さんの作品、お手元にてご愛用いただけますとより一層良さが伝わるかと思います。取材させていただいた前田さん、ありがとうございました。

工房訪問時、おまけ話で。
美味しいドリップコーヒーと季節の和菓子までいただきました。
思わずシャッターを。笑
木の器ってメンテナンスは大変ですか?と尋ねると、子育てと同じだと語る前田さん。こうしよう、あーようとコントロールしようとしてもその通りにはならない、ざっくばらんに陶器の器などと同じように大事に、自由に、使っていけばきちんと育っていきますよ、と教えてくださいました。(※原則として、木の器は食洗器・乾燥器は厳禁です)
笑顔が素敵な前田さん、器に対する解釈もとっても懐が深いです。本当にありがとうございました。