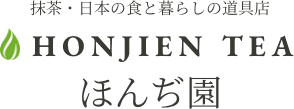はじめに

さてさて、こんにちは。
ほんぢ園にて買い付け・商品企画を担当しておりますマキノです。
今回は、年に1度の貴重な備前焼の窯焚きを取材してきました。その時の様子を記事にしてみましたので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。
まずは、ざっくりと、備前焼の説明です。
備前焼とは岡山県備前伊部地方にて焼かれている焼き物で、釉薬や絵付けを行わず、炎や灰の当たり方によって自然の模様を生み出す「窯変」が大きな特徴です。また日本六古窯の一つとされており大変歴史のある焼き物です。
高温でじっくりと焼くことで強度が増す「焼き締め」という製法をとっており、投げても割れないと言われるほど頑丈な備前焼は、その昔はすり鉢をはじめ、大ガメ、壺などの日用雑器から、茶道が発展した時代には茶陶としても全盛期を迎えました。
また、他の地域の焼物ではガスや電気式の窯が主流の現代において、薪を燃料とした登り窯・窖窯(穴窯・あながま)が主流です。(もちろん電気窯で製作されている備前焼作家さんもいらっしゃいます)備前焼は、釉薬を用いず土を焼き締めるという極めてシンプルな在り方ゆえ、その複雑な発色・土の質感を得るためには、薪窯による焼成が必要なのです。
今回、取材させていただいたのが、岡山県備前市に工房と窯を構える「Quiet House(クワイエットハウス)」さん。※以下「クワイエットハウス」と表記させていただきます。
*クワイエットハウスさんについて詳しくはこちら商品ページをご参考ください。
窯詰め〜窯出し、最後の仕上げの作業まで、クワイエットハウスの小橋さんと山村さんが大変丁寧に解説してくださいました。本当にありがとうございました!
工房をご紹介致します。
▼ クワイエットハウスさんのギャラリー兼工房です。

▼ こちらは窯がある建屋。煙突が見えます。

▼ こちら窯です。

とっても大きくて中は大人が立って入れるくらい大きいです。こちらの窯、元々は国指定伝統工芸士であった故「鷹取閑山(たかとりかんざん)」先生が使われていたもので、お弟子さんであったクワイエットハウスの小橋さんがお借りするという形で現在引き継いでおられます。
また、「閑山」という作家名は、この工房を構えている場所に由来されているそう。まさに文字通り、山の麓のとても静かな場所で、集中して作業するにはうってつけの場所だなと感じました。ちなみに「Quiet House」という名前も同じくこの静かな場所が由来となっています。
▼ こちらは店舗ギャラリーです。

清潔感のある真っ白な内装。
クワイエットハウスさんのシンプルな器もとっても映えます。
▼ こちらはギャラリー奥の作業場です。

ろくろやヘラなど製作に関する道具がたくさん並んでいます。
下の画像の棚は窯詰めの最中だったのでちらほら空きが見えます。

さて、次章では窯詰めの様子からご紹介します。
第1章《 窯詰め編 》
▼ 窯に詰める前の備前焼。

備前焼は素焼きなので、積み重ねて焼くことができます。
重ねる時、器と器の間に藁をかまします。こうすることで、器同士がくっつかず、また焼けの模様にもなります。

▼ 窯に詰められた状態の内部。

綺麗にぴっちりと並べられています。
クワイエットハウスさんの窯は一回の窯焚きで約2000点ほど入れれるそうです。
うつわを乗せている板は耐火性の板で、窯詰めの際に組み立てます。その為、通常窯内部はぽっかりと空洞になっています。
▼ カップを重ねておくと表面がバイカラーのような焼き色になります

上画像左側のカップ、重ねています。このように置くと焼きあがった時にバイカラーのような模様になります。(どんぐりの帽子みたいな感じです)
と同時に火入れによる歪み防止にもなります。火を入れると備前焼は一回り小さくなりますのでその過程で歪んでしまうことがあるそうです。その歪み防止の意味も込めてこのように重ねておいています。
▼ 工房から窯まで器を運ぶ山村さん。

クワイエットハウスさんのメンバーのお一人山村富貴子さんです。
普段は個人作家さんとして活動されています。
撮影の許可をいただきましたので、運んでる様子もご紹介致します。
運んでいる棚は工房棚にもありました、木製の板です。すべての器を手作業で運んでいく…、もちろん一気にではありませんが、神経も使うしなかなかの重労働だなと思いました。
▼ いたるところに積まれている器たち。

窯焚きの準備をしながら、点火の時を待ちます。

第2章《 窯焚き編 》
ついに窯焚き。ここでもう一度備前焼についておさらいです。
備前焼は薪を燃料とする登り窯で約10昼夜焼き続けます。期間は作家さんによってまちまちだと思いますが、今回クワイエットハウスさんは1週間の予定で組まれていました。窯焚き中の窯内部はおよそ摂氏1200度にも到達すると言われています。
今回、撮影取材にお邪魔したのが点火から4日目。
窯焚き全体の工程からみると中盤位の様子です。
▼ こちら下の薪投入口。焚き口と言います。着火時はここから火種を入れます。

▼ こちら上のメイン焚き口。蓋はあげると固定できる仕様です。

▼ 窯内部の様子です。

伺った時はすでに1000度に到達するかしないか位の温度でしたので、窯に近づくと熱気がすごかったです。
▼ 焚き口から薪を入れてる様子です。

静止画じゃなかなか臨場感が伝わりませんが、入れた瞬間、煙と炎が ぶわぁ!と出てきて迫力満点です。
▼ 薪を入れると黒煙が立ちあがります。

木炭の燃焼により煙が黒くなります。窯内部にもこの黒煙が立ち込め、この煙によって備前焼独特の赤茶色に色づきます。燃焼が終わると黒煙は消えます。
▼ 窯焚き記録と温度計。

薪を入れるタイミングですが、今回クワイエットハウスさんはタイマーで計測されていました。
窯内部の温度計も窯の横に設置してあり、途中経過はすべて記録されていました。
こちらの記録表、記録表でありながら事前に予定も書き込まれた日程表でもあります。いついつに何をする、という細かい指示や予定が書き込まれています。窯焚きが始まってしまうとノンストップなのでこれがあると目安になるし、来年の参考としても役に立つそうです。
▼ 積み上げられた薪。(窯焚き前)

備前焼の窯焚きでは基本的に「赤松」が使用されることが多いですが(油分が多く燃えやすい為)特に決まりはなく、こちらは「杉、檜、赤松」だそうです。全部で900束ほど使います。入れる木材によって色づきや模様の出方に変化がでるため、このように意図的に雑木(クヌギ、カシ、サクラ等)を混ぜる場合などもあるそうです。
▼ こんなに減りました。(窯焚き4日経過後)

撮影角度が違ってて差がわかりにくいですが…。めちゃくちゃ減ってます。
▼ 登り窯全体。傾斜になっていて、空気の通り道を作っています。

備前焼の登り窯について。まず、登り窯は火が窯全体に回りやすいように傾斜がついています。クワイエットハウスさんの窯も若干の傾斜のついた場所に窯がありました。
上で紹介した焚口のある一番手前の部屋のことを「ウド」と言い一番大きいです。その後ろにぽこぽこと「二番窯」「三番窯」と続き一番後ろの煙突手前の部屋を「ケド」と言います。部屋の大きさや数は窯によって違います。
ウド(一番手前の部屋)は、割り木を多く使うため、作品は渋めの色になることが多く、後ろの部屋になればなるほど少し浅めの色になります。また「ウド」は灰も多く被るので窯変強めのものができます。
▼ 器の配置表と二番窯横の小さな小窓。

前述のように置く場所によってできる作品に違いができるので、最初の窯詰めの段階で計算して置いていきます。上画像左は窯詰め時の配置表です。
「ウド」付近は窯変強めでざらつき多めのものができるので、花器やお皿など直接口に触れないようなものを置き、カップなどの口当たりが気になるものは後ろの部屋に置くなど、表現したい作品や用途によって分けているそうです。
上画像左の二番窯横の小さな窓。
画像はふさがっていますが、これ実は開きます。そしてここから木炭や灰などを入れて作品に模様や変化をつけていきます。木炭を投入するのでもちろん、中の組み棚は小窓を避けて設置されています。

窯焚き実況と解説については以上です。
窯焚きの解説などを聞いて思ったのが、土や割り木の種類・ブレンド、置く場所や火の調整、窯変の出方の調整など、備前焼って結構合理的で化学的な焼き物なのかなと感じました。芸術性やデザイン性の分野のようでいて、それを表現する為にすごく緻密に計算していかないといけないんだなと、感じました。
また備前焼のもつ効率性や「用の美」のようなものも感じました。
重ねて焼くことができるので効率よく詰めることができ、それが窯変の模様の出方にも繋がっている。また重ねるがゆえに藁を緩衝材としてかまし、それも模様の出方として捉える。
本来であれば制作側の都合やデメリットであったであろうことが、作品の出来栄えや模様に繋がるという美意識に、日本らしさや歴史ある焼き物だなという風にも感じました。
また、これは現場でも小橋さんとお話したのですが、備前焼の窯焚きって意外とハードじゃないんだなということ。もちろん、全体で見た時に大変であるのは大前提なのですが、私の中では、もっとせわしなく薪をくべ続け休む暇なくぶっ続けで作業をするようなイメージがあったからです。そのイメージよりは、静かというか、ゆったりされてる感じがしました。
実際は、割と待つ時間が多く、その間は焚火のパチパチという音を聞いていました。これは他の焼き物との違いでもあると小橋さんは仰っていました。
夏場だとまた違うのでしょうが…今回は11月だったのでそこまで暑くてたまらんってほどでもありませんでした。もちろん窯に近づくと熱気がすごいですが。
では、次章では「窯出し〜仕上げ」まで解説していきます。
第3章《 窯出し編 》
ついに窯出し編。濛々と焼かれ続けた器たちはどうなったのでしょうか。
この記事全体を通して述べている、備前焼の特徴である「窯変(窯の炎により作品に変化が生じること)」。この窯変、窯を開ける瞬間までわからないので、作家さん自身もドキドキの瞬間だと思われます。
窯を開けるタイミングですが、1週間から2週間ほど焼いた窯の中は非常に熱くなっています。火を止めてからすぐに窯を開けると、急激な温度変化によって作品が割れてしまいますので、1週間ほどかけて自然に冷まします。
今回、再び取材に訪れたのはすでに窯を開けてから1週間ほど経過した時でした。

▲▼ 二番窯の小窓から覗いた様子です。

焼きあがったばかりの作品は、まだ灰や藁、土などをかぶっている状態です。

▼ 器をすでに出した箇所は跡になっています。

▼ 一番手前の部屋「ウド」の内部です。

すでに窯出し開始から1週間程経っていたので一番手前のウドのものは全部出した後でした。
▼ 備前焼の模様を作り出すもの。

この丸い石のようなものは、焼き色をつけるためガラス繊維を丸めたもので、窯入れの時に作品に置いておきます。また器同士の緩衝材や丸みのある作品を寝かしておく際の支えにもなります。
このように備前焼は、制作時の実用性と作品としてのデザイン性を兼ね備えている工程や意味合いのものが本当に多いです。
▼ 窯から出した直後の作品。


窯から出したばかりの作品は、焼成時のガラス繊維や灰、藁などが付着していていますのでここから綺麗に磨いていきます。

ちなみにこちら、藁の燃えカスですが、この灰が燃焼時に化学反応を起こし、備前焼の表面にガラス質な膜を作ります。
釉薬を使わない備前焼ですが、表面がつやつやしていたり光っているもの見たことありませんか?あれは、このガラス質によるものなのです。なので、この藁の灰はまた来年用にとっておくそうです。
▼ 石と紙やすりで丁寧に仕上げていきます。

まずは砥石で大きなひっかりを、次に紙やすりで表面を滑らかに仕上げます。
カップやお猪口など口があたるものはより丁寧に「痛くないな」という程度にまで仕上げるそうです。
▼ 実はこの磨きの作業、筆者であるマキノも参加させていただきました。

私はプレートをさせていただいたのですが、まだ初心者向けでやりやすい部類のものだそうです。カップなどは取っ手があったり器自体が湾曲している為難しいです。
生まれて初めてこのスリ作業を体験したのですが、最初はどの程度すればいいのか、削りすぎて傷になったらどうしようなどと戸惑いましたが、小橋さんがとても丁寧に優しく教えてくださったので意外と楽しんでできました。
みんなで作業をしながらいろいろなお話もできたのでなんだか心地よい時間でした。
また、すりすりと手先で備前焼の質感を感じながら一つ一つ磨いていると愛着が沸きますし、全部こうやって人の手を介しながらできているんだなという実感にも繋がりました。このスリ作業の具合や程度なんかも作家さんの味に繋がったりもします。

2時間かけて、15cm程度のお皿4枚ができました。1枚30分程度でしょうか。
私が初心者だったことを考慮してもすごく地道で時間のかかる作業です。
この磨きの作業、テクニックとか技術とかよりも、とりあえず時間のかかる工程です。その為、この窯焚きの時期限定で磨きの作業をしてくださるご近所の方などもいらっしゃるそうです。窯焚きの薪くべもそうですが、このように地域一体連携をとって地場産業を支えているというのは伝統工芸などにはよく聞くお話です。
磨いたあとは、水でよく洗い、水漏れチェックをした後天日干しなどでよく乾燥させます。取材日にもこのように乾燥中の作品たちがたくさん並んでいました。
▼ 天日干し中の作品


▼ 材料となる土山

ちなみに土はどうされているのか伺ったところ、窯のある建屋の目の前に積んでいる土山を見せていただきました。こちら閑山先生の頃からあるそうです。
この土を水に溜めて泥状にし、純粋な生地用の粘土にしていきます。このブレンドする土の具合などで作品の仕上がりも異なってきたりします

ちなみに焼く前の生地の状態であれば土に戻りますので、成形の段階で失敗したものなどの残骸も積まれていました。
窯出しについては以上です。
第4章《 まとめ 》

いかがでしたでしょうか?
以上のような工程を経て、こちらの作品が私たちの元へ届いています。
私は自分の想像の10倍は大変だなと感じました。
備前焼を始めとするハンドメイド系の焼物は決してお安いものではありませんし、作られる量も限られています。しかし、それだけの価値があるということが、制作現場を介して知ることができました。これはまだ一部ですので。作品を焼くという、一部工程にすぎません。
また、備前焼のおおまかな製作過程や特徴など事前知識はある程度ありましたが、ここまで細かく取材できたのは良い機会だったと思います。こんなことしてたんだなぁとか、ここも考えられてたんだなぁとか。割といろいろな衝撃を私自身感じました。
今回の記事が少しでも備前焼の理解への参考になりましたら大変光栄です。今回の取材協力をしていただいたクワイエットハウスさん、本当にありがとうございました。
窯変や焼き締めなどの特徴から、芸術性や美術的な価値が注目されがちな備前焼ですが、クワイエットハウスさんが目指すのは「特別な日のためのものではなく 日々の暮らしのための器。」使ってこそ輝く器作り。
そして、今回2022年秋の窯焚きによる新物、ほんぢ園でも販売中です。
一つ一つ丁寧に作られたハンドメイド製品です。伝統による確かな技術と、現代の暮らしに寄り添った感性の備前焼、ぜひご自宅にてご愛用ください。