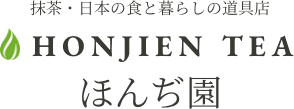はじめに

近年、おうち需要の高まりと共に、インテリアや暮らしの道具を楽しむ方が増えています。
今回は特に、暮らし系の道具の中でも人気の高い「器」にスポットを当てた記事を書こうと思います。器の種類から楽しみ方など、さらには器が作られる過程なんかも併せてご紹介致します。ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。
第1章《 器の種類 》

皆さん、「器」というとどんなものを思い浮かべますでしょうか?
器といってもジャンルは様々。
▼
テイストで分けると洋食器や和食器。
▼製造方法でわけると、量販店などの大量生産系、一つ一つ手作りの作家さんや窯元によるハンドメイド系のもの。
▼和食器の中ではさらに細かく焼き物の種類で分ける方法も一般的ですね。
→「美濃焼」「瀬戸焼」「有田焼」などなど。
▼また、形状・使用用途でも分けられます。
プレートやカップ、小鉢、茶碗・丼、大小から、カタチが正円のものから楕円形のものなど。
▼素材でわけることもできます。
美濃焼・益子焼などのザラザラとしていたり柔らかい質感が特徴的な陶器。有田焼・波佐見焼などの白くてつるっとした質感が特徴的な磁器。※この2つは主に含まれる成分によってこのような違いがでてきます。
ガラスや木製品などの器も食卓には欠かせません。
うーむ、器も沼ったらどこまでも果てしない…!
では、今回は特にほんぢ園でも取扱いのある和食器を中心に調べていこうと思います。
第2章《 和食器の種類 》

和食器も実は大きく次の3つに分けられます。
明確な違いがあるわけではないですが、個人的には以下のように分けようかなと思います。
【 工業製品、規格品 】
製品企画されたものを工場などでライン作業によってつくられます。均一レベルのものが大量にできる為、コストがかからず低価格、生産や品質が安定しているというメリットが挙げられます。
【 職人もの 】
熟練の技術をもつ職人さんの手によって、同一規格のものが作られます。同じサイズ、形状のものが人の手によって生み出されます。工業製品では出せない緻密な作業であったり人の手が加わることで作品として味わいがでます。日本の従来のモノづくりの流れとして、1つのものを作る為に各工程を職人同士でわける「分業制」などもこのカテゴリに属します。
【 作家もの 】
こちらも人の手で作られるという点は「職人もの」と同じですが、作る時により形や模様などに変化がある、という意味で「作家もの」と分けさせていただきました。
作るときの感性や環境などで風合いや具合も異なってくる為、
完成品は唯一無二の世界にひとつだけの器となります。作家ものの器は、作家さんが表現する世界観がベースになっていることが多く固定のファンがつくことも多いです。人の手でつくる味わい・深みなどは「職人もの」と同じと言えるでしょう。
さぁ、いかがでしたでしょうか。「器」ファンの方ならば、知ってて当然!という声を聞こえてきそうですが(笑)
それぞれにメリット・デメリットもありますし、予算やお好みなど選ぶ基準は様々です。
どのような器であっても、使う人が愛着をもって楽しむこと、それが大事だと思います。
第3章《器ができるまで(備前焼編)》
さてさて、次の章では、さらに器への理解を深める為に器がどのようにできるのか、を深掘りしていきます。数ある器の中でも、特にほんぢ園でもお取り扱いのある「備前焼」についてご紹介いたします。(下の画像は「鳴瀧窯」の安藤騎虎さんの作品です※時期により在庫状況は異なります。下記画像と同じものののご用意は致しかねます。)

■(ざっくりと)備前焼の製作工程
1.土作り(採土・粉砕・水ヒ処理・陰干し・荒練り・土を寝かす)※省略します
釉薬を使わないだけに、備前焼では土づくりに神経を使います。備前焼の原土は伊部周辺の地下にある粘土層で「ひよせ」といいます。作家の好みで山土を混ぜて使うこともあります。このブレンドの仕方や土作りも作家の個性の一つです。
2.土もみ(菊練り)
備前焼に限らず、陶芸家であれば必ず行う作業です。土の硬さを均一にし、土の中に入った余計な空気を抜き、扱いやすい土にして以降の作業をスムーズにするのが目的です。とても高度な技術が必要とされ、マスターするまで3年もかかると言われています。

3.成形
主にろくろを使って成形していきます。陶芸家、というとこのイメージが強いかと思いますが、作品の要と言える工程で、一度作り始めたら途中で止めることもできない為大変神経を使う作業です。
4.半乾燥
成形したものを一度乾燥させます。
5.削り(仕上げ)
半乾燥させて少し固まったものを削るようにしてさらに完成形に仕上げます。お茶碗の高台などはこの段階で作られます。
6.乾燥
完全に水分が飛ぶように乾燥させます。備前焼の粘土は、たいへん乾きにくい粘土で、急に乾かすと乾かしているときに割れてしまったり、真っすぐ作ったものが曲がったりします。その為できるだけゆっくりと乾燥させます。
7.窯詰め
備前焼は釉薬をかけない焼き物なので、窯に並べる時に重ねておくことができます。ですが、この置き方によって模様の出方や色など変わってくるので、どのような作品に仕上げたいかなど詰め方をよく考えなければいけません。作家さんの計算や経験、それにプラスして偶然がもたらす自然の模様、これこそが備前焼最大の魅力です。

9.窯焚き
登り窯による窯焚きは、年に1.2回ほどしか行われません。また、登り窯であれば5日間以上火を焚き続けます。窯の温度は1000度近く。この高温で焼くことでより頑丈に堅くなっていき、この製法のことを一般的には「焼き締め」と呼ばれます。
5日間24時間、窯には蒔きをくべ続け、窯の温度管理と時間管理がとても重要です。窯焚きはかなりの力仕事に重労働!近所の窯元同士で協力しながら進めるケースもよくあります。 また近年では電気窯も主流となっており、電気窯であれば作陶ペースに併せて作品を焼くことができます。
10.冷却期間(5〜10日程)
急激な温度差で作品が割れてしまう可能性があるため、乾燥と同じくゆっくりと時間をかけて温度を冷ましていきます。
11.窯出し
ついに作品のお披露目です。どれだけ計算を尽くして窯詰めしても、狙い通りの景色(模様)が出ないのが備前焼の面白いところであり、大きな魅力。世界にひとつだけの器が生まれる窯出しの瞬間は、作家にとっても楽しみの瞬間でもあります。
出したばかりの備前焼は灰をかなり被っている為、そこからさらに磨いたり水漏れのチェックをしたりと最終仕上げまで行い、作品として出来上がります。
いかがでしたでしょうか?これだけの工程をたいていの作家さんはお一人でこなしておられます。これらのすごさがぜひ伝わったら幸いです!
また何か機会があれば窯元さんの元へお邪魔して取材などさせていただけたらなと考えています!
第4章《器の楽しみ方(スタッフAさん)》
今回、本記事を書くにあたり、ほんぢ園の器好きスタッフAさんにお話を伺いました!
また、ご自宅にお邪魔させていただき、実際に器を見せてもらいながら、日頃愛用している器や好きな作家さんのお話、普段の生活の中でどのように器とかかわっているのかなど、伺いました。ご協力いただき本当にありがとうございました!

上の画像は、ほんぢ園スタッフAさんのお手持ちの器です。
ガラスが好きということで、食器棚には作家さんのものやご自分で手作り(!)されたという器がずらり!普段、量販店や100円ショップの器メインで使っている筆者からすると、憧れのライフスタイルだなと思っちゃいます!そしてもちろんすごく美しくてついじっと見てしまいます。うちにあるものと何が違うんだろう?どうやって作っているんだろう?と、なんだか製作方法や作り手の背景などにすごく興味が沸きました。
作家さんが作るクラフト品ならではの、質感だったりちょっと崩したようなディティール、また作家さんによる個性、表現する世界観、もちろん熟練された高度な技術など、いろんなものがこの器たちから感じられました。作家ものの器は、単なる造形美だけではない、人の手や想いが加わったストーリーも含めて器として魅力が増すのだと感じました。

上の画像は、最近購入されたという「Quiet House(クワイエットハウス)」さんのオーバルプレート。ほんぢ園で「Quiet House(クワイエットハウス)」さんのお取扱いを開始してから「Quiet House(クワイエットハウス)」さんの器が気になり、なんと窯元さんのギャラリーまで直接足を運んでいただいたとのこと!最初お皿を見た時は大きめの印象を持ったそうなのですが、ご自宅で使ってみると案外なんにでも使えて使いやすいそうです。カレーやパスタなどの深さが必要なものからこちらの写真のようにワンプレート風に盛り付けるのも様になります。また、「Quiet House(クワイエットハウス)」さんのまっすぐマグカップもご購入されたそうなのですが、その使いやすさにもとっても感動されていました。まさに「用の美」。そこを追求していけるのも日用品である食器ジャンルならではの魅力だと思います。
「Quiet House(クワイエットハウス)」さんはほんぢ園でもお取り扱いのある、「生活の為のシンプルな器」をテーマにアノニマス(無名性)デザインで企画製造されている備前焼の窯元さんです。ぜひ気になる方はほんぢ園のカテゴリもチェックしてみてくださいね。秋の窯焚きまで在庫が少な目ですが、また窯出しの時期には買い付けてきますのでお楽しみに!
また、お近くにお住いの方はギャラリーに直接行ってみるのもおすすめです。備前の静かな山のふもとでシンプルな店内には「Quiet House(クワイエットハウス)」さんの程よく可愛く主張少な目、だけど備前焼の味わいは感じられる、そんな器がずらりと並んでいます。OPEN日などは公式SNSなどチェックしてみてくださいね!

上の画像はAさん所有のガラスの器たち。手前のブルーのボウルはガラス作家の「中野由紀子」さんのもので、サラダを入れたり丼にしたりと重宝されているそうです。
奥のモールド状になっている足付きのグラスは「花岡央」さんのもの。こちらのグラスでお水をいただいたのですが、見た目に美しいのはもちろんのこと持った時の手の馴染みや縁の口当たりが優しく使いやすいなと感じました。どれも本当に素敵で私も何か欲しくなりました(笑)

最後に、質問形式でインタビューにご回答いただきました!
・器集め、器好きになったきっかけは?
Aさん:過去に陶芸体験をしたり、吹きガラスの講座に行ったりしたことをきっかけに作家さんの展示会に行ったりもして、興味を持ちました。 作り手を知っていると、器もなんとなく愛着がわく気がしています。
・どのようなジャンルの器が好きですか?
Aさん:シンプルなものが好きです。ごく最近、備前焼も好きになってきました。(いかにも、じゃないのが増えたからかも?)普段使いできそうなものをついつい買ってます。
・暮らしの中でどのようなシーンで使用することが多いですか?
Aさん:以前は割れるのが怖くてしまいこんでましたが、最近は、できるだけ使うようにしています。ふだんのごはんやデザートもちょっと贅沢している気分になれるのがうれしいです。
・今注目している焼き物・作家さんなどあれば教えてください?
Aさん:十河隆史さんの陶器、花岡央さん、中野由紀子さんのガラスが好きです。ごく最近、クワイエットハウスの備前焼を購入して、使いやすさに感動しています。
・あなたにとって「暮らしの中で楽しむ器」とは?
Aさん:少しだけ生活を彩ってくれるもの、という感じでしょうか。
大切な器だからと、食器棚に大事にしまい込んでしまうというのはよく聞きます。Aさんの「ふだんのごはんやデザートもちょっと贅沢している気分になれるのがうれしいです。」と言うように、使ってこそ、モノとしての価値が活きてきますし作り手の方にとってもきっと嬉しいと思います。
また、Aさんのように、陶芸体験や吹きガラス教室など、自分で作ってみるのもおすすめです!普段何気なく使っている器が、こんな風にできるんだなとかこんなに手間暇かかるんだってことが"自分ゴト"として捉えられるからです。作家さんの作品がより一層素敵で大切なものとして感じられますよ。もちろん、作った器も愛着がわいて可愛いです!(出来栄えは…もちろんプロにはかないませんが。笑)
Aさんが最後に仰っている「生活を彩るもの」。まさに、ほんぢ園が今後のコンセプトに据えている大事なキーワードです。ほんぢ園の提案する商品が少しでも「心豊かな生活」に繋がりましたら幸いです。Aさん、ご協力いただきありがとうございました。
さいごに

今回、「器」をテーマに記事を書かせていただき、作り手、使い手、様々な面からの見方が見えてきました。ただモノを作ればいいのなら、大量に安くできる方法は今の世の中たくさんあります。
しかし、あえて、人の手で作ることにこだわる、表現する世界を追求する、まさにそれは他の誰でもない自分自身と向き合うことなのだなと思います。そしてきっと、それに共感した使い手の方たちが暮らしの中で愛用することで完成するのだと強く感じました。
ほんぢ園ではそんなこだわりのモノづくり、想いの詰まった作品たちを介して「心豊かな暮らし」をご提案できたらなと考えています。そんな店づくり・商品ラインナップを目指して邁進していきたいと思っております。ぜひぜひ、皆様のご意見・ご感想などお待ちしております。では、最後までお読み頂き誠にありがとうございました。